
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
顧問先2200社を抱える会計事務所を率いる公認会計士、古田土満氏が語る小さな企業の経営のコツ。その第16回は、銀行が中小企業をどのように格付けしているのかを解説します。格付けは融資を受ける際に大きな影響を及ぼしますから、格付けのポイントを押さえておくことが重要だと、古田土氏はアドバイスします。
古田土会計ではお客さまの会社の決算書に「財務格付ワークシート」を添付して、都市銀行と同じ基準で格付けをして、銀行がお客さまの会社をどのように評価しているかを説明しています。格付けは定量評価のみで、決算書の数字を入力すると自動的に2決算期間の格付けが判定されるようにしています。
格付けは1~10まであり、自動的に計算される最低の格付けは7です。8~10は出しません。8は要注意先、9は破綻懸念先、10は実質破綻先です。出さないのは、これは銀行が判定するものだからです。先日ある都市銀行の方から、銀行の格付けの仕方について裏話を聞くことができました。裏話ですから、話半分で読んでください。
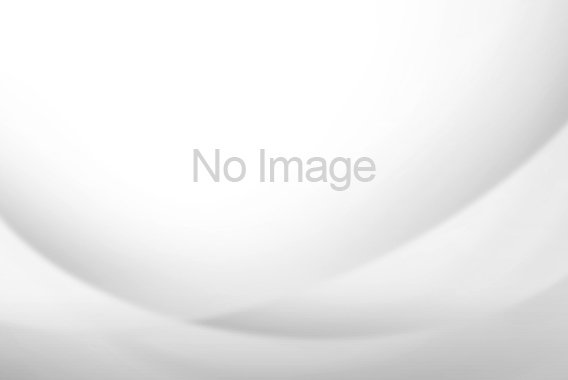 まず中小企業は、計算上の格付けが2とか3と高くなっても、付ける最高の格付けは4であること。貸倒引当率は1~7が2%、8の要注意先になると20%になり、9は80%、10は100%とのこと。
まず中小企業は、計算上の格付けが2とか3と高くなっても、付ける最高の格付けは4であること。貸倒引当率は1~7が2%、8の要注意先になると20%になり、9は80%、10は100%とのこと。
8に格付けされると引当率が大幅に上がり、銀行としては自己資本が減るので貸し出しをしないばかりか、回収に走ります。回収額が増えると引当額が減り、自己資本額が増えるからです。
なぜこの格付けが大事かというと、銀行の中で中小企業に対する見方が変わったからです。従来は担保主義で、総合的に与信判断していたものを、企業審査を標準化するため、定量評価(信用格付け)、定性評価によって判定するようになりました。従って、銀行から融資をしてもらうためには格付けを意識した経営が必要となります。
そこで定量面でのポイントは6つあり、次の6項目が全てOKなら融資するとのことでした。
(1)税引き後利益が2期連続して赤字にならないこと。
2期連続で赤字にすると、格付けは即、8以下になります。特別損失による赤字も同じです。特別損失は1期のみ、2期連続はまずいそうです。そして赤字の幅は5万円の赤字も、1億円の赤字も同じ扱いだそうです。
(2)実態純資産残高(自己資本比率)は10%以上
1桁はまずいそうです。表面上、30%は必要です。実態純資産残高の計算は、会社に繰り延べ資産があればその評価は0(ゼロ)。長期滞留、社長貸し付け、立替仮払金も評価0。入居保証金は金額の30%で評価します。では土地、建物をどのように見ているかというと、稼働資産は簿価評価だそうです。商売を前提として見ているからです。このように計算して純資産がマイナスになれば8評価になり、融資は打ち切るとのことです。
(3)債務超過の有無
帳簿上、債務超過になれば格付けは8以下になります。
(4)返済条件の変更
これは一発で8以下になります。銀行が貸してくれないから、返済額を少なくしようとして条件変更をするわけです。つまり、条件変更をする以前に8以下に評価されているわけです。よって貸し渋りに対して返し渋りをするのは、正しいと私は思っています。
(5)中小企業の特例
役員借入金は資本金扱い、また社長の個人資金と合算して考えるとのことです。
(6)借入償還年数の算定
これが一番重要で、この年数が10年を超えると格付けは8以下になります。以下の式で9年なら、10年になるまでは貸せるとのこと。ということは、10年になるまでが借入上限ということになります。この式の分母×10−分子の数字が、追加して借り入れできる借入可能額ということが分かります。また、定性要因によって格付けを上方修正することは原則ありません。こうした銀行による格付けの性質を活用して、銀行からも信頼してもらえる決算書を作り、資金で苦しまない会社づくりをしたいものです。
〔総借り入れ(含む社債)−現預金−(受取手形+売掛金+商品−支払手形−買掛金)〕÷〔税引き後利益+減価償却費(※貸しビル、倉庫、ホテル業は償却期間20年で計算)〕
※本記事は、2017年に書籍として発刊されたものです
執筆=古田土 満
法政大学を卒業後、公認会計士試験に合格。監査法人にて会計監査を経験して、1983年に古田土公認会計士・税理士事務所を設立。財務分析、市場分析、資金繰りに至るまで、徹底した分析ツールによって企業の体質改善を実現。中小企業経営者の信頼を得る。
【T】
人気会計士が語る、小さな会社の経営“これだけ”