
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
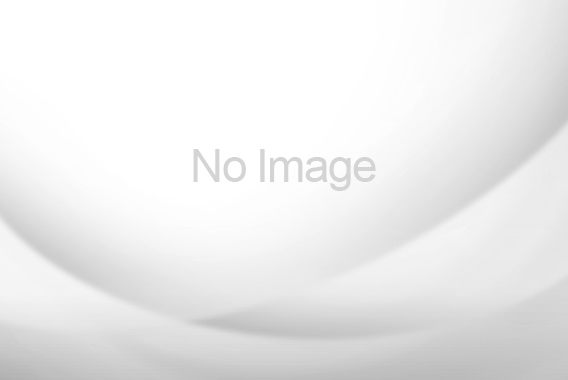
2019年10月、消費税率引き上げと同時に軽減税率制度が始まり、請求書の発行・保存方法がそれまでの「請求書等保存方式」から「区分記載請求書等保存方式」に変わった。そして、2023年10月1日からは「適格請求書等保存方式」、通称“インボイス制度”に移行する。インボイス制度は、軽減税率制度による複数税率に対応し、消費税の仕入税額控除の金額を正しく計算するために導入される制度だ。
単一税率であれば、適用する税率や税額が明記されていなくても仕入税額の計算ができた。だが複数税率の場合、これらの記載がなければ正確な仕入税額の計算ができない。ちなみにインボイスとは、定められた事項が記載された請求書、納品書、領収書、レシートなどをさす。
インボイス制度において、売り手は定められた事項が記載された請求書を交付し、税率ごとの合計対価、税率ごとの消費税額などを買い手に伝える。買い手は交付されたインボイスに基づいて仕入税額を算出し、自らも定められた事項が記載された領収書を発行する。
インボイス制度は、仕入税額控除の金額を正しく計算するために、企業規模を問わず対応しなくてはならない。それに伴い、企業の業務負担が増す可能性が生じる。例えば、請求書、領収書のフォーマットは「登録番号」「税率ごとの消費税の合計額」を記載できるものに変更する必要が出てくる。
インボイス制度は、消費税を納める義務のある課税事業者が対象だ。対象となる課税事業者はあらかじめ税務署長に申請を行い、適格請求書発行事業者の登録を受けなければならない。この登録に伴って発行されるのが登録番号だ。
また、現行の軽減税率制度では10%、8%と2種類の税率の消費税が併存する。インボイス制度では、消費税10%の品目の消費税の合計額、消費税8%の品目の消費税の合計額の記載が義務付けられる。もちろん記載に当たっては、それぞれの税率で消費税の合計額を算出しなくてはならない。
それだけではない。インボイス制度は、消費税を納める義務のある課税事業者だけが対象だ。免税事業者からの仕入れは適用外となるため、課税事業者から交付されたインボイスとしての請求書と、免税事業者の請求書の仕分け作業が必要となる。そのほかにも入金消込・会計仕訳のためにインボイスに記載される税率ごとの本体金額と税額の仕分け作業が発生する。また、発行者・受領者双方に7年間の保管が義務付けられる。
インボイス制度では交付された請求書が課税事業者のものなのか、免税事業者のものなのかを仕分けなければならない。受け取った請求書が、制度で定められた適格な請求書なのかも確認しなければならない。現在のように紙の請求書でこれらの判断・処理を行うと、非常に手間を要し業務効率の低下が懸念される。各社のフォーマットに基づいて発行した紙の請求書では、課税事業者と免税事業者の仕分けだけでも一苦労だ。
また、前述のようにインボイス制度では受領者は原本を、発行者は副本を7年間保管する義務があり、紙のインボイスだと保管の手間とコストがかかる。こうした負担を軽減したいなら、請求業務などは紙ではなく電子化が有効な手だてになる。
そうした必要性に対応するため、2020年7月、電子インボイス推進協議会が発足した。協議会は、クラウド会計ソフトで高いシェアを持つ弥生や「勘定奉行」で知られるオービックビジネスコンサルタントなど、大手のビジネスソフト会社10社を発起人として立ち上げられた。
協議会では、インボイスの処理がスムーズに行えるよう標準化された電子インボイスの仕様を策定し、クラウド上で利用できる電子インボイス・システムの構築をめざす。このシステムでは請求書の作成・処理がクラウド上でできるほか、取引先への入金や領収書の作成を自動的に進める機能も加えられる方針だ。まずは2020年内をめどに仕様を策定し、2021年から認知と普及の促進活動を実施する。
インボイスの仕様が統一されて電子化が進めば、企業は請求書・領収書の発行、処理に関する手間やコストが削減される。もちろん、システムの導入に際しては、ある程度のコストが生じるものの、政府もインボイス制度の導入に際しては電子化が重要という認識があり、導入費用については補助金の供出などを検討している。
インボイス制度は2023年からの開始が決まり、多くの企業は対応が必須になる。制度の開始に伴って増える作業の効率化を図るために、中小企業でも電子インボイス・システムをあらかじめ導入しておくべきだといえる。協議会の動向や、導入補助金制度のスタートに注目しておきたい。
執筆=山本 貴也
出版社勤務を経て、フリーランスの編集者・ライターとして活動。投資、ビジネス分野を中心に書籍・雑誌・WEBの編集・執筆を手掛け、「日経マネー」「ロイター.co.jp」などのコンテンツ制作に携わる。書籍はビジネス関連を中心に50冊以上を編集、執筆。
【TP】
雑談力を強くする時事ネタ・キーワード