
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
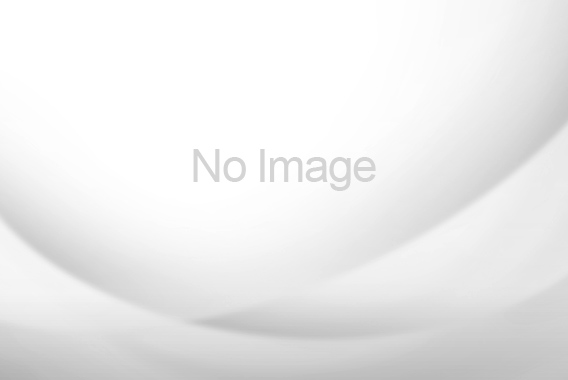
世界各国は気候変動に悪影響を与えると考えられる二酸化炭素の排出を、限りなくゼロに近づける「脱炭素社会」の実現に向けた取り組みを推進しています。この脱炭素社会を実現するには、政府だけでなく、経済活動の担い手である各企業の協力が欠かせません。本記事では、なぜ脱炭素社会を実現することが重要なのか、脱炭素社会の実現のために個々の企業ができる取り組みとは何かを解説します。
目次
・脱炭素社会とは温室効果ガス排出量が実質ゼロの社会
・環境省が掲げる2050年カーボンニュートラルの実現
・脱炭素社会が求められる背景
・脱炭素社会実現に向けた施策
・環境省が行う補助制度一覧
・脱炭素社会実現の可能性は
・まとめ
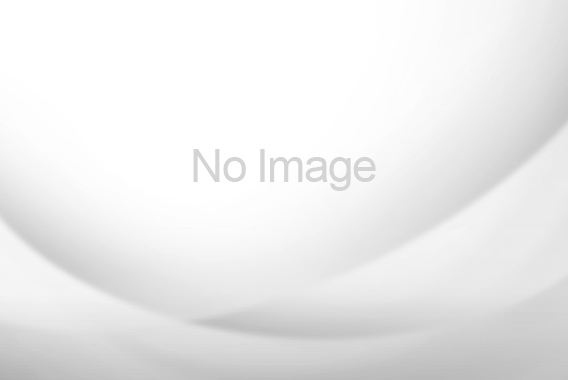
脱炭素社会とは、化石燃料に頼った技術や生活から脱却し、二酸化炭素の排出量を限りなくゼロに近づける社会のことです。
地球温暖化の原因であると考えられている温室効果ガスには、二酸化炭素をはじめ一酸化炭素、メタンなどが含まれます。この中でもその大部分を占めているのが二酸化炭素であるため、「脱炭素化」が重要視されています。太陽光発電や風力発電、バイオマス発電などの再生可能エネルギーの利用を促進したり、電気自動車などのクリーンなエネルギーで動く技術を普及したりするのも、脱炭素化に向けた取り組みの1つです。
カーボンニュートラルとの違い
脱炭素社会と関連性の深い概念として、「カーボンニュートラル」が挙げられます。カーボンニュートラルとは、二酸化炭素の排出量と吸収量を相殺させて実質ゼロにすることです。「ネットゼロ」という言葉も、基本的にはカーボンニュートラルと同じ意味合いとなります。
現在の技術レベルでは、二酸化炭素をまったく排出しない(化石燃料をまったく使わない)で、従来と同等のエネルギーを確保するのは難しいのが実情です。例えば、最近では電気自動車が普及しつつありますが、飛行機や貨物船などを電気で動かせるようになるにはまだ多くの時間がかかることが予想されます。
このような事情から、ある程度は二酸化炭素が排出されるのを許容する替わりに、排出された二酸化炭素を大気中から除去しようというのがカーボンニュートラルの考え方です。実際の手段としては、植林や二酸化炭素を吸収・除去する技術を開発することで、カーボンニュートラルを推進できます。
脱炭素社会は二酸化炭素排出量を限りなく「ゼロ」に近づける社会を示しますが、その過程でどうしても二酸化炭素は排出されるため、カーボンニュートラルによって排出量の「プラスマイナスゼロ」をめざしているのが現在の状況です。
関連記事:人ごとではない「カーボンニュートラル」
低炭素社会との違い
脱炭素社会と類似した概念として「低炭素社会」もあります。低炭素社会とはその名の通り、二酸化炭素排出量が少ない社会です。化石燃料の使用量を減らし、二酸化炭素排出量を低くするという考え方となります。低炭素社会のコンセプトを発展させたものが、脱炭素社会となります。実現のプロセスとしても、脱炭素社会を現実にするためには当然、前段階として低炭素社会になることが必要です。
日本の環境省は2050年までにカーボンニュートラルを実現することを宣言しています。具体的には、2030年度までに温室効果ガスを2013年度比で46%削減することを中間目標とし、その後2050年までにカーボンニュートラルを実現するという計画です。
この宣言に先駆けて2020年10月、菅義偉首相(当時)は所信表明演説において、気候変動対策はもはや経済成長の制約にはならないと強調し、カーボンニュートラルを本当に実現するために考え方を切り替えていく必要性を語りました。2050年までにカーボンニュートラルを実現するという宣言は、アメリカやEUもすでに行っています。
世界的に脱炭素社会の実現が求められる背景としては、いくつかの理由が考えられます。
地球温暖化の深刻化
世界が脱炭素社会の実現に向けて動き出した理由の1つは、温室効果ガスの増加に伴う地球温暖化が深刻な問題になっているからです。産業革命以降、人間が生み出す温室効果ガスは増加の一途をたどり、地球の平均気温は2020年時点で19世紀の工業化以前と比べて約1.1度上昇したと報告されています。
温暖化によって、台風や洪水、熱波などの異常気象や海面上昇による海岸線の浸水など、人々の暮らしや生命を脅かす多くの自然災害が頻発する恐れがあります。さらに、干ばつによる食糧不足の発生も憂慮されます。このような事態を防ぐため、温暖化の原因となる温室効果ガスを削減することが求められています。
化石燃料への依存
化石燃料への依存を解消するのも、脱炭素化の目的の1つです。現在、日本における主要なエネルギーは石油や石炭、天然ガスなどといった化石燃料に大きく依存しており、しかもそのほとんどは海外からの輸入に頼っています。
こうしたエネルギー資源は有限のものであり、国際情勢の緊張などによって供給が不安定化することも懸念されます。そのため、再生可能エネルギーの利用や開発を進め、化石燃料への依存から脱却することが重要になる、というわけです。
運送業の脱炭素化の遅れ
日本においては、各国に比べて運送業における脱炭素化が遅れていることも懸念されています。環境省の資料「2020年度(令和2年度)温室効果ガス排出量(確報値)について」によると、電気・熱配分後の二酸化炭素排出量において、運輸部門は産業部門に次いで大きな割合(19%)を占めています。
運送業における運搬手段である飛行機や自動車の動力は、現状は化石燃料が主流です。逆に言えば、欧米と比べて遅れている運送車両の電動化などを進めていくことで、脱炭素社会へ向けて大きく前進できることになります。
世界人口の増加
国連経済社会局人口部が2022年に発表した「世界人口推計2022年版」によると、世界人口は2022年中に80億人を突破し、2050年までに97億人に到達する見込みです。世界人口が増加していく中で、これまで通りのエネルギー政策を維持していけば、二酸化炭素の増加はさらに加速していくことでしょう。そのため、人口の増加と共に増大していくエネルギー需要を満たしつつ温室効果ガスの排出を抑制するために、脱炭素化に取り組むことが重要です。
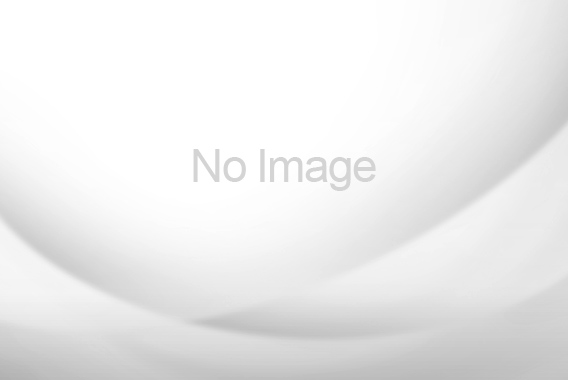
脱炭素社会を実現するためには、どのような取り組みを行うのが良いのでしょうか。具体的な取り組み例と、日本政府による施策例をいくつか紹介します。
再生可能エネルギーの導入
脱炭素社会を実現するためには、経済のあらゆる部門において、温室効果ガスの排出を大幅に削減することが必要です。例えば、発電を化石燃料から風力や太陽光発電などの再生可能エネルギーに切り替えることで、二酸化炭素の排出量を大幅に削減できます。各企業や各家庭単位でも、事務所やビル、家屋の上に太陽光パネルを設置し、太陽光発電で得たエネルギーを自家消費分に充当するなどの取り組みが可能です。
食品ロスの削減
食品ロスの削減も重要です。環境省の発表によれば、2020年度の食品ロス量は約522万トンと推計されています。温室効果ガスはごみを焼却する際にも発生するので、可燃ごみとして出される大量の廃棄食品を減少させることは、二酸化炭素排出量の削減にもつながります。食品ロス問題を改善するためには、正確な需要予測に基づいて過剰生産や期限切れなどによる廃棄を減らすことが重要となります。
カーボンオフセット
脱炭素社会を実現するには、カーボンオフセットも欠かせません。カーボンオフセットとは、二酸化炭素の排出を削減しきれない分を、植林や土壌の管理、あるいは環境保護活動への寄付によって埋め合わせることです。二酸化炭素削減に取り組んだうえで、解決しきれない部分を補うための施策となります。
ESG経営の促進
脱炭素化に向けた取り組みは、ESG経営の一環として捉えられます。ESG経営とは、「環境(Environment)」、「社会(Social)」、「企業統治(Governance)」の3つの面を重視した経営のことです。脱炭素化はこの中で、環境の領分に属します。昨今ではESGへの取り組み方を投資先決定の評価指標とするESG投資が広がっており、金融庁や東京証券取引所もESGを含む非財務情報の開示を全上場企業に求めるようになりました。
地域脱炭素ロードマップの策定
環境省では、「地域脱炭素ロードマップ」を策定しています。同ロードマップでは、脱炭素化を地域レベルで推進すると同時に、その取り組みを地域経済の活性化や地域の課題解決に結びつけるための取り組みや施策の具体例が記載されています。脱炭素化を効果的に進めるためには、自治体、企業・金融機関などが協力することが重要です。地域レベルで脱炭素化を進める中で、同ロードマップは参考になることでしょう。
改正地球温暖化対策推進法の成立
日本政府は、2021年に改正地球温暖化対策推進法を国会で成立させました。これは2050年までにカーボンニュートラルを実現することを法律に明記したものです。この法律によって、脱炭素政策の一貫性を高め、脱炭素社会の実現に向けた取り組みや投資、イノベーションが加速されることが期待されます。
環境省では、脱炭素化に向けた取り組みをする企業に対して補助制度を提供しています。ここでは、その中から2022年に実施された3つの補助制度を紹介します。
自立・分散型エネルギー設備導入推進事業の支援
再生可能エネルギー設備の導入支援を目的にした制度です。エネルギー設備の導入を支援し、その設備で生産されたエネルギーを災害時などに地域の公共施設に転用できるようにする狙いもあります。主な補助対象は、再生可能エネルギー関連の施設導入費で、支給上限額は500万円です。
建築物などの脱炭素化のためのZEB化支援
環境省は、災害対応や感染症対策と共に、脱炭素化に資する建築物の導入支援も行っています。ZEBとは「ネット・ゼロ・エネルギー・ビル」の略称で、自然エネルギーの利用やエネルギーの高効率化、建物構造の高断熱化などによって、二酸化炭素排出量の大幅な削減を実現したビルのことです。補助費用の上限は最大5億円となっています。
脱炭素型カーシェア促進の支援
再生可能エネルギー設備の導入および社用車を地域住民とカーシェアリングすることを要件に、電気自動車の導入を支援する補助制度です。さらに、電気自動車を災害時の蓄電池として活用されることも想定しています。補助金の上限額は申請全体で1億円です。補助金や補助率の上限は、車両や設備の種類ごとに個別に設定されており、例えば電気自動車の導入なら100万円(補助率1/3)が上限額になっています。
「二酸化炭素の排出をゼロにする」ことについて、途方もないことのように感じる人も多いかもしれません。しかし、環境省の発表によると、2020年度の日本における温室効果ガスの総排出量は二酸化炭素に換算して11億5000万トンであり、すでに前年度比5.1%減に成功しています。
地球温暖化やそれによる異常気象などはすでに現実のものとなっており、たとえ困難なことであっても、「無理だ」と放り投げるわけにもいかない問題です。二酸化炭素排出量の削減を推進し、植林や二酸化炭素を吸収・除去する技術などの開発も加速していくことで、脱炭素社会に向けて取り組んでいくことが重要です。
脱炭素社会を実現するために、日本政府は現在、二酸化炭素排出量と削減量をプラスマイナスゼロにする「カーボンニュートラル」を推進する法律や補助制度の整備に取り組んでいます。各企業はこうした補助制度を適宜活用し、再生可能エネルギーの導入などを通して自社の二酸化炭素排出量を削減していくことが求められています。
※掲載している情報は、記事執筆時点のものです
執筆= NTT西日本
【MT】
覚えておきたいオフィス・ビジネス情報のキホン