
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
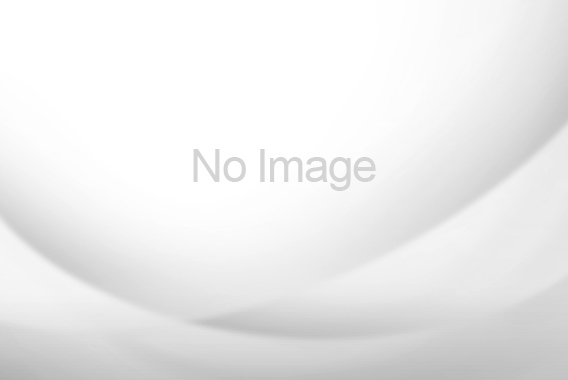
前回の「正しい考え方を身につける」の中で、その方法として『論語』や『老子』など、長い間、多くの人が正しいと認めてきたものをまず勉強するようお勧めしました。今回はその『論語』について深掘りしてお話ししようと思います。
『論語』は2500年もの間、多くの人が正しいと言ってきたものです。私も正しいと思っています。『論語』は儒教の考え方を端的に表しているもので、その中でも私が大切にしている言葉がいくつかあるのでご紹介します。
1つは孔子の弟子で曾参という人がいて、論語の中では曾子と呼ばれている人の「吾、日に三たび吾が身を省みる」という言葉です。自分で自分の身を毎日3回振り返るんだと言っているのですね。自分を省みることがとても重要だと。
コンサルタントとしてたくさんの経営者を見てきた経験から、成功している人には共通点があると思っています。1つは何事に対しても前向きな姿勢の持ち主であること。やはり前向きでないといろいろなことにチャレンジしませんから、経営者としてとても大事です。それからもう1つは利他心。自分だけではなくて、他の人も良くしようという気持ちを持っているということも重要です。
そしてもう1つの共通点が反省するということではないかと思います。経営がうまくいかない経営者、会社をつぶしてしまった経営者は大抵独善的なんですね。この連載をお読みになっている経営者の方の中には、イケイケドンドンの人もいらっしゃるのではないかと思います。もちろんその姿勢で今までも今後も、売り上げを伸ばして高い利益率を実現していれば何の問題もありません。けれども実際にはイケイケドンドンで前向きに取り組み、周りの人を思いやっているのに、なぜか業績が悪いという方が結構いらっしゃるわけです。
その場合は、やはり反省がとても大切です。同じ失敗を二度とやらない。あるいは失敗していないまでも、売り上げが落ちてしまった、利益率が下がってしまったという場合に、自分や自社には何が足りないのかと考える。人のせいにしていては、うまくいきません。松下幸之助さんもおっしゃっているのですが、うまくいったときは「自分は運が良かった」と思ってください。反対に失敗したときは、「自分のどこが足りなかったのか」を真剣に考えるのです。
ポジティブなのは良いことですし、前へ、前へと進んでいくのもとても良いことです。ただ、良いときも含めて必ず反省を忘れてはいけません。経営者の皆さんには「どうしてダメだったのか」「より良くするには、どうすればいいか」を繰り返し考えてほしいのです。
一代で1万人を雇う一部上場会社をつくった社長と、あるとき二人で食事に行きました。その席で私が「反省は大事ですよね」と話を振ったら、驚いたことにその社長は「小宮さん、違うよ」とおっしゃるんです。その後、どんな言葉が続いたと思いますか。社長いわく、「反省では足りない。自己否定だ」と。私は結構なショックでしたね。でも自分に対して「今の自分ではダメなんだ」と厳しく律する姿勢だからこそ、自分の会社をここまで成長させたのだと納得しました。「好調だから、今後もこれでいいだろう」という気持ちでは到底無理だと思います。
『論語』の「晏平仲、善く人と交わる。久しくして之を敬す」という言葉も私は好きです。晏平仲というのは孔子の時代の小さな国の宰相でして、人とよくつき合った。「久しくして之を敬す」というのは、人は長くつき合うほど晏平仲を尊敬したという意味です。
そのために大切なことは2つあって、1つはぶれないということです。言っていることがコロコロ変わると、尊敬されるなどあり得ません。もう1つは進歩するということです。何も変わらなくても人はつき合うでしょうが、尊敬され続けることはないでしょう。ぶれずに、そして日々新たな進歩を目指す姿勢がとても大事だと私は考えています。
●経営習慣の確認ポイント
うまくいったとき、「自分のおかげ」と過信していませんか
執筆=小宮 一慶
経営コンサルタント。株式会社小宮コンサルタンツ代表取締役CEO。十数社の非常勤取締役や監査役、顧問のほか名古屋大学客員教授も務める。1957年、大阪府生まれ。京都大学法学部卒業後、東京銀行(現・三菱UFJ銀行)入行。米ダートマス大学タック経営大学院に留学、MBA取得。1991年、岡本アソシエイツ取締役に転じ、国際コンサルティングに従事。1996年に小宮コンサルタンツを設立。
【T】
どんなときでも稼ぐ社長の経営習慣