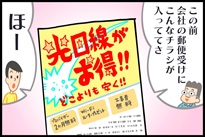
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線

社長の仕事と社長の時間についてお話をしたいと思います。私は経営という仕事を次のように定義しています。それは3つありまして、1つは「会社を方向付けする」。自分が経営する会社は何をやるのか、何をやめるのかを決めるのです。
2つ目は「会社が持つ資源を最適配分する」。経営者は限りあるヒト、モノ、カネを最適に配分し、私利私欲に走ったり、公私混同をしたりしてはいけません。当たり前に聞こえますが、これがすごく大切なんです。
そして3つ目は、「人を動かす」ことだと思っています。社長の仕事は企業の方向付け、資源の最適配分、人を動かすこと。中小企業の場合は当然、こうした経営ばかりというわけにはいかないかもしれません。
しかしこの3つについては、部下は絶対にやってくれないし、できない仕事なんですね。ですから、経営者自身が企業の方向付け、資源の最適配分、人を動かすということにどれだけ時間を使っているかを、改めて考えないといけないわけです。
その際に自社の事業を定義しておく必要が出てきますが、1つヒントになると思い、お伝えしたいのは、私の好きな本である『ビジョナリー・カンパニー2 飛躍の法則』に書かれている一節です。先ほど申し上げた方向付けをするときには注意しなければならないことが1つあります。『ビジョナリー・カンパニー2』には、事業を飛躍的に伸ばした会社が事業をどうやって定義しているかについて書かれています。
これには3つありまして、1つは「世界一を目指す」。中小企業の場合、事業を世界一にするのは大変かもしれないので、まずは「小さな日本一」を探してみてはどうかと私はよくアドバイスしています。これは、おのずと他社との差別化につながりますので、とても有効です。2つ目は、その目指す日本一が経営者自身や社員も含めて、全員が「わくわくする」かです。そして3つ目は、なおかつそれが「経済的原動力になる」かどうか。つまり、それが結果的に売り上げを伸ばして利益を出せるかどうかという視点です。
これら3つの重なるところを事業として定義していく。繰り返しますと、世界一ではなく小さな日本一でも構わないので1番になること。働く人がわくわくすること。なおかつ経済的原動力になること。この3つを定義しながら方向付けをやっていくのが大事なのです。
ここで経営者の皆さんに振り返ってほしいのですが、1日の限られた時間をどんなことにどの程度使っているでしょうか。私は経営者が働いているときに、3つの時間の使い方があると思っているんです。
①機会を追求している時間かどうか。
②現状の事業を維持するために使おうとしている時間かどうか。
③問題解決に使っている時間かどうか。
いうまでもないですが、多くの社員は現在の事業を維持するために結構時間を使っています。これは当たり前の話で、当面のキャッシュフローを生み出すために、しっかりやってもらわないと困ります。場合によってはクレーム対応のように、問題解決に時間を使うときもあるでしょう。
ただし、経営者に求められるのは機会の追求です。新しい事業に取り組んだり、お客さまに新たな提案をしたりといったことに、自分は多くの時間を割けているかを留意しないといけません。もちろんクレームには先頭に立って対応しなければなりませんが、最悪の場合、問題解決にばかり時間を取られている経営者がいるかもしれません。でもそれはマイナスの状態から普通の会社になるための時間ですから、いわば本来はかける必要がない時間です。会社が伸びていく要素にはなり得ません。
この考え方は会社全体で捉えても同じで、機会追求、現状維持、それから問題解決の3つそれぞれに、人員や他の資源をどんな割合で配置しているかについても、十分に検討していただきたいと思います。
●経営習慣の確認ポイント
現状維持や問題解決ばかりに時間を費やしていませんか
執筆=小宮 一慶
経営コンサルタント。株式会社小宮コンサルタンツ代表取締役CEO。十数社の非常勤取締役や監査役、顧問のほか名古屋大学客員教授も務める。1957年、大阪府生まれ。京都大学法学部卒業後、東京銀行(現・三菱UFJ銀行)入行。米ダートマス大学タック経営大学院に留学、MBA取得。1991年、岡本アソシエイツ取締役に転じ、国際コンサルティングに従事。1996年に小宮コンサルタンツを設立。
【T】
どんなときでも稼ぐ社長の経営習慣