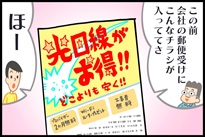
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
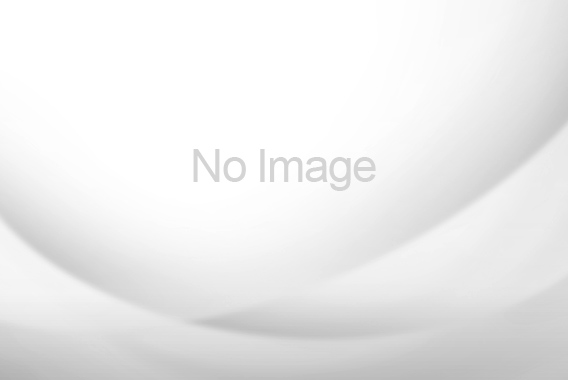
朝礼は中小企業にとって2つの目的を果たすために欠かせないと、私は考えています。1つは「社員教育」で、もう1つは「経営者の姿勢を示す」ためです。
会社が成長するには生産性を上げていかなくてはならず、社員の「基礎力」を高めることはその土台となります。仕事の意味を理解する力を高めるとともに、仕事に向き合う意識も高める必要があります。
例えば、上司から「コピーを100枚取ってほしい」と言われれば、部下の誰でもその意味を理解できます。しかし、「どんな目的で必要なのか」「誰が読むのか」「100枚で過不足はないのか」などに気を配れるかどうかは、部下によって違います。全員をそういった人材に育てるためには「意識」が鍵を握ります。
そんな意識教育の格好の場になるのが朝礼です。私がコンサルタントとしてお付き合いする会社には、環境整備すなわち整理整頓と掃除の徹底を勧めています。目的はきれいなオフィス環境で仕事をするためだけではありません。日々の変化に気付く意識を養うためでもあります。
「今朝は○○さんの机の周りにゴミが多いけれど、昨日は忙しかったのかな? 今日は私が何か手伝えるようにしておこう」などと変化に気付き、次の準備しておく。こうした仕事への意識や気付きこそが、生産性や質の向上につながるのです。
これは、毎日トレーニングを続けてこそ身に付きます。もう1つの目的は経営者の姿勢を示すためで、この点においても朝礼は格好の場になります。私の会社では、全員参加の朝礼は創業時から欠かしません。
15分ほどの環境整備に始まり、その後、当番が経営理念と取り組み方針を読み、各人が今日行う仕事の内容報告と情報共有、最後に当番のスピーチで締めくくる。これが1日の仕事を始める区切りにもなるのです。在宅勤務が増えた今でも、ビデオ会議サービス「Zoom」で在宅勤務者に参加してもらっています。
我々のようなコンサルタント業にとって、環境整備は社員とお客さまの両方に向けて大切です。なぜなら優れた戦略を立てても、理屈だけが先立って手を動かさない人間を周りは信用しないからです。論理だけでは目の前に落ちているゴミが片付かないのと同じで、実際に手を動かして初めてコンサルタントは信用されるのです。
この話は、経営者にもそのまま当てはまると思います。経営者自らが環境整備では手を動かさないのに、経営理念や方針でどれだけ美辞麗句を並べても、社員の心には響きません。社員を金もうけの道具と思っているような経営者ほど、自分から動こうとしないものです。社員たちはきちんと見抜いています。
●経営習慣の確認ポイント
環境整備や朝礼を毎日行っていますか
執筆=小宮 一慶
経営コンサルタント。株式会社小宮コンサルタンツ代表取締役CEO。十数社の非常勤取締役や監査役、顧問のほか名古屋大学客員教授も務める。1957年、大阪府生まれ。京都大学法学部卒業後、東京銀行(現・三菱UFJ銀行)入行。米ダートマス大学タック経営大学院に留学、MBA取得。1991年、岡本アソシエイツ取締役に転じ、国際コンサルティングに従事。1996年に小宮コンサルタンツを設立。
【T】
どんなときでも稼ぐ社長の経営習慣