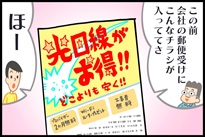
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
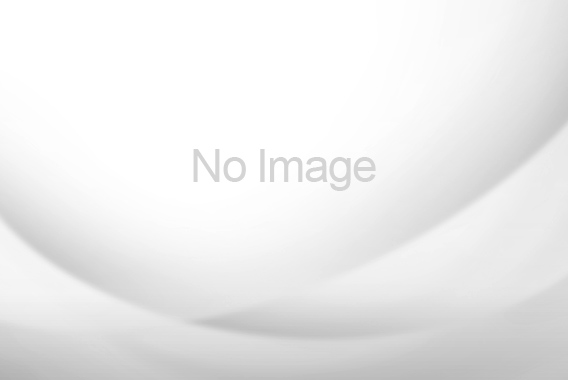
新型コロナウイルスの猛威によって世界経済が受けたダメージは計り知れません。そして、東日本大震災なども含めたこれまでの経済危機とは違う点があります。まずダメージそのものが大きい。そして環境変化に伴う社会全体の対応が不可逆的であると考えられます。つまり、もう元には戻らないことも多くあるということです。
ここで会社を経営する皆さんに強くお伝えしたいことがあります。経営環境は変わりますが、経営の本質や原理原則はコロナ感染拡大が収束した後のニューノーマル(新常態)でも変わりません。それどころか、重要度はより増します。
本連載は私が経営コンサルタントとして20年以上にわたり多くの大企業や中堅中小企業の経営者や経営を見た結果、導いた経営の原理原則についてまとめたものです。原理原則は大企業にも中堅中小企業にも共通して通用するものでなければ、本物ではありません。すぐに実践できるよう、分かりやすく解説していきます。経営を振り返り、明日に生かすきっかけとしてご活用ください。それでは第1回として経営の本来の目的から説明しましょう。
経営の原点でまず大事なことは、「目的」と「目標」の違いを認識することです。皆さん、目的と目標という2つの言葉を知らず知らずのうちに使い分けているのではないでしょうか。けれども、この目的という言葉と目標という言葉がいかに違うかという点をきちんと理解しておくことは、経営においてもそうですけれども、人生においてもとても大切なことなのです。
目的というのは最終的に行き着く所で、存在意義そのものと言ってもいいかもしれません。それに対して目標はというと、その目的に達するための通過点や目的達成のための手段だと私は考えています。
分かりやすく具体的にご説明します。私の場合、「経営コンサルタントの小宮一慶」としての目的は、関わるお客さまに成功していただくこと。これが存在意義、目的です。一方、私が目標として長い間持っていたのは、おかげさまで達成しましたが本を100冊出版することです。
ただし、100冊の本を出して目標を達成したからといって、目的も達成したかというとそれは別の話。私が現役で働いている限り、関わるお客さまに成功していただくという目的は、ずっと存在し続けるのです。
皆さんはご自身の会社の目的というものが何かをきちんと考えたことはあるでしょうか。皆さんの会社の存在意義です。目的と目標の違いをはっきりさせることがとても大事ですけれども、どの会社にも共通してある目的は、1つは「良い商品やサービスを通じてお客さまに喜んでいただいて社会に貢献する」。これが大きな存在意義です。別にこれはいい格好を言っているのではなく、これなくして成り立つ会社はありません。そして、それとともに、「働く人を活かし幸せにする」ことも大きな存在意義といえるでしょう。
それに対して、売上高や利益は目的ではなくて目標です。良い商品やサービスを通じてお客さまに喜んでいただいて社会に貢献したり働く人を活かし幸せにしたりすると、その結果、目に見える売上高や利益となって表れてくるわけです。だから、売上高や利益は、ある意味、目的が達成できているかどうかを確認する物差しであり、同時に目標だと私は考えています。
働く人がしんどくなる会社は、本来は目標であるべき売上高や利益が目的化してしまっている会社です。売上高や利益だけを考えて経営者も社員も働いているから、疲れるのです。お客さまのことが売上高や利益達成のための手段となってしまっては、会社はやはりうまくいかなくなるのです。そうならないようにするために、自社の本来の目的は何だったのかということを、時々きちんと振り返ることが大事になってきます。
もちろん、売上高や利益を軽視していいと言っているわけでは決してありません、先ほど申し上げたように自社の本来の目的が達成できているかどうか、きちんと追求できているかどうかということを判断するための尺度ですから、私は売上高や利益の出ない会社はまったく信じません。ただし売上高や利益が目的化している会社には関わりたくありません。結局うまくいかないからです。世間も働く人も、そんな会社を好きではないのです。
私の人生の師匠は禅寺のご住職の藤本幸邦(こうほう)先生という、99歳でお亡くなりになった方でして、私によくおっしゃっていました。「お金を追うな、仕事を追え」と。これはまさに目的と目標の違いです。良い仕事をする、つまり仕事を追うことが目的であって、お金はその結果ついて来るものなのです。
この「お金を追うな、仕事を追え」という考え方は、日本固有のものではなく普遍のようです。数年前に2泊3日でモンゴルへ講演に行ったことがありました。現地の企業のご依頼を受けての講演だったのですが、その企業はとても大きくて、1万人もの人を雇っているような会社でした。モンゴルは人口が約320万人しかいない国です。そんな中で1万人も雇っているということは、とても巨大な企業といえます。
銀行やカシミヤ工場、日本の自動車メーカーのディーラー、ホテル、外資系の小売りなどを20社弱経営する巨大グループを1代で作ったオーナーはモンゴル人で、実は日本の大学を出ていて日本語を流ちょうに話せます。その創業者が新聞に掲載された私の書籍の広告をご覧になって、私に講演を依頼されたのです。内容は幹部300人を前に1日かけて講演するというものでした。
講演を私がお引き受けすると、創業者の方が単身で当日の打ち合わせをするために、東京にある当社にやって来られました。そして創業者から講演で話してほしいとお願いされたテーマが「お金を追うな、仕事を追え」でした。モンゴルでも、やはり成功している人は同じ考え方を持っているそうです。自分がいつも考えているこのことを、まったくの他人である私の口からいろいろ解説してほしいとのことでした。
「講演をウランバートル市の本社で行うと、幹部の意識が変わりにくい」という創業者の考えで、会場を市内からわざわざ50㎞ほど離れた草原の中の施設に移しました。講演に先立って、相手はモンゴルの人たちですから、何をしゃべってもいいのでしょうかと確認したら、本当に思っていることを率直に話してほしいとおっしゃいました。おかげで、講演の反応はとても良かったです。
そこですごいなと思ったのが、私は松下幸之助さんが好きで、東京の自宅にいるときは、毎晩、松下さんの『道をひらく』という本を必ず読んで寝る習慣があります。その話を講演で披露したところ、創業者がすぐに松下さんの本を買ってきなさいと周りに指示を出しました。300人ほどの幹部の中で20人ほどは日本に留学経験があり、日本の大学や大学院を出ている人たちなので、日本語が分かるとのことでした。その人たちが分担して『道をひらく』の内容をモンゴル語に翻訳して、幹部で読み合わせをする場を用意するようにしたいというのが創業者の狙いでした。
やはり世界中どこでもそうですが、世の中が求めているのは良い仕事なんですね。だから、やっぱり「お金を追うな、仕事を追え」ということを根本にすると、日本でもモンゴルでも成功するんだと改めて強く感じました。このモンゴル出張の前日までは米国に出張していたので時間的、体力的には結構厳しかったのですが、私に非常に貴重な経験を与えてくれたと思っています。
●経営習慣の確認ポイント
本来の目的をないがしろにして売上高や利益を追っていませんか。
執筆=小宮 一慶
経営コンサルタント。株式会社小宮コンサルタンツ代表取締役CEO。十数社の非常勤取締役や監査役、顧問のほか名古屋大学客員教授も務める。1957年、大阪府生まれ。京都大学法学部卒業後、東京銀行(現・三菱UFJ銀行)入行。米ダートマス大学タック経営大学院に留学、MBA取得。1991年、岡本アソシエイツ取締役に転じ、国際コンサルティングに従事。1996年に小宮コンサルタンツを設立。
【T】
どんなときでも稼ぐ社長の経営習慣