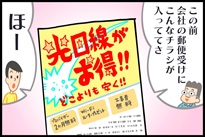
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線

前回、目標の定め方のポイントについて解説しました。その中で、顧客が求めていることの実現を目標にして、それから数値に落とし込んでいくようお勧めしました。今回は、その数値目標に対する姿勢について注意を促したいと思います。それは、全力で頑張れば達成できる高い目標を設定し、それを達成するために力を尽くすというものです。
皆さんの会社では年間目標や月間目標を立てているところが多いと思います。私が経営している社員15人の会社も、もちろん目標を設定しています。目標についてはいろいろな考え方があると思いますが、私は目標というのは達成するもの、達成すべきものだと考えています。
どうしてそう考えているかというと、私はこれまでにたくさんの会社を見てきましたが、ずいぶん高い目標を立てて、8割程度達成できればいいかなどと考えている経営者が珍しくはないんですね。そのやり方を続けると、目標は達成できないのが当たり前という思考になりがちで、私は反対の立場です。年間目標や月間目標といった大きな目標に対して、「達成しなくても当たり前」という姿勢でいたら、その手前のもっと小さな目標も達成しなくて当たり前と考えてしまうようになると思うのです。人生の目標も同じです。
私が親しくさせていただいているお客さまの中に、自動車部品メーカーがあります。その会社は自動車メーカーに部品を納めています。自動車メーカーは日本でも海外でもジャストインタイム生産で、在庫は徹底的に回避するようにしていて、部品メーカーの立場からすると非常に大変です。決められた数の部品を、決められたある一定期間のうちに納入しないとペナルティーを課されてしまいますから。しかも、シックスシグマといって100万分の1個単位の不良率に抑えないと許してもらえないそうです。
このような厳しい環境にさらされている会社が、もしも目標達成は適当でいいよ、8割達成できればいいよという姿勢でいたら、その日からもう会社として成り立たなくなるでしょう。日本の自動車メーカーや部品メーカーが強いのは、この非常に厳しい環境の中で毎日鍛えられているからです。
この記事を読んでいる方の中には、上場会社で働いている方がいるかもしれません。私も今までに上場会社4社の社外役員を務めてきました。ご存じの方がいらっしゃるかもしれませんが、上場会社においては売上高が開示している業績予想より1割、利益の場合は3割上振れもしくは下振れした場合は、外部開示義務により即座に公表しないといけません。
ですから上場会社の場合は、期初に立てた目標を達成するのは半ば当たり前になっています。目標の立て方自体が曖昧で、目標を達成できてもできなくても、「まあ、いいか」と済ませてしまう中小企業の経営者を見ると、とても残念に思います。
目標についてもう1つ言及すると、「ストレッチ目標」という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、この言葉を多くの人が誤って理解しているような気がします。ストレッチ目標は「頑張る目標」ではありません。もともと米国のGE(ゼネラルエレクトリック社)で使われていた目標設定の仕方で、外部環境と内部環境がベストの状態のときに、売上高や利益がどれだけ出るかを事前に決めたものをストレッチ目標と呼びます。
ビール会社を例に挙げると、ビールという飲み物は気温次第で売り上げが大きく変わります。外部環境の1つである「夏の想定最高気温の平均が33度」とか、内部環境なら「営業人員が充足した」「工場の稼働率が100%」など、すべてが100%想定している状況になったときに実現する売上高や利益がストレッチ目標となります。
その際、例えば「最高気温の平均を33度」と見積もっていたところ、蓋を開けたら連日35度の炎天下が続いて見込みよりもたくさん売れたとしても、その好業績は経営者の手腕とはいえません。あくまでも想定していた内部環境を100%達成することが大前提となるのです。
目標を決める以上、必ず達成するという姿勢で精いっぱい努力する。ただし低い目標を立てて達成しても意味はありませんから、覚悟を持って、全社が思い切り頑張れば達成できるというレベルの目標を立てて、それを達成させることが大事なのです。
●経営習慣の確認ポイント
「目標は8割達成したら十分」と緩く考えていませんか
執筆=小宮 一慶
経営コンサルタント。株式会社小宮コンサルタンツ代表取締役CEO。十数社の非常勤取締役や監査役、顧問のほか名古屋大学客員教授も務める。1957年、大阪府生まれ。京都大学法学部卒業後、東京銀行(現・三菱UFJ銀行)入行。米ダートマス大学タック経営大学院に留学、MBA取得。1991年、岡本アソシエイツ取締役に転じ、国際コンサルティングに従事。1996年に小宮コンサルタンツを設立。
【T】
どんなときでも稼ぐ社長の経営習慣