
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
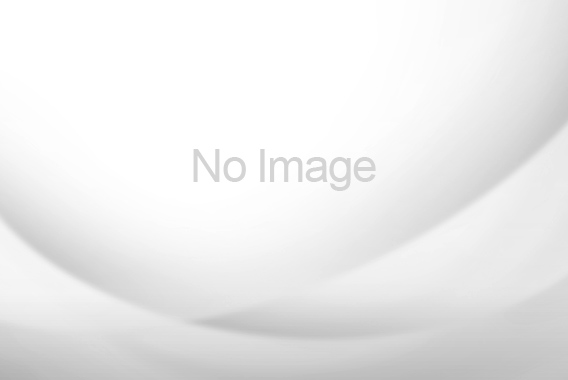
今回は、ビジネスや人生でとても大切な利他心について、解説したいと思います。利他心は「他を利する心」と書きます。人生がうまくいく人とうまくいかない人に分かれる大きな要因になっていると思っています。利他心を持ってビジネスや人生に向かっていくのかどうかで、その後の結果は大きく変わるのです。
ビジネスというのは、お客さまに喜ばれる商品やサービスを提供したり、周りの人と協力したりして仕事をし、結果を出していくことです。皆さんはこれまでを振り返ったとき、利他心を優先させてきたでしょうか。それとも自己中心的な考えを優先させてきたでしょうか。
以前、こんなことがありました。寒かったので、私はある店で鍋を食べていました。カジュアルな店で、低いパーティションで仕切られた向こうのテーブルから食事中の人たちの声が聞こえてきました。おそらく4人だったと思います。年齢は40 歳くらいの課長と部下の方3人で、鍋を囲みながらお酒も飲んでにぎやかにされていたのですが、耳に入ってくる彼らの話を聞いていて、「この人たちは将来きっとうまくいかないだろうな」と思ったのを覚えています。短い時間居合わせただけなのに、私がどうしてそう思ったかがお分かりでしょうか。
「もう少し頑張って、ボーナスをもらおうよ」と課長さんが言うと、部下の人も「それはいいですね」と応じていて、私もそれ自体が悪いとは思いません。ただ、1時間くらい話している内容が、「自分たちがいかにお金をもらうか」ということに終始していたんです。どうやら営業職のようだったので、お客さまにどういう提案をするかということが話の中心であれば利他だと思います。しかし自分たちがいくらもらうかとか、どうやってもうけるかとか、そういった自己中心的でお客さまそっちのけ、会社全体のこともそっちのけのことばかりを考えていたら、きっと行き詰まると思います。
ビジネスはお客さまに商品やサービスを差し上げることであり、それが良い商品やサービスであるほど利他になります。結果として売り上げや利益がついて来るのは間違いありません。けれども自分たちがいくらもうけるかしか考えていないようであれば、それは「自己中」でしかありません。皆さんの会社の売り上げや利益や働く人の給与などは、お客さまにとっては、全く知ったことではないのです。
言い方を変えると、経営者は売り上げや利益が後からついて来るような良い経営、良い仕事をしないといけません。売り上げや利益のために仕事をしている姿勢は、利他とは正反対です。先にも申し上げたように、利他の心でお客さまに喜んでいただくこと、働く仲間に喜んでもらう気持ちでずっと仕事を続けると、その先の道はどんどん開けていきます。逆に自分たちがいかにもうけるかということしか考えていないと、道はどんどん狭まっていくのです。
ここで誤解されている方が多くいらっしゃるので、1つお伝えしたいことがあります。利他心は自己犠牲を必要とするわけではありません。私の人生の師匠の藤本幸邦先生も生前によくおっしゃっていたのですが、自己犠牲をすると長続きしない。お客さまに喜んでもらうこと、それから周りの働く仲間に喜んでもらうことを、自分の喜びとできるかどうかということが、とても大事になってきます。もしそういう気持ちを持っていない社員が皆さんの会社に在籍しているとしたら、それははっきり言って採用の誤りです(あるいは経営者自身が自己中で、そういう気持ちが伝わったのかもしれません)。
そういう人を採用している会社は、どんなに高い実力があったとしても将来は伸びません。やはりお客さまに喜んでもらって、自分の喜びにできることに尽きるのです。それを理解しているかどうかがビジネスの成否を大きく分けるポイントだと思います。藤本先生は、「お金を追うな、仕事を追え」ということをよくおっしゃっておられましたけれども、実はそれこそが利他心そのものだったと私は解釈しています。
仕事をするということは、とにかく周りの人を喜ばせるということです。その結果が自然とお金につながるというふうに考えられるかどうか。ビジネスや人生をいいものにするには、利他心(=良い仕事)が先に来るということがとても大事だと思います。
●経営習慣の確認ポイント
お客さまに喜んでもらうことを自分の喜びとできる会社ですか
執筆=小宮 一慶
経営コンサルタント。株式会社小宮コンサルタンツ代表取締役CEO。十数社の非常勤取締役や監査役、顧問のほか名古屋大学客員教授も務める。1957年、大阪府生まれ。京都大学法学部卒業後、東京銀行(現・三菱UFJ銀行)入行。米ダートマス大学タック経営大学院に留学、MBA取得。1991年、岡本アソシエイツ取締役に転じ、国際コンサルティングに従事。1996年に小宮コンサルタンツを設立。
【T】
どんなときでも稼ぐ社長の経営習慣