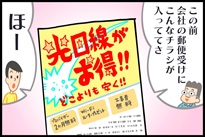
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線

どんなときでも稼ぐ社長の経営習慣として、第1回では「目的」と「目標」の違いを認識すること、そして「良い仕事」をする、つまり仕事を追うことが目的であって、お金はその結果ついて来るものであると心に刻むことを説明しました。そこで、第2回ではその「良い仕事」についてお話を申します。
お客さまや世の中は、皆さんの会社に「良い仕事」をしてくれることを求めています。ですから私は経営のアドバイスをしている会社の経営者たちに対して、「良い仕事をすることに集中したほうがいいですよ」ということをよく申し上げています。
私は「良い仕事」というものに定義を持っていまして、それは3つあります。良い仕事というのは、1番はお客さまが喜ぶこと。2番目に働く周りの仲間が喜ぶこと。そして3番目に工夫。繰り返しますと、お客さまが喜ぶこと、それから働く周りの仲間が喜ぶこと、工夫、この3つに集中するということが大事だと考えています。お客さまが喜ぶことというのは、皆さんなら当然お分かりでしょうし、働く周りの仲間が喜ぶことということもお分かりだと思います。
ある会社で研修をしていたら、そこの社員さんが「働く周りの仲間を喜ばせるというのは、具体的には次にその仕事をする人がやりやすくなるようにすること」と言っていたのですけれども、まさにその通りだと思います。自分の仕事の後に続いて仕事をする人がやりやすくなるように工夫をしてあげれば、その相手はきっと喜びます。チームワークももちろん良くなります。
3つ目の工夫に関してはお客さまが喜ぶこと、周りの仲間が喜ぶことに関して、いろいろ工夫をすることが大事なんですけれども、工夫することで時間の節約ができるようになります。同じことをより短い時間でできる、あるいは質を高めるということは、より多くの方に喜んでいただけるということだと私は思っています。
お客さまから支持されない多くの会社は、売上高や利益に集中しているのではないでしょうか。さらにその会社で働いている人も売上高や利益が目的化すると、しんどくなってきます。
世の中が求めていることや働く仲間が求めていることは、今、申し上げた良い仕事、つまりお客さまが喜ぶこと、働く周りの仲間が喜ぶこと、そして工夫です。良い仕事をすればするほど売上高や利益が上がる。言い方を変えると、良い仕事に集中したほうが結果的に売上高や利益が上がるということを、皆さんに理解していただきたいのです。そして、これが本当に分かれば経営はうまくいきます。
これはきれいごとではなく、実践している会社を私は何社も知っています。例えば神奈川県のある会社は、これまで申し上げてきた3つ、お客さまが喜ぶこと、働く周りの仲間が喜ぶこと、工夫というものをそれぞれの人が月間目標として立てて、月末には上司と一緒に評価して、また翌月に生かすということをずっと繰り返しています。皆さんも良い仕事ということに集中していただければと思います。
「良い仕事」に続いて、「良い会社」についてお話ししたいと思います。良い仕事と同じように、良い会社についても私は3つの定義を持っています。それを申し上げますと、まず、「良い商品やサービスを提供し、お客さまが喜び、社会に貢献する会社」。次に「働く人が幸せである会社」、そして最後に「高収益」であるということです。この3つを成し遂げている会社は良い会社だと私は定義しています。これは先に話した「良い仕事」の結果なのです。
順に詳しくお話ししていきます。まず、良い商品やサービスを提供してお客さまに喜んでいただいて、社会に貢献する会社ですが、これがなければ、そもそも会社の存在意義がないことになります。私の言葉で言えば独自のQPS、すなわちクオリティー・プライス・サービスを提供しているということが、この良い商品やサービスを提供することと、同じ意味になります。
良い商品やサービスを提供して、お客さまに喜んでいただいて、さらに社会に貢献するところまで考えないといけません。お客さまに喜んでいただける商品やサービスを提供している会社があったとして、極端な例ですが、それが危険ドラッグのような反社会的なものであれば社会に貢献できているとはいえないはずです。
2つ目の働く人が幸せはどうでしょう。お客さまに良い商品やサービスを提供して喜んでいただき、かつ社会に貢献していても、そこで働く人が幸せでなければ、やはり良い会社とはいえません。経営学者ピーター・ドラッカーは、現代では、働く人が社会と最も接している窓口である会社が人を幸せにしていないというのは、社会にとっての自己矛盾だと指摘していました。私もその通りだと思います。
ですから、良い商品やサービスを提供してお客さまに喜んでもらい、社会に貢献することと同じく、働く人が幸せということはとても大事になってきます。それを実現するためには、「働くことそのものの喜び」と「経済的な喜び」の両方を社員に感じてもらえるよう、経営者は努力しなければいけません。働くことそのものの喜びは、お客さまや働く仲間に喜んでもらい、工夫することから生まれるのです。
3つ目の高収益については、これまでにお話しした1つ目、2つ目ができているかどうかを評価する明確な指標になると思います。では具体的に数字に落とし込むとどうなるか。私は高収益を皆さんの会社が作り出している付加価値を使って判断しています。
付加価値とは平たく言えば、売り上げから仕入れを引いたものです。小売業や卸業を経営している会社の場合は売上総利益(粗利)ですね。製造業なら売上総利益に、製造に関わる人件費と減価償却費を足し戻したものになります。それが付加価値。この付加価値の2割の営業利益を出す会社を高収益企業だと考えています。
●経営習慣の確認ポイント
お客さまや働く周りの仲間が喜ぶことに、正面から向き合っていますか
お客さま貢献、働く人の幸せ、高収益。この3つを達成できていますか
執筆=小宮 一慶
経営コンサルタント。株式会社小宮コンサルタンツ代表取締役CEO。十数社の非常勤取締役や監査役、顧問のほか名古屋大学客員教授も務める。1957年、大阪府生まれ。京都大学法学部卒業後、東京銀行(現・三菱UFJ銀行)入行。米ダートマス大学タック経営大学院に留学、MBA取得。1991年、岡本アソシエイツ取締役に転じ、国際コンサルティングに従事。1996年に小宮コンサルタンツを設立。
【T】
どんなときでも稼ぐ社長の経営習慣