
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
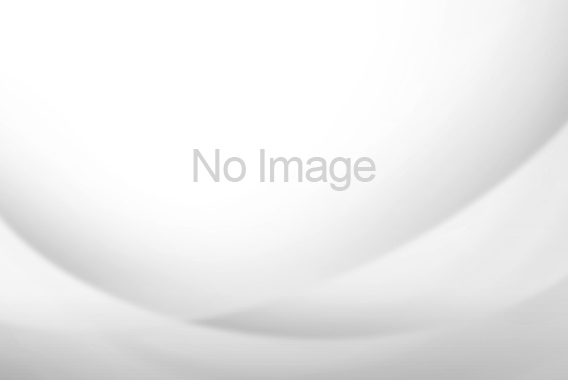
顧問先2200社を抱える会計事務所を率いる公認会計士、古田土満氏が語る小さな企業の経営のコツ。その第20回は、会社の躾(しつけ)をすることの重要性です。なぜ、社員ではなく会社を躾ける必要があるのか、誰が躾けるのか、どのように躾けるのかについて解説します。
「人を躾けるのではなく、企業を躾けよ」
この言葉は『儲かるメーカー改善の急所101項』(柿内幸夫著、日本経営合理化協会出版局)にある言葉です。該当箇所を引用します。
――多くの工場では、5S『整理、整頓、清掃・清潔・躾』を励行している。もちろんこれは良いことだが、ひとつ重要なことは、会社経営における『躾』とは、人に対してではなく、まず企業に対して行なわれなければならないということだ。企業の理念や方針が躾けられていないと、どんなに社員が5Sを実行しても形だけとなる。
まさにその通りだと、私も考えます。経営理念、経営ビジョンがなかったり、社員に浸透していなかったりする状態で5Sの教育、実施をしても、「何のために」が抜けているため心の込もらない5Sとなり、徹底できないので会社の社風になりません。
この状態では、社員は5Sをもうけるための技術としか考えません。そうではなく、全社員が経営理念・ビジョンを実現しようと、使命感を持って一丸体制になることで初めて、会社が躾けられている状態だといえるわけです。一部の社員が実践している程度では「お宅の会社には良い社員がいますね」程度で、会社の評価にはなりません。
では、なぜ社員ではなく、会社を躾けなくてはならないのか。それは経営理念、方針の浸透は当然のこととして、経営者の戦略、戦術を全社員が余すところなく実行するためです。
戦略とは、時代の流れに合わせて自分の会社の商品・サービスを変えていくことです。経営者の立てた戦略、戦術を社員が実行しなかったら、成果は出ません。経営者は常に「今の商品・サービス・販売方法はいつかお客さまに飽きられるから、新しい商品・サービス・販売方法に変えていかなければならない」と強い危機感を持っています。
しかし、社員は違います。多くの社員は職人です。職人とは、自分の技術を磨くことに熱心な人、変化を好まない人と定義します。
ですから、職人は社長やお客さまに指示されたり、命令されたりするのが嫌いな人たちです。こういう職人を躾けるのは、社長ではありません。社長1人では不可能です。管理職(マネジャー)たちです。
管理職とは、会社の理念・使命感や社長の戦略、戦術を社員に浸透させ、実施させる人です。管理職が躾けられている会社は業績が良く、躾けられていない会社は業績が悪いのはいうまでもありません。
会社を躾ける道具として、社員に規則を守らせる技術の道具として経営計画書があります。社員は社長が何度も口を酸っぱくして言って聞かせても、ほとんど覚えておりません。すぐに忘れます。社長もすぐに忘れます。それが人間です。
だから、言葉ではなく文章で伝えるのです。文章ならばお互いに確認しながら、伝え、注意し、指導できます。繰り返し読むことによって、文章の意味を理解するようになります。
社員ではなく、会社を躾けることとは、経営計画書に経営理念・使命感・基本方針・環境整備などの個別方針を書き、経営者、管理職が繰り返し、繰り返し解説し、読み合わせをして、全社員が同じ価値観で同じように行動することによって、お客さまに信頼してもらうことではないでしょうか。そのためには、全社員が同じように行動できるように、方針書は具体的にチェックできるように書くことがコツです。
例えば、古田土経営の方針書には、以下の項目が書いてあります。
「雨の日のお客様の傘はタオルできれいにふいて、たたんでお返しする。(受付)」
「ドアは走っていって手動で開けてさしあげる。小走りドア」
挨拶の仕方も定義してあり、その通りやっているか毎日チェックしています。私ども古田土会計は、挨拶、掃除、朝礼を3つの文化として大事にしています。会社を躾けることにより、それは会社の文化となるのです。
※本記事は、2017年に書籍として発刊されたものです
執筆=古田土 満
法政大学を卒業後、公認会計士試験に合格。監査法人にて会計監査を経験して、1983年に古田土公認会計士・税理士事務所を設立。財務分析、市場分析、資金繰りに至るまで、徹底した分析ツールによって企業の体質改善を実現。中小企業経営者の信頼を得る。
【T】
人気会計士が語る、小さな会社の経営“これだけ”