
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
顧問先2200社を抱える会計事務所を率いる公認会計士、古田土満氏が語る小さな企業の経営のコツ。第15回は、弁護士・税理士・コンサルタントといった外部の専門家との付き合い方です。それぞれの立場を考えて、アドバイスを聞き、活用することを、古田土氏は解説しています。
前回は、金融機関などから持ち込まれるうまい話に関する注意点を解説しました。今回は、弁護士・税理士・コンサルタントなどの専門家のアドバイスを聞く際の注意点について説明します。
数年前に、うちの社員を弁護士さんが講演する相続税のセミナーに参加させたことがあります。感想を聞いたら、「所長、相続は相続人全員が納得するまで話し合い、『争続』にならないようにまとめるのがプロの仕事だと弁護士の先生はお話しされていました。全くその通りですね」と言っていました。
私はその話を聞いて、その社員に言いました。「○○さん、弁護士は争いが長くなるほど報酬が増えます。税理士は早く相続税の申告書を作らないと報酬が入りません。その人がどういう立場なのか理解して話を聞かないと、本質を見誤りますよ」と。
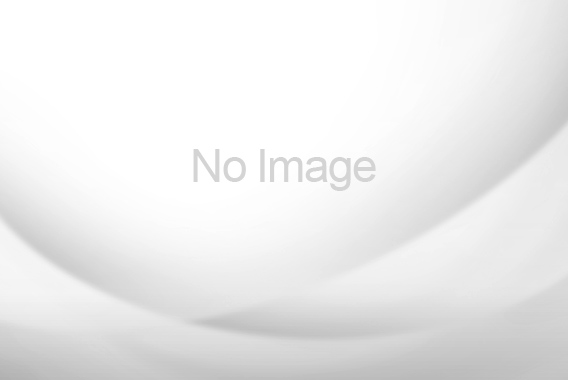 会社を倒産させるか、継続するかの判断で、弁護士さんに相談に行くと「倒産させましょう」という意見が多く、税理士さんに相談に行くと「どうにか存続させる方法を模索しましょう」と言うそうです。
会社を倒産させるか、継続するかの判断で、弁護士さんに相談に行くと「倒産させましょう」という意見が多く、税理士さんに相談に行くと「どうにか存続させる方法を模索しましょう」と言うそうです。
弁護士は、破産や民事再生でお金を稼ぐものです。一方、税理士は会社が倒産するとお客さまが1件なくなるわけです。立場が違うと意見が違うのは、当然です。では、私ども古田土会計はどういう立場かというと、税理士ですから存続の立場です。会社の存続に熱心な弁護士さん、コンサルタントと組んで仕事をします。
古田土会計には、倒産するほか道はないと思い込んでいる経営者の方も相談に来られますが、多くのケースはお金が回っていないだけで、努力すれば存続できるのです。貸借対照表の見直し、資金繰りの改善によって存続可能な会社に変わります。
コンサルタントの方々との接点が多いのは、金融分野です。特に銀行出身のコンサルタントは我々会計事務所では知り得ない銀行の内部事情を熟知しているので、心強い味方です。一般に経営者は銀行交渉の経験が少なく、強気に出るとお金を貸してもらえなくなるのでは、という不安を持っています。そこで、銀行さんの言われるままに、借金をしながら定期積立や定期預金をしたり、為替予約やデリバティブ取引の契約をしたりして大きな損失を出しているケースもあります。
古田土会計では、お客さまと一緒に銀行交渉やリ・スケジュールのための経営計画のお手伝いをしています。しかし、中には私たちではどうしても手に負えない事例もあります。そのときには、金融コンサルタントの先生にお願いして解決し、感謝されたケースも数多くあります。
ただし、世の中には銀行さんからお金を借りるのを専門にして、そこから手数料を取っているコンサルタントもいます。将来も事業が改善する見込みがなく、潰した方がよいと私たちが思っていても、できもしない事業計画をコンサルタントがつくってお金を調達するケースもあります。将来、多くの人に迷惑がかかる可能性があるにもかかわらず、目の前のお金のためにやっているのです。
会計事務所にとって一番やっかいなコンサルタントは、事業承継・相続コンサルタントです。彼らは講演会や著書で「事業承継や相続のことが分かっている弁護士や税理士は日本にごく少数しかいない」「我々は何百件もの事例で成功している」と言います。これは税理士業界について大きな認識不足です。多くの税理士はネットワークでつながり、相続のプロ中のプロが中心となって勉強会と情報の共有をしています。
また税理士業務は無償独占なので、資格がない人が有償だろうと無償だろうと業務にするのは税理士法違反になります。税理士会もニセ税理士の調査、摘発を行っています。コンサルタントの方々が会計事務所と協力してやりましょうとお客さまに言ってくれれば協力しますが、自分たちだけでやりたがるコンサルタントは要注意です。税務調査に立ち会い交渉できるのは、我々税理士だけです。
なお、この文章を書いている私は税理士ですから、読んでくださっている皆さま、この点をお含みおきください。
※本記事は、2017年に書籍として発刊されたものです
執筆=古田土 満
法政大学を卒業後、公認会計士試験に合格。監査法人にて会計監査を経験して、1983年に古田土公認会計士・税理士事務所を設立。財務分析、市場分析、資金繰りに至るまで、徹底した分析ツールによって企業の体質改善を実現。中小企業経営者の信頼を得る。
【T】
人気会計士が語る、小さな会社の経営“これだけ”