
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
一方、新聞で誤字脱字を見かけることは、かなり少ないでしょう。
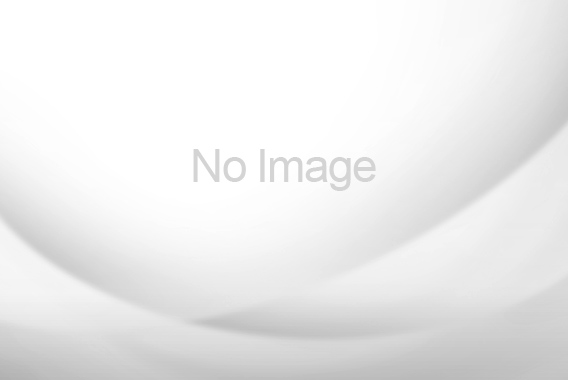
これは、早版から最終版まで通して掲載される記事の場合、版が変わるたびに事実関係や誤字脱字のチェックを受け、修正されていくからです。
原稿を書いた記者は、新しい版が刷り上がるたびに、文面を変えていなくても1行1行、赤鉛筆で文章をなぞりながら、誤字脱字や、変えた方がいい表現がないかをチェックします。
出てくる人名は、取材時にもらった名刺や、データベースに出てくる過去記事と照らし合わせて毎回見直します。
もちろん、担当デスクも同じように、誤字脱字はもちろん、記述に根拠があやふやな点がないか、事実関係は正しいかなどをチェックし、疑問が生じたときは自分で確かめたり、記者に問いただしたりします。同時に、校閲記者も誤字脱字や事実関係の間違いを探します。
ここからお分かりのように、早版と最終版ではチェックの回数が全く異なります。自分の経験から言っても最終版までの過程で誤字脱字と事実の間違いはかなり減ります。要するに「情報の質」ということで言えば、遅い版になるほど高いわけです。
もし、購読している新聞で、一週間に何度も誤字脱字を目にしているとすれば、新聞の一面に書かれている「版」を確認してみてください。おそらく朝刊であれば、最終版である14版(産経新聞は15版)ではなく、11〜12版なのではないでしょうか。こうした早版は、最終版に比べてチェックが甘いのです。
もっとも、「最終版の一面」に限ると、早版とは違う理由で誤字脱字が生じやすい事情があります。特ダネが入ってくることがあるからです。
特ダネは基本的に最終版にだけ入れます。前々から原稿が出来上がっているケースがないわけではありませんが、大半は夜、遅い時間にウラが取れて掲載が決まります。
その場合、原稿を書く時間は短く、編集や修正の時間もあまりありません。ゲラも1回しか出ないので、チェックも一発勝負です。ですから、特ダネが入っている最終版の一面には、結構な確率で誤字脱字があるのです。
こうした観点からすれば、ある新聞で誤字脱字が目に見えて増えてきたら、経営状態が悪化している可能性を疑ったほうがいいかもしれません。特ダネを生むことのない校閲部門は、業績が悪くなると人員削減の対象にされやすいからです。
例えば、行き過ぎた「合理化」の結果、チェックする人の数が減ってミスを見つけにくくなっているのかもしれません。本来なら版を作り直してでも修正すべき間違いに気付いていながら、コストをケチってそのまま載せている可能性もあります。
こうなると、報道自体の信頼性にも疑いが湧いてきます。
人員削減が記者やデスクにまで及び、個々人に割り振られた仕事量が限界を超えると、ミスが目立って増えるものです。誤字脱字の増加は、記者たちが以前より時間に追われていることを示しているのかもしれません。
こうした新聞社では、十分にウラを取らずに書いた記事が出てくる可能性が高いといえます。ニュースの分析も、たくさんの専門家に取材した上で書いたものではなく、記者の印象論だけを書いているのかもしれません。
「記事の質」の違いや変化は、毎日のように複数紙の記事を読み比べ、実際に自分で検証している記者には見えていますが、一般の読者はそこまで時間をかけることはできないでしょう。しかし、誰でも検証が可能な誤字脱字を目安にすると、記事や媒体の「情報の質」を類推することができるのです。
執筆=松林 薫
1973年、広島市生まれ。ジャーナリスト。京都大学経済学部、同大学院経済学研究科修了。1999年、日本経済新聞社入社。東京と大阪の経済部で、金融・証券、年金、少子化問題、エネルギー、財界などを担当。経済解説部で「経済教室」や「やさしい経済学」の編集も手がける。2014年に退社。11月に株式会社報道イノベーション研究所を設立。著書に『新聞の正しい読み方』(NTT出版)『迷わず書ける記者式文章術』(慶応義塾大学出版会)。
【T】
情報のプロはこう読む!新聞の正しい読み方