
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
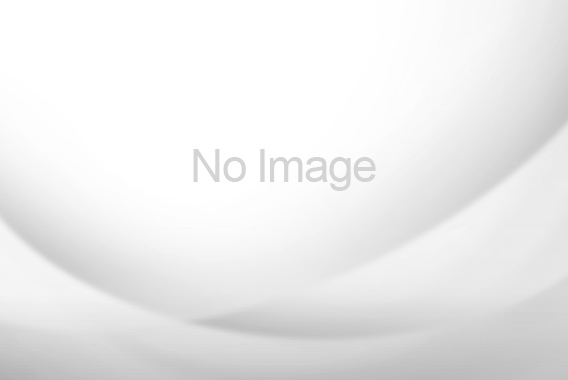 コピー、プリント、スキャニング、ファクシミリといった機能を1台に統合した複合機は、業務に欠かせない存在だ。それぞれの機器を個別に導入するのに比べ、設置場所の省スペース化が図れる。ネットワークへの接続もシンプルになる。多彩な機種が各社から販売され中小企業でも導入が進んでいる。
コピー、プリント、スキャニング、ファクシミリといった機能を1台に統合した複合機は、業務に欠かせない存在だ。それぞれの機器を個別に導入するのに比べ、設置場所の省スペース化が図れる。ネットワークへの接続もシンプルになる。多彩な機種が各社から販売され中小企業でも導入が進んでいる。
複合機はどのメーカーもほとんど機能は大差ないと考えがちだ。しかし、実際は各社が機能の拡充を進めている。いったん導入すれば、リース期間の5年程度は使い続けることになる。多くの社員が毎日の業務で使用するだけに、機能や操作性はもちろん、消費電力など環境面にも留意して選択したい。
近年、各メーカーが力を入れているのが起動のスピードアップだ。一般的に複合機やコピー機には一定時間、機器を使用しないと自動的に消費電力を下げる節電モード(スリープモード)の機能が搭載される。一方、スリープモードのときに操作を開始しようとすると、ウオームアップのために待たなければならない。
「急いで提案書をコピーしてお客さんのところに持っていかなければならないのに、何で遅いんだ」。こんな経験をした人も多いのではないだろうか。こうしたウオームアップの待ち時間を短縮するため、複合機に人感センサーを搭載。センサーが人を検知してスリープモードを解除し、複合機の前に立って操作するときには使用状態になる。待ち時間のイライラを解消できる機種もある。
ただ、複合機の設置場所によっては人感センサーの機能が「あだ」になる。複合機を利用しない人が近くを通過するたびにセンサーが働くからだ。スリーブモードを解除してしまえば、節電になりにくい。それを避けるため、富士ゼロックスでは、複合機の前に立った人の姿と顔をカメラで検知する画像認識技術を活用。「ApeosPort-VI」や「DocuCentre-VI」シリーズなどでオプションとして搭載できるようにしている。
もう1つのトレンドが操作性のアップだ。複合機に限らないが、最新のOA機器は多機能になる一方、操作が複雑で十分に機能を使い切れないケースが少なくない。多機能な複合機は操作方法が分かりにくいのだ。
そこで、操作しやすいように、大型液晶カラーディスプレーを搭載する動きが進んでいる。例えばリコーの複合機「RICOH MP C6004/C5504/C4504/C3504/C3004」は10.1インチの大型カラータッチパネル「MultiLink-Panel」を搭載。スマートフォンやタブレットのように指でディスプレーをタッチしたままページを送ったり、文字を拡大して原稿の内容をプレビューしたりする操作が可能だ。
また最近は、電子メールに書類データを添付したり、文書を電子化して保管したりする需要が増えた。そのため、複合機の機能の中でもスキャニングの重要性が増している。オプションの装置を利用して、両面同時スキャンを可能にしたり、名刺読み取りができるようにしたりした機種も出てきている。原稿の裏表を同時にスキャンできれば、読み取り時間が少なく、業務効率は上がる。顧客・取引先と交換する名刺の情報を電子化して社内で共有し、ビジネスに活用するために専用端末を用意する必要もなくなる。
数々発売されている複合機の中でもかなりユニークなのが、「消色」機能を搭載したタイプだ。これまでOA用紙を節約する方法といえば、両面印刷や裏紙印刷、1枚の用紙に複数原稿を印刷するなどだったが、これらとは別次元の節約が可能だ。1度印刷した内容を消してその用紙を再利用できるので、紙の使用枚数が劇的に減り、企業の課題であるCO2削減に貢献する。紙の購入・廃棄・保管に関わるコストも削減できる。
消色機能を備えた複合機の開発元が自社のオフィスを対象に調査した結果では、印刷した用紙の約9割が保管されず、1週間以内に廃棄されていたという。こうしたプリントは果たして必要なのか。その無駄を減らすために開発された。
文具メーカーのパイロットコーポレーションの大ヒット商品に、こすって熱を発生させることで消せる「フリクションインキ」を使ったボールペンがある。その技術を活用して、「消せるトナー」が開発された。
消せるトナーの色は、少し黒味が強いブルー。消さない印刷物で使用する黒のトナーと区別がつきやすいようにしている。消せるトナーを使う複合機は、従来の複合機に比べて低温で定着、印刷するように開発した。複合機で1度使ったOA用紙を繰り返し使うためには、紙の状態が良くなくてはならない。高温で定着させると紙が反ってしまうことがあるので、温度を下げたのだ。これにより、再利用時の紙詰まりが防げる。
消せるトナーでプリントすれば、フリクションインキを使ったボールペンと同様に熱を加えれば完全ではないものの、実用上問題ないレベルにまで消せる。1枚の用紙に対する再利用の目安は5回程度で、単純計算で紙の使用量を1/5に減らせるわけだ。
こうした消色機能を備えた複合機の例として、NTT西日本が取り扱っている「OFISTAR T3500 hybrid」をみてみよう。同機種は、プリントアウトを残す印刷物は従来通りにモノクロトナー、消してOA用紙を再利用する印刷物はブルートナーといった具合に選択できるハイブリッド複合機だ。
例えば、FAXを受信した場合にはブルートナーを利用してプリントアウトするにように設定しておく。そうすれば、業務に関係ないFAXが送られてきて出力してしまった場合、紙を無駄にせずに済む。FAXとして送られてきたデータは電子保管可能なので、確認後に消して再利用できる。
パソコンから出力したピッキングリストや、一時的に使用する会議資料などもブルートナーで印刷する。リストのチェックや資料の書き込みに、パイロットのフリクションインクを使ったボールペンを使用すれば、書き込んだ文字なども一緒に消色できる。再利用に支障は生じない。このように業務の種類によって、ブルートナーの使い方を考えれば、紙の使用量を見直せる。
消色は複合機本体でも可能だが、オプションである専用の消色装置を使えばよりスピードを上げられる。消色装置は、両面同時に消色でき、用紙の劣化や書き込みなどを判断し、再利用可能かどうかを自動的に分別する機能も備える。
最近の複合機は、カラー印刷が可能な機種が主流になっている。ビジネスのプレゼンテーション資料などを作成する際には、カラー印刷のメリットが大きい。カラー印刷ができる機種を1度導入してしまえば、できない機種に戻るのは難しいかもしれない。
しかし、実際にはカラー印刷ではないモノクロのプリントアウトを毎日大量に行い、しかも、その用紙は保管されずに分別して廃棄されるだけという実態は少なくないはずだ。そうした業務には消色機能を持った複合機を用意すれば、紙の使用量の削減効果が期待できるはずだ。社内すべての複合機をリプレースする必要はない。そうした業務専用にまずは1台導入してみてはどうだろうか。
※掲載している情報は、記事執筆時点のものです
執筆=山崎 俊明
【M】
ビジネスコミュニケーション手法の改善