
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
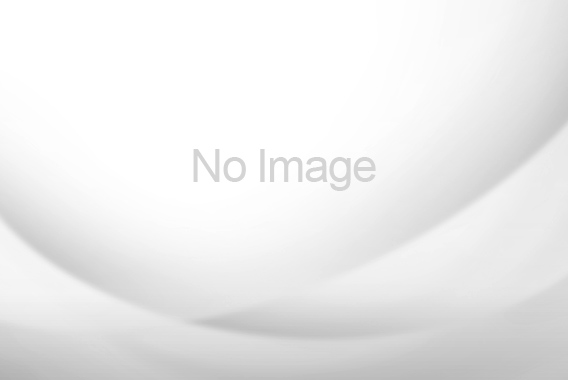 今年は梅雨明けが例年よりも早く、早くも本格的な夏を体験していることでしょう。この時期に悩まされるのが蚊。最近は電子式の蚊取り器具がかなりメジャーになっていますが、渦巻き型をした蚊取り線香の独特の匂いを覚えている方も多いのではないでしょうか。今回は、世界で初めて蚊取り線香を開発したKINCHO(大日本除虫菊)創業者の上山英一郎を紹介します。
今年は梅雨明けが例年よりも早く、早くも本格的な夏を体験していることでしょう。この時期に悩まされるのが蚊。最近は電子式の蚊取り器具がかなりメジャーになっていますが、渦巻き型をした蚊取り線香の独特の匂いを覚えている方も多いのではないでしょうか。今回は、世界で初めて蚊取り線香を開発したKINCHO(大日本除虫菊)創業者の上山英一郎を紹介します。
「金鳥の夏、日本の夏」というキャッチフレーズから、蚊取り線香にはドメスティックな(国内向けっぽい)イメージがあるかもしれません。しかし、英一郎は早くから海外に目を向けており、それが自らのモチベーションとなっていた人物でした。積極的に輸出に取り組み、彼が開発した蚊取り線香は、現在、世界の人々の生活に欠かせないものになっています。
英一郎は1862年、和歌山県有田のみかん農家に生まれました。西洋に関心を抱いていた彼は1882年ごろに上京し、欧文正鵠(おうぶんせいこく)学館に入学。欧文正鵠学館は、クラーク博士で有名な札幌農学校でも教壇に立っていたジェームズ・サマーズが設立した英語塾です。
サマーズ一家から英語を学んだ英一郎は、かねて憧れていた福沢諭吉の慶應義塾に入学。日本は西洋に学び、世界に伍(ご)していかなければならないという諭吉の思想は、英一郎の深く共感するところでした。そして1885年、和歌山に帰郷すると実家のみかんを輸出する貿易会社「上山商店」を設立。事業家としての第一歩を踏み出します。
同じ頃、米サンフランシスコで種苗商を営むH.E.アモアという人物が、諭吉を訪ねてきました。アモアが日本のみかんの苗を求めていることを知った諭吉は、英一郎のことを思い出し、アモアに紹介することにします。師から連絡を受けた英一郎はアモアを迎えに東京まで出向き、和歌山の実家へ招待。アモアにみかんの苗を提供しました。
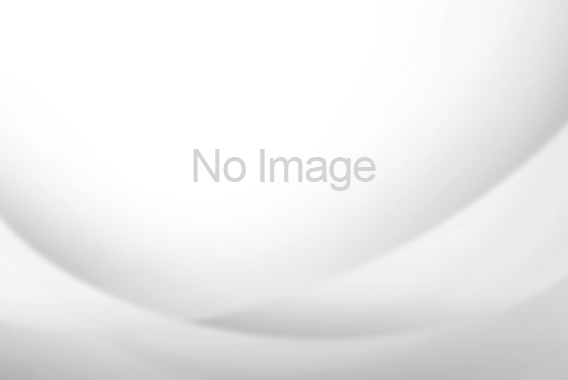 このときのもてなしが忘れられなかったアモアは翌1886年、お返しとして珍しい植物の種をいくつか英一郎に送ります。その中にあったのが、除虫菊の種でした。種と一緒に送られたアモアの手紙には、アメリカでは除虫菊の栽培で巨万の富を得た者がいると書かれています。
このときのもてなしが忘れられなかったアモアは翌1886年、お返しとして珍しい植物の種をいくつか英一郎に送ります。その中にあったのが、除虫菊の種でした。種と一緒に送られたアモアの手紙には、アメリカでは除虫菊の栽培で巨万の富を得た者がいると書かれています。
「荒れた土地でも栽培できる除虫菊なら、貧しい農家を救うことができるし、輸出すれば日本も豊かになる」。そう考えた英一郎は除虫菊普及のために各地を奔走するようになりました。
ところが、除虫菊の効能を説いても農家の反応は芳しくありません。最初は種を無償で提供すると言っても「そんなえたいの知れないものはペテンに決まっている」と栽培してもらえなかったのです。そのような状況でも、除虫菊は必ず農家を救う、そして除虫菊を日本の輸出品として育てるという英一郎の思いは変わりません。自ら栽培の手引書を制作し、農家を訪ねていきます。栽培の指導まできめ細かに行ううちに、少しずつ除虫菊を栽培する農家が出てきました。
そして1904年に開戦した日露戦争で、戦地でのシラミ対策として陸軍が大量の除虫菊粉を購入。除虫菊が注目を集めるようになります。以降、英一郎の尽力が花開き、1930年ごろには除虫菊の生産量で日本は世界一の座に就き、除虫菊は重要輸出品へと成長します。「除虫菊を日本の輸出品として育てる」という英一郎の思いは、現実のものとなりました。
こうした除虫菊栽培の普及の中で生まれたのが、蚊取り線香でした。当時、除虫菊の粉はノミ・シラミ取り用に主に使われていました。しかし、日本でノミやシラミ以上に悩まされてきたのが蚊です。ノミ・シラミに使える除虫菊の粉を、蚊を退治するのにも使えないか。これが英一郎の発想の原点だったのです。
日本では古来、杉や蓬(よもぎ)の葉をたいて煙を出す「蚊遣(かや)り火」が蚊の退治に使われていました。そこで、ノミやシラミを駆除できる除虫菊の粉を使えば、もっと効果的に蚊を退治できるのではないかと考えたのです。
早速、鉢や香炉などの火種の周りに除虫菊の粉をくべてみます。しかし、煙た過ぎてとても実用的ではありませんでした。また、暑い夏に火鉢を使うというのも無理がありました。どうすれば除虫菊を蚊の退治に使えるか、頭を悩ませながら除虫菊を広めるための旅をしていると、泊まった宿に線香屋が同宿していました。そうだ、線香にすればいいのではないか……。英一郎は仏壇線香の職人を雇い入れ、1890年、除虫菊の粉を線香状にした製品を開発しました。世界初の蚊取り線香の誕生です。
しかし、仏壇線香と同じような形をした当時の蚊取り線香は40分程度しか持ちません。しかも細くて煙が少ないので、同時に2、3本たく必要があります。長持ちさせようと線香を長くすると、折れてしまいました。
行き詰まったとき、英一郎の妻・ゆきが「渦巻き型にしたらいかがですか」と提案したといいます。そこから長持ちして折れにくく、大量生産できる線香の製法を7年かけて研究し、1902年、私たちにもなじみの深い渦巻き型の蚊取り線香が誕生しました。
1905年、英一郎は大日本除虫菊貿易合資会社を設立し、製品の輸出を本格的に始めます。さらに1906年には露ウラジオストックに上山商店の支店を開設。1909年には日本貿易輸出合資会社を設立し、1922年には米ニューヨークにも支店を設け、世界と渡り合って商売して日本を豊かにするという思いを現実のものにしていきます。そして、英一郎は1930年に長男に社長の座を譲り、会社の盛業を見届けて1943年にこの世を去りました。
英一郎の開発した渦巻き型の蚊取り線香は、その形状から海外では「Mosquito coil」と呼ばれ、世界中で愛用されています。電化が進んでいない地域でも簡単に使えることから、特に東南アジアやアフリカで大活躍しています。
国内市場が縮小している現在、海外市場に活路を見いだしている企業は少なくないでしょう。日本の輸出品国内需要を掘り起こす努力はもちろん重要ですが、海外市場を視野に入れないわけにはいかないのが現代の日本の状況です。そんな中、決して豊かとはいえなかった明治時代にいち早く英語を学び、輸出品を育てることで日本を豊かにしようとした事業家がいたことは、私たちを励ましてくれているように思われます。
最近は、日本の輸出品といえば、自動車や情報機器などハイテク製品ばかりが思い浮かびます。しかし、その先達として世界を制覇し、今も人々の健康を守り続けている蚊取り線香。この夏、蚊取り線香の香りを嗅ぎながら、高い志を持った先人の足跡に思いをはせてみるのも悪くないかもしれません。
【T】
偉大な先人に学ぶ日本ビジネス道