
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
金は中国、プラチナは南アフリカ、ダイヤモンドはロシアなど、宝飾品の素材である貴金属・宝石類の生産量が多いのは、基本的に鉱物資源に恵まれた資源国です。
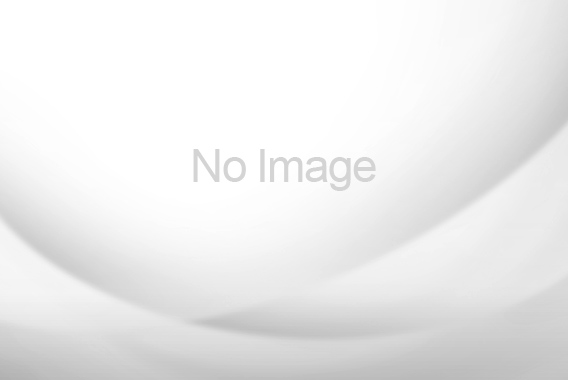 しかし、宝飾品の素材の中で、日本が世界一の生産量を誇るものがあります。真珠です。今回は真珠王と呼ばれ、日本が真珠大国となる礎を作ったミキモトの創業者・御木本幸吉を紹介します。
しかし、宝飾品の素材の中で、日本が世界一の生産量を誇るものがあります。真珠です。今回は真珠王と呼ばれ、日本が真珠大国となる礎を作ったミキモトの創業者・御木本幸吉を紹介します。
幸吉は1858年、志摩国鳥羽浦(現・三重県鳥羽市)のうどん屋の長男として生まれました。そして、13歳になると青物の行商を始めます。当時の幸吉に、こんなエピソードがあります。ある日、鳥羽港に英国籍の軍艦が入港しました。乗組員目当てに地元の商人が小舟を出しますが、取り合ってもらえません。そこで、幸吉はひと工夫。小舟の上で得意の足芸を披露したのです。これを面白がった乗組員は幸吉を艦に上げ、品物は売り切れたそうです。幼いながらも幸吉が商才を持っていたことがうかがえます。
20歳で家督を継いだ幸吉は、一家の長として商売を始めるにあたり、東京、横浜へ視察旅行に出かけました。そこで故郷・伊勢志摩の天然真珠が高値で取引されているのを目の当たりにしました。故郷に戻った幸吉は真珠の状況を調べたところ、真珠を宿すアコヤガイが乱獲によって絶滅の危機に瀕していたことが分かりました。早速、幸吉は養殖場を作り、アコヤガイの養殖を始めます。
しかし、アコヤガイを増やしても真珠の生産はほとんど増えません。天然の真珠は、偶然によってできるものだったからです。貝は栄養分を摂るために海水を吸い込みますが、そのとき一緒に砂や小石なども吸い込むことがあります。そのような異物が入ると貝は吐き出しますが、貝殻と体を覆う膜の間などに異物が入って吐き出せない場合は、真珠層となる分泌物を出して異物を包み、自身の内臓が傷つかないようにします。
そうしてできたのが真珠です。そもそも、異物はたいてい吐き出されてしまうので真珠が形成されるのは稀なのです。さらに真珠ができたとしても装飾品として使える質のものはその中でも限られており、アコヤガイ1万個に1個程度でした。
このことから幸吉はアコヤガイを増やすのではなく、貝の中で真珠ができる割合を高めることを考えます。真珠の養殖への挑戦です。当時、真珠の養殖に成功した者は世界で誰もいませんでした。
前述の通り、貝は異物が入ると吐き出そうとします。吐き出さずに真珠を形成させるには、核となる異物としてどのようなものを入れればいいのか。その核は貝のどこに入れればいいのか。どのような環境が真珠を形成するのに適しているのか。幸吉の試行錯誤が続きます。
1893年、幸吉は、世界で初めて半円真珠(半球型の真珠)の養殖に成功。京橋区弥左衛門町(現・銀座4丁目)に御木本真珠店を開き、真珠の販売を始めました。その後12年かけ、1905年には真円真珠(完全な球体の真珠)の養殖に成功。真珠王と呼ばれるようになります。
真珠の養殖は、のちにエジソンから「驚嘆すべき発明」と賞賛されるほど画期的なものでした。しかし、幸吉の足跡を見ていて目を引くのは、世界的な発明に成功したに止まらず、「いかに売るか」を考え、力を尽くしたことです。その象徴となるのが、当時の日本で最も先端的な繁華街だった銀座に、自ら最初の店舗を出したことです。
また、装飾品として真珠を売るには、デザインや技術が優れていなければいけないことを感知していました。そこで、側近をヨーロッパに派遣。ヨーロッパの装飾品の技巧を学ばせ、日本の伝統的な技術と融合させることでオリジナルデザインの開発に力を注ぎます。1907年には日本初の本格的な装身具加工工場である「御木本金細工工場」を開設。生産から販売までの一貫体制を確立し、近代宝飾産業の礎を築きました。
もちろん、最大の市場である欧米へのアピールにも力を入れました。1893年に開かれたシカゴの万国博覧会を皮切りに、世界各国で開催される博覧会に養殖真珠を使った工芸品などを出品。世界に「ミキモト」の名前を浸透させます。
1905年、伊勢神宮に行幸した明治天皇に拝謁した幸吉は「世界中の女性の首を真珠でしめてご覧にいれます」と言ったといいますから、世界市場攻略に自信があったのでしょう。1913年にはロンドン支店を開設。本格的に海外進出に乗り出しました。
天然真珠より安価な幸吉の養殖真珠を脅威に思ったヨーロッパの天然真珠業者は「養殖真珠は模造真珠である」というキャンペーンを打ち、不買運動を展開。パリで裁判沙汰にまで発展しました。
しかし、英国や仏国の研究者が分析した結果、養殖真珠は天然真珠と変わるものではないと結論が出て、日本の養殖真珠は本物の真珠であると認められます。以降ニューヨーク支店、パリ支店と次々に店を開き、世界各国に幸吉の真珠は広まっていきました。現在でも欧米やアジア各国に直営店を持ち、ミス・インターナショナルの優勝者の王冠にミキモトの真珠が使われるなど、ミキモト・パールは世界的なブランドとして確立しています。
かつてない技術や商品の開発はビジネス発展の大きなポイントであることは間違いありません。しかし、幸吉がそれに満足してしまっていれば、ミキモトは現在のような日本を代表するブランドにはなっていなかったでしょう。売り方を考え、さらにデザインという付加価値を加える。そんな幸吉のビジネス哲学には学ぶべき点があると思います。ビジネスはすばらしい技術や商品を開発すればそこがゴールではありません。そこがスタート地点なのです。
【T】
偉大な先人に学ぶ日本ビジネス道