
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
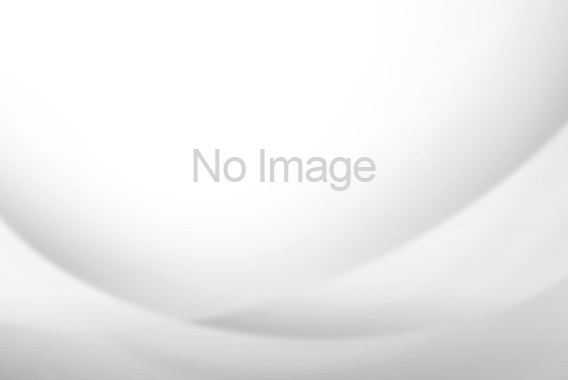 大阪・道頓堀にあるグリコの看板「グリコサイン」を知らない人は、ほとんどいないでしょう。大阪城、通天閣と並ぶ大阪三大スポットの1つという声も聞かれるほどで、看板がよく見える戎橋(えびすばし/通称ひっかけ橋)ではひっきりなしに観光客が写真を撮っています。一企業の看板がこれほどの観光スポットになるというのは、かなりまれなケースではないでしょうか。
大阪・道頓堀にあるグリコの看板「グリコサイン」を知らない人は、ほとんどいないでしょう。大阪城、通天閣と並ぶ大阪三大スポットの1つという声も聞かれるほどで、看板がよく見える戎橋(えびすばし/通称ひっかけ橋)ではひっきりなしに観光客が写真を撮っています。一企業の看板がこれほどの観光スポットになるというのは、かなりまれなケースではないでしょうか。
現在のグリコサインは6代目。歴代それぞれが名物として親しまれてきました。1935年に初めて設置された初代の看板は、高さが33メートルもある巨大なもの。これで一躍、大阪ミナミの名物になりました。
戦後に再建された2代目は特設ステージ付きというユニークなもの。当時は演奏会や漫談などの催しを開いていたそうです。1963年に作られた3代目は中央から12トンの水が噴き出して人々を驚かせました。陸上競技場を背景とした4代目、大坂城や海遊館などが描かれた5代目と続き、2014年には14万個のLED照明を使った6代目が登場しました。
グリコサインは、ユニークなアイデアで人々の耳目を引きつけ続けてきたからこそ、大阪で有数の観光スポットになっているのです。そして、このアイデアで人々を引きつけるというのは、江崎グリコの創業者である江崎利一が得意としたところでした。
利一は1882年に佐賀県で生まれました。幼少の頃から家業の薬種業(薬を調合・販売する店舗/薬種商ともいう)を手伝い、商売を実地で学んでいきます。高等小学校を卒業すると、家業を手伝う傍ら独学で勉強を進めました。
また、近所の寺子屋の師匠・楢村佐代吉を訪ね、教えを請うています。「商売というものは、自分のためにあるとともに、世の中のためにある。商品を売る人はモノを売って利益を得るが、買う人もまたそれだけの値打ちのものを買って得をする。共存共栄がなかったら、本当の意味の商売は成り立たない」。佐代吉から受けたこの教えは、「事業即奉仕」としてその後の利一の事業を支える哲学となります。
利一が19歳の時、父が死去。家業の薬種業を引き継ぎ、本格的に事業を手掛けることになりました。30代に入ると、当時日本で流行し始めていたワインに注目し、たるに入ったワインを仕入れて瓶に詰め替えて販売するビン詰葡萄酒販売業を開始。この事業が大当たりとなり、事業家として成功を収めます。この成功も「ワイン」と「瓶詰め」を結びつけた利一のアイデアによるものですが、その本領が発揮されるのはこの後のことになります。
ある日、利一が行商していると、筑後川下流の土手で漁師たちが大釜でカキを煮ているのを見かけました。「エネルギー代謝に重要なグリコーゲンが日本の貝類、特にカキに多く含まれている」という新聞記事を思い出した利一は、漁師に煮汁を分けてもらい、九州帝国大学付属医院に分析を依頼します。すると、グリコーゲンの他にもカルシウムや銅分が含まれていることが分かったのです。
翌年、彼の長男が腸チフスにかかってしまいます。医者もさじを投げるほどの重症でしたが、医者と相談のうえカキのエキスを与えたところ、効果があり、なんと無事に回復します。「息子を救ってくれたグリコーゲンを広く世に役立てたい。グリコーゲンを一番必要とするのは子どもだ」。
ここから、利一の発想力に拍車がかかりました。グリコーゲンを子どもに摂取させるにはどうしたらいいか。利一は、子どもが好きなキャラメルに入れることを思いつきます。さらに商品を手に取ってもらうには目を引くトレードマークが必要です。どんなトレードマークがいいだろう……。頭をひねっていたとき、自宅近くの神社で駆けっこをする子どもが両手を挙げてゴールする姿を目にします。「まさに健康の象徴。これだ」。有名なグリコのマークが生まれた瞬間です。
キャッチフレーズにも工夫を凝らします。最初「一粒100メートル」というフレーズを思いつきますが、「100メートルでは短すぎる。300メートルがちょうどよい」と考え直し、グリコ一粒を人が300メートル走るのに必要なカロリーに調整。あの有名なフレーズが誕生します。
そして、グリコといえばおまけのおもちゃ。これも「食べることと遊ぶことが、子どもの二大天職である。これを一箱で満足できれば、子どもにとって大きな魅力になるはずだ」と考えたことから生まれたアイデアで、最初はカードを封入しました。
1922年2月11日。大阪三越百貨店で、利一のアイデアが盛り込まれたグリコが販売開始。1927年には、カードの代わりに豆玩具の封入を始め、「おまけ付きグリコ」は大ヒット商品になります。
利一のアイデアは、販売方法やPRにも及びました。その1つが、映画付き自動販売機。これは、10銭入れると販売機の画面にチャンバラ映画の抜粋が流れ、映画が終わるグリコとおつりが出てくるというもの。子どもたちが喜び、行列ができるほどの人気を呼んだといいます。また、道頓堀に巨大なサイン塔を設置。これが、今日のグリコサインに至っているのは、最初に述べた通りです。
利一はその後も、酵母をクリームに練り込んだ「ビスコ」、板チョコが主流だった時代にチョコレートにアーモンドを入れた「アーモンドチョコレート」、世界で初めての棒状チョコレート菓子「ポッキー」などアイデアあふれる商品を数多く生み出し、江崎グリコを、日本を代表する製菓会社の1つに育てます。そして、1973年に91歳で社長を退任、1980年に生涯を閉じました。
利一の成功の源に、アイデアを生み出す力があったのは間違いないでしょう。利一は、「オモチャ屋と冷やかされ、グリコはおまけで売れたという人もある。しかし、本当はグリコのおまけを生み出すほどの創意工夫こそ、グリコ発展の原動力であった」と言っています。
そんな利一がビジネスについて言った言葉に「商売は2×2=5(ににんがご)」があります。大切なのは、考えて工夫してみること、考える努力をすること。2×2=4では当たり前で、さらに人一倍の努力と工夫をすれば、2×2=5にも6にもなる、という利一の仕事に対する姿勢を表しています。
身体にいいグリコーゲンを子どもに取ってもらうために、キャラメルの中に入れる。そして目を引くトレードマークとキャッチフレーズを考え、箱の色で差別化し、おもちゃを付け、PRにもアイデアを盛り込む――。
製菓業界の一大ヒット商品は、製品開発からPRに至るまで、数々の創意工夫により生まれたものでした。ヒット商品を生み出すために、すべてわたって考えて工夫することの大切さ、そしてその効果を、利一のエピソードは改めて教えてくれているように思います。
【T】
偉大な先人に学ぶ日本ビジネス道