
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
ゆとり世代の叱り方・教え方を具体的なケースで学ぶ連載の第5回。報告・連絡・相談がきちんとできない、営業の電話を嫌がる場合の対処法です。
Q 報告・連絡・相談がきちんとできません。こちらから聞けばきちんと答えるのに、なぜ自分から報告に来ないのでしょうか?
A 基本的に「待ち」の姿勢でいることが多いです。余計なことをして叱られるのが嫌だから、聞かれるまで待っているのです。
【対処法のポイント】
ゆとり世代は基本的に「待ち」の姿勢でいます。それは周囲が勉強する環境を整えてくれたことから来る環境依存型人間であり、「自分から何かをするより、自分が何かをしてもらう」ことに慣れているからです。
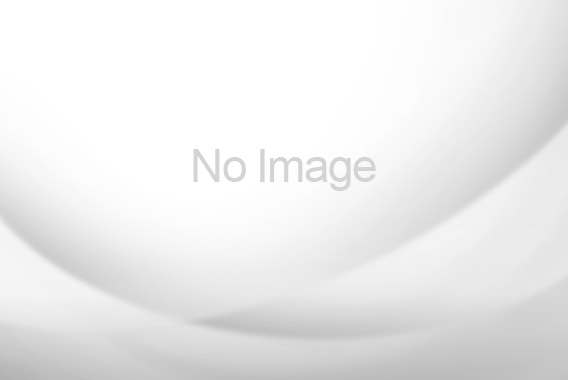 もう1つ、社会に出てからの経験で、「待ち」の姿勢がことさら強くなるケースがあります。例えば、新入社員が何かを報告・連絡するために上司にコンタクトしたとき、それが上司の望むタイミングでなければ、叱られることがあります。すると、その叱られたことに大きなショックを受け「次は聞かれるまで待っていよう」と受け身になってしまいます。上司が何かを聞いてくるときは、間違いなく上司が望んでいるタイミングであり、自分が叱られることはないからです。
もう1つ、社会に出てからの経験で、「待ち」の姿勢がことさら強くなるケースがあります。例えば、新入社員が何かを報告・連絡するために上司にコンタクトしたとき、それが上司の望むタイミングでなければ、叱られることがあります。すると、その叱られたことに大きなショックを受け「次は聞かれるまで待っていよう」と受け身になってしまいます。上司が何かを聞いてくるときは、間違いなく上司が望んでいるタイミングであり、自分が叱られることはないからです。
受け身になるのを防ぐには「叱ったり、注意したりするときもあるが、それは報告・連絡のタイミングを自分で判断できるようになるためのトレーニングなんだ」という説明をして、部下が能動的に動くように促すことです。
相手の立場を考え、相手の喜ぶことを、ちょうどよいタイミングでするのが仕事の上では大切です。取引先との交渉や商談などで使う、社会人に欠かせないテクニックです。報告・連絡・相談はそのトレーニングの一環です。上司に対してだけではなく、先輩社員などに対してもどんどんコンタクトさせて、人によってやり方が異なることを学ばせるとさらによいでしょう。
能動的に動くことがトレーニングになる。
Q 新人に営業の電話をかけさせたところ、理由を付けてはサボっています。「そんなに何度も何度も電話されたら、自分なら嫌だけどなぁ」と同期社員に漏らしていると聞きました。
A 自分の価値観で物事を判断しています。「新人はお客様に育てられるもの」という意識を持たせましょう。
【対処法のポイント】
ゆとり世代は何ごとも「自分の視点」で考える傾向があります。他人ならどう考えるか、という発想に乏しいのです。社会人になるまでの期間、良いか悪いかを自分の視点だけで考え「昨日の自分から今日の自分へ」と、自分のことだけを考えながら学んできたからです。
この場合は「僕はそんな商品なんか欲しくない」という自分の考えから、電話をかけるモチベーションがまったく上がらない状態になっています。しかし現実には「そういう商品があるなら欲しい」というお客様は、確率はともかくとして確かに存在しているのです。「そんなに言うなら、試してみようかな」というくらいの気持ちのお客様が、購買につながります。商品に対して、さまざまな気持ちを持ったお客様がいるという、市場を客観視することから、まず教えましょう。
また彼らの「何度も電話をしたら迷惑じゃないか」という考えに対して、教えてほしいことが1つあります。それは「何度も電話をすることより、新人が電話をすることのほうが本当は迷惑だ」という点です。
お店での接客もそうですが、ベテランに話をしてもらったほうがお客様にとっては楽です。「(未熟な)新人の接客は迷惑」なのです。にもかかわらず、なぜ新人に営業電話をさせるのか。それは新人の営業テクニックをお客様との会話で鍛えてもらうためです。お客様には「新人だから、聞いてあげよう」という方もいます。営業電話は自分自身のトレーニングのためにしている、という意識を持たせ、前向きに取り組むようにさせてください。
「新人の営業電話はトレーニングのため」と考えさせる。
執筆=柘植 智幸(じんざい社)
1977年大阪生まれ。専門学校卒業後、自分の就職活動の失敗などから、大学での就職支援、企業での人財育成事業に取り組む。就職ガイダンス、企業研修、コンサルテーションを実施。組織活性化のコンサルティングや社員教育において、新しい視点・発想を取り入れ、人を様々な人財に変化させる手法を開発し、教育のニューリーダーとして注目を集めている。さらに、シンクタンクなどでの講演実績も多数あり、毎日新聞、読売新聞、産経新聞、経済界、日経ベンチャーなど多数のメディアにも掲載される。
【T】
ゆとり世代の叱り方・教え方Q&A