
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
ドラッカー教授の説くマネジメントの本質は「異なるものに方向性を与える」ことではないだろうか。「社員の意識と行動を変えたい」。こう願う経営者は多いが、容易にかなわない。そもそも人の意識や行動の基盤となっている個性は変化しにくいものであり、マネジメントの力によって変えるべきではないものだ。人間には1人ひとり、異なる資質や価値観、ワークスタイルや知識、経験など、多様な持ち味と強みがあり、むしろそれらを最大限に生かすのが、ドラッカー教授が理想としたマネジメントといえる。今回はその理想のマネジメントを実践する経営者のケースを紹介する。
●ドラッカーの言葉
「組織の中の人間が果たすべき貢献は多様である。しかしそれらの貢献は、すべて共通の目標に向けられなければならない」
(『マネジメント[中]』)
〈解説〉組織に属するメンバーは、強みやワークスタイル、価値観までそれぞれに異なる。それゆえ個性に任せておくと、ばらばらなやり方で行動する。必要なのは、組織の方向性を示すことである。各自の個性を生かすための方向づけである。そのための道具が、組織の使命を明らかにするミッションであり、成果の定義、目標である。これらは組織のメンバーにとって判断や行動の基準となるだけでない。組織内部に閉じこもりがちな彼らの視線を、広く外の世界に向けさせる。
店は大繁盛。しかし、悩みが多かった。
 Mijoa(大阪市)の大塚三紀子社長は、2002年、26歳のときに、約7坪(23・1㎡)の小さなカフェを大阪市内に開いた。
Mijoa(大阪市)の大塚三紀子社長は、2002年、26歳のときに、約7坪(23・1㎡)の小さなカフェを大阪市内に開いた。
店の名前は「実・身・美(サンミ)」。「実」のある栄養バランスのいい食事で、「身」体の健康を守り、「美」しく生きる女性を応援する。そんな思いを込めて、玄米と野菜が中心の食事を提供することにした。
以前に会社勤めをしていた頃、外食の多い不規則な生活で体調を崩した経験があった。折しも女性の社会進出が進んでいた時期。ヘルシーな食事を手ごろな値段で提供するカフェがあれば、新しいニーズをつかめるとにらんだ。
狙いは当たった。わずか20席の店に、1日に180人を超える来店があり、店は大いににぎわった。
それと同時に、経営者として最初のカベにぶつかった。
最初は友人2人と始めた店だったが、売り上げが増え、新しいスタッフを採用するうち「どうして優秀な人材が入っても、思うように動いてくれないのか」と、頭を抱えるようになった。
人気店だけに、働きたいという人は多く現れた。だが、「この人こそは」と期待して採用しても、なぜかどうしても仕事ぶりに満足できなかった。大塚社長はスタッフに仕事を任せることができずに1人で仕事を抱え込み、疲弊していった。
そんなとき、書店でふと手に取ったのが、ドラッカーの本だった。「読んだ途端、店がうまくいっていない理由が分かった。要するに自分のマネジメントの問題。指示の出し方が悪いのだ」
特に心に刺さった一節がある。
「貢献に焦点を合わせることによって、コミュニケーション、チームワーク、自己開発、人材育成という、成果をあげるうえで必要な四つの基本的な能力を身につけることができる」(『経営者の条件』)
自分が的確な指示を出せないのは、スタッフに求める貢献が曖昧だから。そう直感した。
そこで「クレド」を定め、自分たちの店が果たすべきミッションを定義。さらにスタッフに期待する働き方を明確にし、共有した。
すると途端に、スタッフとの意思疎通が円滑になった。
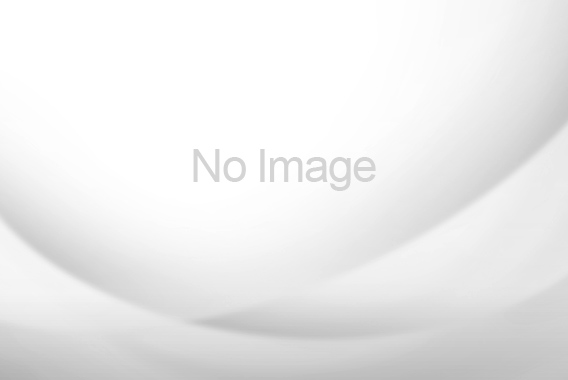 例えば、大塚社長はかねがね、忙しいランチタイムのスタッフの動きに違和感を覚えていた。日替わりの定食の注文が5つ入ると、接客のスタッフが「ランチ、ファイブ!」と声をあげ、それを合図に、厨房のスタッフが黙々と調理や盛り付けに取り掛かる。それの何が嫌で、どう変えてほしいかを、スタッフに説明できずにいた。
例えば、大塚社長はかねがね、忙しいランチタイムのスタッフの動きに違和感を覚えていた。日替わりの定食の注文が5つ入ると、接客のスタッフが「ランチ、ファイブ!」と声をあげ、それを合図に、厨房のスタッフが黙々と調理や盛り付けに取り掛かる。それの何が嫌で、どう変えてほしいかを、スタッフに説明できずにいた。
この問題が解決した。なぜなら、クレドにこんな一節があるからだ。
「私たちは、家族を迎えるように、お客様をお迎えします」
大塚社長は、どんなときでもスタッフに、お客様1人ひとりの姿を見てほしいと感じていたのだ。例えば、忙しいとつい、みそ汁に入れる具の量がバラつくことがある。けれど、お母さんが子どもにみそ汁をよそうときには、そんな不公平がないように最大限の注意を払うはずだ。
そんな思いが「家族のように迎えてほしい」という一言で、スタッフに初めてしっかり伝わった。
クレドの作成を機に、スタッフの動き方が変わった。顧客への接し方がきめ細やかになっただけではない。業務改善の提案が活発に出てくるようになった。例えば、「真冬でも、氷入りの冷水を出すのはおかしい。白湯を出したらどうか」といった具合だ。
スタッフが主体的に動くようになり、仕事を任せられるようになった。06年には念願の2号店を出店した。
その矢先、再びカベにぶつかる。
サンミに似た店が次々に現れたのだ。しばらく熱心に働いていたスタッフが退職した後、調度品からメニューまでそっくりの店を運営しているのを見つけたこともある。大塚社長は人間不信に陥った。しかし、そんなとき、ドラッカーのこの一文が目に留まった。
「あらゆる組織が自らについて定義をもつ。明快で一貫性があり、焦点の定まった定義が、組織にとって最も強力なよりどころとなる」(『未来への決断』)
この言葉に触れて、大塚社長はあらためて決意した。
「私たちには、事業の定義となるクレドがある。外側をマネできても、内側までもマネすることはできない。自分たちがすべきことをしよう。横を見ないで前を向き、会社としての貢献に焦点を合わせていこう」
そう捉えて、社業にまい進した。
現在は大阪や東京に6店を展開。ドレッシングなどの物販部門も成長している。
日経トップリーダー 構成/尾越まり恵
【あなたへの問い】
■社員への期待を「○○のように」という表現で例えると、どうなりますか?
〈解説〉人は大抵、「善かれ」と思って行動します。ただ、その「善かれ」と考える基準はまちまちです。一緒に働く人にいら立ち、失望するのは、この基準の個人差が原因であることがほとんどです。そんなときはまず、期待する基準を明確にすることです。次に、その基準を相手にイメージしやすい言葉で伝えること。その際に「○○のように」といった比喩を使うのは、有効な手法の1つです。大塚社長が使った「家族のようにお迎えする」などは、その好例です。(佐藤 等)
次号:実例で学ぶ!ドラッカーで苦境を跳ね返せ(第14回)
「汝の時間を知れ編 時間を記録して利益がV字回復」2016年11月7日公開
執筆=佐藤 等(佐藤等公認会計士事務所)
佐藤等公認会計士事務所所長、公認会計士・税理士、ドラッカー学会理事。1961年函館生まれ。主催するナレッジプラザの研究会としてドラッカーの「読書会」を北海道と東京で開催中。著作に『実践するドラッカー[事業編]』(ダイヤモンド社)をはじめとする実践するドラッカーシリーズがある。
【T】
実例で学ぶ!ドラッカーで苦境を跳ね返せ