
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
未知の世界に飛び込む変革期の経営者は悩み続けるものだ。顧客を見失うことなく、自社の強みを生かす方法は多数ある。その中で、ドラッカーは「われわれの事業は何か」という問いを通じて徹底的な思考と検討することの大切さを訴えかけている。今回はこの問いに対し、見事な解を導き出した経営者のケースを紹介する。
●ドラッカーの言葉
「『われわれの事業は何か』という問いは常に難しく、徹底的な思考と検討なくして答えることはできない。しかも通常、正しい答えはわかりきったものではない」
(『現代の経営〈上〉』)
〈解説〉この問いに向き合うと多くの経営者が業種を答える。しかし、この問いに答えるには、少なくとも次の2点を明確にする必要がある。「われわれの顧客は誰か」「顧客にとっての価値は何か」――検討すべき顧客層は複数ある。目の前の顧客だけでない。顧客を見直して初めて、「顧客にとっての自社の存在意義」が見えてくる。自社の強みを生かすのは重要だが、顧客を見失うと失敗する。そこで食品メーカーの真田(京都府宇治市)は、顧客を「良き生産者を評価できる消費者」に絞り込んだ。
2期連続の減収。それまで25年、伸びてきたのに──。食品メーカー真田(京都府宇治市)の真田千奈美専務は危機感を募らせていた。
真田は「山城屋」ブランドで干物の製造、販売を手掛ける。1904年、山城屋の商号で煮干し問屋として創業。戦後はスーパー向けに幅広く食品卸を手掛けた。
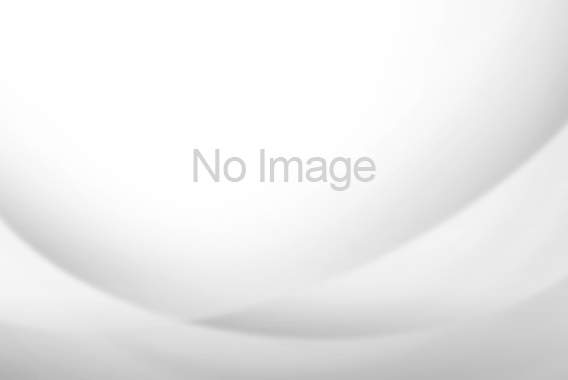 メーカーに業態転換したのは81年。当時取締役だった真田佳武社長が主導した。「大手スーパーの購買力が強まる中で、売上高30億円ほどだった、うちのような中小卸は生き残れない」とにらんだ。
メーカーに業態転換したのは81年。当時取締役だった真田佳武社長が主導した。「大手スーパーの購買力が強まる中で、売上高30億円ほどだった、うちのような中小卸は生き残れない」とにらんだ。
メーカーとしては売上高5億円ほどからの再スタートだった。しかし、強みのあった干物分野の知識を生かし、当時まだ珍しかった「金ごま」を「京いりごま」の名前で商品化。大ヒットさせるなど高付加価値路線で軌道に乗った。
こうして2005年12月期には、売上高36億円に成長した。だが、06年12月期、07年12月期と2期連続で、それぞれ約2億円ずつ売り上げが減少した。
「当時は全く(売り上げ減少の)理由が分からなかった」と、真田社長の妻、千奈美専務は話す。だが、打開策としてひらめくものがあった。
本社を移転してはどうか。
当時の真田には3大ヒット商品があった。「京いりごま」に加え、「京きな粉」、そして副菜の材料になる干物と調味料をセットにした「京のおばんざい」シリーズ。いずれも商品名に「京」を冠している。
しかし、本社工場は大阪府守口市にあった。「本社移転で、名実ともに京都ブランドになろう」。この妻の提案に真田社長が乗り、早速、京都府内に土地を手当てした。
だが、拠点を移すだけで簡単にブランドをつくれるわけがない。
そう悩んでいたとき、千奈美専務はたまたま電車で立命館大学のMBA(経営学修士)コースの生徒募集の広告を目にする。「経営を一から学び直してみよう」。そう考えて08年春、入学した。
そこでドラッカーと親交が深かった上田惇生氏の授業を受けた。ブランド力の源泉を探していた千奈美専務にヒントを与えたのは、こんなドラッカーの問いだった。
「われわれの事業は何か」──干物メーカーという答えでは浅い。干物製造の本質とは何か、中でも真田を特徴付けるものとは……。深く突き詰めると、自社が手掛けるのは「良き生産者なしに成り立たない事業」だという結論に至った。
江戸時代は米問屋を営んだ真田家。その後、取り扱う商品こそ変化したが、「生産者を大事にする」方針を貫いてきた。メーカーへの転身が消費者に支持されたのも、良い原材料を確保できたからだ。
そう考えると、2期連続減収の原因も見えてきた。干物市場全体は、日本人の食生活の変化に伴い、縮小傾向にあった。そんな中で、増収のプレッシャーを感じた現場が無理をしていたのだ。
例えば、個別のスーパーに合わせた専用商品が増えていた。1社がまとめ買いするので、1件の成約で大きな売り上げが取れる半面、価格への要求はシビア。品質が軽視されやすい。さらに契約が打ち切られたときの反動が大きい。このような「売り上げ至上主義のほころび」が、減収につながっていた。
「今こそ原点回帰。そしてわれわれの原点とは、良き生産者との協業による品質重視の商品づくりだ」
こう考えた千奈美専務は、全国各地の生産者の情報収集に励んだ。折しも、政府主導で「農商工連携」が押し進められていたころ。多くの意欲的な生産者に出会えた。
例えば、取引先から紹介された京都・与謝野町の契約栽培農家。有機肥料を使った特別栽培農法で、赤唐辛子やごまを育てている。これらを原料にした製品を山城屋ブランドで売り出したところ、好評を博した。ほかにも滋賀県産の原料を使った無漂白のかんぴょうや、明石海峡で採れる天然物のわかめなど、次々にヒット商品が生まれた。
これらの原料は生産量が限られ、全量買い取りが原則。他社が参入する余地が狭く、利益率は高い。

原点回帰を決めたとき、千奈美専務も真田社長も「売り上げは下がっていい」と覚悟した。だが、13年12月期に売上高は反転。2期連続で増収増益を記録している。
日経トップリーダー 構成/尾越まり恵
【あなたへの問い】
■あなたの会社が蓄積してきた知識は何ですか? その知識で貢献できる社会問題はないですか?
〈解説〉「成功している企業には、常に、少なくとも1つは際立った知識がある」と、ドラッカーは言います。長年の努力は無駄にはなりません。未知の世界に飛び込む変革期こそ、自社の中にすでにある知識や強みを軸足にすべきです。いざ第一歩を踏み出すときに、世の中で今、話題になっている事象に着目するのも手です。真田が農商工連携の波に乗ったように、自社が関われる社会の課題はないか。そんな切り口から意外な強みが見つかるケースもあります。(佐藤 等)
次号:実例で学ぶ!ドラッカーで苦境を跳ね返せ(第10回)
「何で憶えられたいか編 “名ばかり専務”が脱皮」2016年7月4日公開
執筆=佐藤 等(佐藤等公認会計士事務所)
佐藤等公認会計士事務所所長、公認会計士・税理士、ドラッカー学会理事。1961年函館生まれ。主催するナレッジプラザの研究会としてドラッカーの「読書会」を北海道と東京で開催中。著作に『実践するドラッカー[事業編]』(ダイヤモンド社)をはじめとする実践するドラッカーシリーズがある。
【T】
実例で学ぶ!ドラッカーで苦境を跳ね返せ