
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
食品包装材メーカーとしてアルミカップやフィルムカップ、紙カップなどの加工生産の特許技術を持つ大阪市の有限会社住友は、NTT西日本の「おまかせAI 働き方みえ~る」を導入し、従業員のパソコン業務の視える化への取り組みを開始した。従業員のパソコンのログ(履歴)を収集し、どこに無駄があるかを可視化し、業務の改善につなげようという取り組みだ。そのデータを基に、今後は、RPA(ロボティクス・プロセス・オートメーション)の導入も視野に入れる。
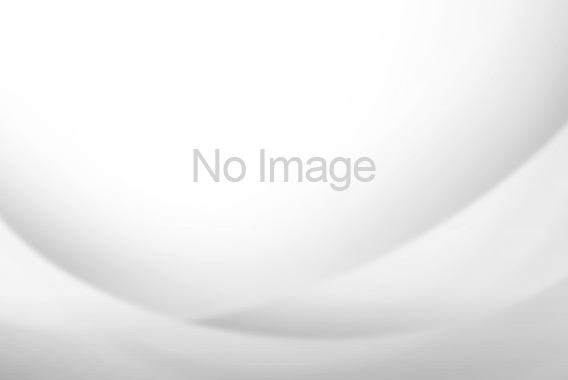 1984年設立、年商約9億6000万円。従業員は約50人。食品包装資材など加工製品の製造販売を手掛ける。素材の知識に詳しい包装資材加工メーカーとして売り上げを伸ばす。国内の3つの工場だけでなく、タイ工場でも生産を行い、近年は海外での販路を拡大してきた。多くの素材を扱うため、原材料の調達、管理が複雑になり、今後人材確保とともに、より一層の効率化を追求している。
1984年設立、年商約9億6000万円。従業員は約50人。食品包装資材など加工製品の製造販売を手掛ける。素材の知識に詳しい包装資材加工メーカーとして売り上げを伸ばす。国内の3つの工場だけでなく、タイ工場でも生産を行い、近年は海外での販路を拡大してきた。多くの素材を扱うため、原材料の調達、管理が複雑になり、今後人材確保とともに、より一層の効率化を追求している。
現在の住友の事業には2つの大きな柱がある。包装資材問屋からの注文に対応した別注品と、同社が独自に考案した企画商品である。それぞれアルミ箔、紙、フィルムなどの素材を活用して、アルミカップ、フィルムカップ、紙カップ、コンビニのおにぎりや巻きずしに使うフィルムといった食品包装資材に仕上げる。こうした商品の製造だけでなく、袋詰め、ラベルの印刷・貼り付けまで一貫して行うセットアップも請け負う。

代表取締役社長 住友壽氏
「一時期、別注品が大半を占めていた頃は、繁忙期と閑散期の差が大きかったのが悩みだった。企画商品を手掛けるようになって平準化が進み、その差が多少は改善したものの、業務量の増加は今でも課題」と住友壽社長は語る。取り扱いアイテム数は数千に上る。素材や商品の在庫管理は複雑になる一方だ。その上、「商品の売れ行きが好調なので、包装資材を至急追加生産してほしい」といったオーダーがあると、製造ラインの入れ替え、素材の調達などの煩雑な作業が発生する。
業績的には順調に推移する住友の、現在の最大の課題は人材確保だ。なんとかルーティン業務ができていても、余力がなければ急な追加オーダーや、トラブルの発生に対応できない。これでは取引先からの信用に関わる。「現状では、お客さまの新規開拓を抑え気味にして、既存の仕事に注力している。それでも既存顧客の新しい仕事が増えることも多い。業務の効率化が必須だ」(住友氏)
住友社長は「弱小企業は何か特徴を持たないと生き残れない」プレッシャーも常に背負う。そのため住友では、多くの特許や実用新案を取得して、他社と差別化を図る。「同じことをしていては勝ち残れない思いから、どんどん新しいことを取り入れている。業務量の増大にはその影響もある」と緊迫した思いを語る。
現在、約50人の従業員のうち、事務業務の担当者が10人程度、入出庫管理が3人。それ以外は工場で製造を担当する。事業拡大のために、人材を雇用したくてもなかなか難しい。それをカバーすべく、タイ工場から現地で雇用したタイ人を5人、日本本社に出向させている。彼らはスキル的には問題ないが、日本語能力などコミュニケーション面で課題を抱える。さらに今年、働き方改革が本格化した。有給取得の義務化に伴い、残業規制が強化され、業務の効率化は待ったなしの状態だ。
住友ではこれまでも、業務を効率化する手段を積極的に取り入れてきた。例えば、販売管理システムを導入した。社員にはそれぞれにJANコードを割り振って、備え付けのカードリーダーで読み込ませてから処理を行っている。自動的に業務の記録を取れるようにして、作業日報や営業日報業務を効率化した。
また、種類の多い受注処理を効率化するために、ファクスで来た注文はデジタル化してパソコンに取り込み、ペーパーレス化も進めた。営業担当者が受注した案件は、自動的に業務の流れに乗るフローをつくった。
外部講師を呼んで、社内研修も実施。社員教育にも力を入れる。「昨年秋には、社員の意識改善のために業務効率化の専門家を呼び、研修をしてもらった。“1歩1秒にいくら経費がかかるか記録しているか”と聞かれ、感心した。そういう意識の積み上げが必要だと実感した」と住友社長は語る。
さらなる業務効率化のために、今はその前提となる“働き方の視える化”に取り組む。NTT西日本が提供する「おまかせAI 働き方みえ~る」を導入した。業務に使用するパソコンの操作ログを分析し、レポートとして可視化することで、従業員の働き方や業務の中身を把握する。
2019年8月からサービスを開始した「おまかせAI 働き方みえ~る」を、住友はいち早く導入した。その理由について住友社長は「NTT西日本とは30年の付き合い。何か新しいものができたら教えてほしいと日ごろから伝えていた。従業員がパソコンで何をしているか。今まで分からなかった業務内容が視えるようになると説明を受け、試すと決断した」と語る。
働き方みえ~るでは、いつ、どんな作業をしたかという、パソコンの使用状況が分かる。業務の効率化が期待できる「繰り返し業務」の抽出、その他にはUSBメモリーや外部ストレージへの重要データの持ち出し、パソコンの交換時期、メモリーやハードディスクの使用実態などがレポートで報告される。それらを見て業務の改善につなげる。

Webで確認できる使用実態レポートを印刷したもの
住友社長は「最初のレポートを見て、業務の細かい内容はともかく、従業員全員が真面目に仕事をしてくれているのがよく分かった。従業員に感謝している。次は分析したデータを、業務改善に役立てていく」と語る。
同社が働き方みえ~るを導入してからまだ半年だが、本サービスのレポートからはさまざまな課題が見えてくる。「パソコンのログから、どの従業員がどの操作に時間をかけているか分かるようになった。まずは、その時間を短縮できないかから考える」と住友社長。また生産設備についても稼働実績が極端に少ないものがあるなど、実態が見えてきた。稼働状況に応じて工場内のレイアウトを調整することで、生産効率を高めることができそうだ。業務のベテランだから操作時間が短いわけではない。初心者だから長いわけでもない。従業員それぞれの得意不得意と、業務内容の相性のマッチングを考慮するつもりだ。
パソコン作業が可視化されることは、データ上の棚卸しにもつながる。「これまで営業の感覚的な判断に頼る部分が多く、最終的には営業と現場で話し合って生産量を決めてきた。しかし、データを見ると長い期間動いていない在庫も明確に把握できるようになる。過剰生産を防ぐことで、無駄な作業量を無くし業務全体の効率化を図ることができる。今後は感覚だけに頼らすに、データに基づいて生産計画を策定していく」と住友社長は話す。
「繰り返し行われる業務を短時間でうまくやる人の作業手順」。この共有が業務改善の常とう手段だ。それにも挑戦しつつ、さらにその先も意識する。人間の代わりに、ソフトウエアにパソコン操作を代行させるRPAの導入だ。そのためには、作業手順のマニュアル化が必要となる。
住友社長は「作業が早い人の手順をマニュアル化して共有すれば、短い時間でも生産性を高められる」と語る。働き方みえ〜るによって、次のPRA導入への視界も開けた。「小ロット多品種生産のニーズが高まり、完全な自動化は難しい。結局、人間の能力を頼りにするしかない業務がたくさん残る。新しい人を雇っても戦力になるまで時間はかかる。だからこそ、時短につながる業務の効率化が欠かせない」と住友社長は期待を寄せる。
「最終的には会社がもうかって社員への還元をめざす」という住友社長にとって喫緊の目標は、徹底した業務効率化による時短実現だ。それによって受注拡大の余力も生み出せる。コンビニや水産会社から新規大型案件の依頼もある中で、働き方みえ~るの導入成果が今後どのように出てくるのか。住友の効率化の成否を左右するかもしれない。
※掲載している情報は、記事執筆時点のものです
執筆=高橋 秀典
【M】
一足お先に!IT活用でパワーアップ