
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
店舗や駅、空港など多くの人が集まる場所で無料Wi-Fiの整備が進んでいる。ただ従来、電波の使用で電子機器にトラブルが生じる恐れがあるという理由で、整備が進まなかった場所もある。その代表が病院だ。しかし2014年、手術室などの一部区域を除いて利用可能という指針が出されて状況が変わった。それを受け、翌年には富山県内の公的病院内で初となる無料Wi-Fiの導入に動いた黒部市民病院(同県黒部市)の担当者に、導入の狙いや経緯、活用状況、今後の展望などを聞いた。
<黒部市民病院>
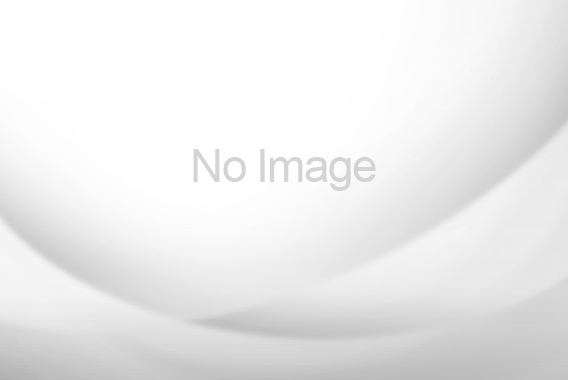 1948年に「下新川厚生病院」として開設。以後、富山県東部、新川医療圏の基幹病院として、包括的かつ高度な医療サービスを提供する。「日々念心(医療者の研究と工夫努力に裏打ちされた患者さんとの心の医療)」を病院憲章に定め、電子カルテや地域医療連携システムも積極的に活用。急性期・救急医療の拠点としての機能強化に取り組む。外来診療棟内の1、2階の待合スペースなどで無料Wi-Fiを利用可能にしている。
1948年に「下新川厚生病院」として開設。以後、富山県東部、新川医療圏の基幹病院として、包括的かつ高度な医療サービスを提供する。「日々念心(医療者の研究と工夫努力に裏打ちされた患者さんとの心の医療)」を病院憲章に定め、電子カルテや地域医療連携システムも積極的に活用。急性期・救急医療の拠点としての機能強化に取り組む。外来診療棟内の1、2階の待合スペースなどで無料Wi-Fiを利用可能にしている。
富山県東部に位置する黒部市は、トロッコ電車で有名な黒部峡谷や宇奈月温泉など、恵まれた自然環境で知られる。また、多くの企業が立地する工業地域としての顔も併せ持つ。2015年には市内に北陸新幹線・黒部宇奈月温泉駅が設置され、利便性が向上した。
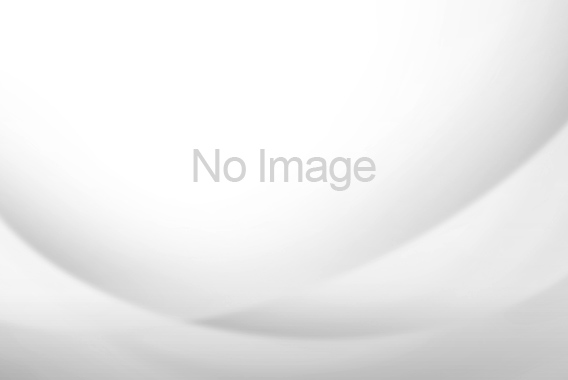
黒部市民病院医療情報部情報管理課長の荻野仁氏
黒部市民病院は、黒部市と近隣自治体(魚津市、入善町、朝日町)で構成される「新川医療圏」の基幹病院として、包括的な医療サービスを提供する。同院医療情報部情報管理課長の荻野仁氏は、院内の課題と解決策について次のように話す。
「外来を受診する方々から、“待ち時間が長い”とのご意見が多数寄せられていました。これは当院に限らず、病院全般の問題です。診察までの長い時間を少しでも快適に過ごせるようにするのは、患者に対する有効なサービスになります」。その具体策として、同院では受診者が待ち時間に利用できるWi-Fiサービスに着目。導入の検討を開始した。
これまで病院内でのスマートフォン、携帯電話の利用は、電波による医療機器などへの影響を考慮して原則的に禁止とするケースが多かった。しかし2014年8月、電波環境協議会(※)が「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針」を発表し、手術室や集中治療室など、一部のエリアを除いて利用可能との見解を示し、状況は大きく変わった。
当時、黒部市民病院では2015年の完成をめざして、外来診療棟の改築を進めていた。「病院の増改築事業に伴いネットワークインフラの再構築を検討していました。ちょうどそのタイミングで新しい指針が発表され、患者用のWi-Fiサービスを提供しようと考えたのです」(荻野氏)
受診までの待ち時間短縮に向けて努力するのはもちろんだが、採算性などを考えれば、診療能力を上げるには限界がある。そこでWi-Fiサービス提供により、待ち時間を有効に活用してもらい、患者の不満を減らすことを考えた。
※ 電波による電子機器などへの影響を防止・除去する対策を協議するために、学識経験者、関係省庁、業界団体などで構成された協議体
黒部市民病院では、電子カルテや院内システムを運用するネットワークを構築していた。当初はこれを無線化し、一部を患者に開放する方法も検討した。しかし、この方法ではネットワークを介して、院内の個人情報が抜き取られる危険性が完全には排除できない。独立したネットワークにすることとした。
独立ネットワークの場合でも、多くの人々が訪れる施設で提供されるサービスには高度な安全性が求められる。公立病院という立場上、コスト削減も至上命令だ。同院ではWi-Fiサービスを手がける事業者数社から聞き取りを行い、情報セキュリティーとコストの両面で条件を満たすサービスの選定を開始した。
検討の結果、選択したのはNTT西日本が提案した「スマート光ビジネスWi-Fi」(※)だった。中堅・中小企業を主な対象にWi-Fi環境をパッケージ化し、無線LANアクセスポイントの導入と運用サポートを提供する同サービスは、病院内の無料Wi-Fiとして十分なポテンシャルを持つと同院は判断した。
※スマート光ビジネスWi-Fiの利用には、「フレッツ 光ネクスト」または「フレッツ 光ライト」もしくはコラボ光の契約・利用が必要
「スマート光ビジネスWi-Fiはセキュリティー面だけでなく、困ったときのサポートや、病院側で自由に使えるクラウド上のWi-Fi設定サーバーなども含め、その名の通り『ビジネスでも使える安心度』を低価格で提供してくれるサービスだと思います」(荻野氏)
導入に先立ち、医師、看護師、事務職員などで構成された医療情報管理委員会で無料Wi-Fiの提供範囲について慎重に協議した。その結果、病棟での提供は他の患者の静養を妨げる恐れがあり、入院治療に影響を与える可能性があるので見送り、外来診療棟1、2階の待合スペースでの提供とした。

外来診療棟の1、2階待合スペースに無料Wi-Fiを導入した
情報セキュリティーについては、アクセスポイントと端末間の通信を暗号化するとともに、接続する端末同士で情報をのぞき見されるのを防ぐ、無線セパレーター機能で強化した。また、利用に際してはSSID(アクセスポイントを識別するためのID)とパスワードの入力を求め、接続、切断の履歴はログ情報として保管することに決めた。
「いずれも情報セキュリティーを強化する仕組みですが、無料Wi-Fiサービスの中には設定が不可能だったり、可能であっても多額の費用が必要になったりすることがありました。スマート光ビジネスWi-Fiはこれらの要件を満たし、コスト的にも満足できるサービスでした」(荻野氏)

アクセスポイント(左写真)、Wi-Fi利用可能エリアに掲示された案内ポスター(右写真)
外来診療棟の建設が完了した後の2015年10月、富山県の公立病院で初となる無料Wi-Fiサービスの提供がスタートした。活用状況について荻野氏は次のように話す。
「待合スペースでスマートフォンを操作する患者の姿を見る機会が増えました。待ち時間のストレス解消にかなり貢献しているのではないかと思います」
これまで、運用上の大きな問題は発生していない。患者からは「SSID、パスワード入力を不要にしてほしい」「利用できるエリアを拡大してほしい」といった要望は寄せられている。
「パスワード入力を不要にする要望について、市役所や他の公共施設がパスワード不要になっていることもあり、また院内の異なる利用エリアで、再度パスワードを入力させることは利用者に負担がかかるため、近日中に当院でもパスワード入力を不要にすることを検討しています。また、エリアについては、今年3月に中央受付ロビーとカフェ・イートインにアクセスポイントを増設し、土日祝日も利用できるスペースを追加しました」(荻野氏)
今後の展開として、Wi-Fi利用開始時に「病院からのお知らせ」を自動表示する仕組みを取り入れる方針だ。現在も休診などの情報は、主に院内の壁や掲示板に貼り出されている。病院ではインフルエンザ流行に伴う面会制限など、急を要するお知らせも多々発生する。こうした情報を告知するツールとして、スマートフォンが普及した現在、その活用にも期待が高まっている。
「これまで、医療分野でのICT活用は電子カルテや医療機器に偏っていました。無料Wi-Fiのように患者の利便性や満足度を高める仕組みも重要です。通信事業者もこうしたニーズがあるのを理解して、多くのサービスを開発してほしいと思います」(荻野氏)
一部の医療機関ではスマートフォンで予約を入れたり、診察の順番を自動案内したりするシステムも導入されている。「一律電源OFF」の原則から解き放たれた今、病院はICT活用の新たなフィールドへと、さらに変化を遂げていくはずだ。
※掲載している情報は、記事執筆時点のものです
執筆=林 達哉
【M】
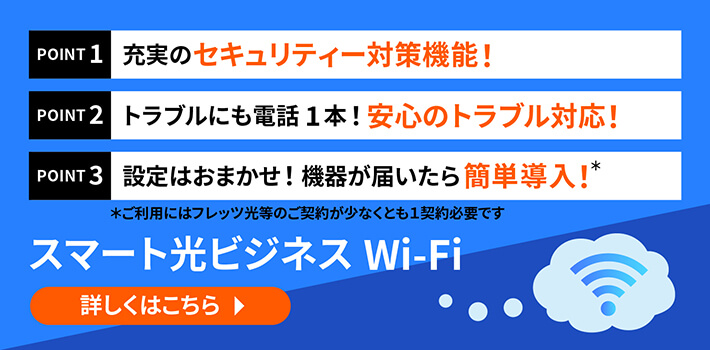
一足お先に!IT活用でパワーアップ