
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
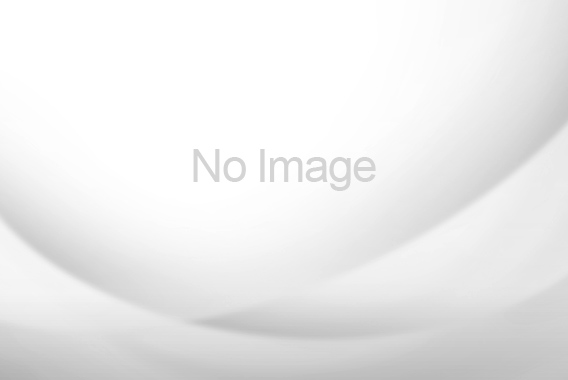
オフィス向けWi-Fiルーターは、家庭用Wi-Fiルーターとは異なり、オフィスで大勢の人が同時に使用した場合でも、快適に業務を行える点が特長です。この記事では、オフィス向けWi-Fiルーターを導入することのメリットや、オフィス向けWi-Fiルーターの選び方のポイントなどを解説します。
目次
・オフィス向けWi-Fiルーターとは
・オフィスにWi-Fiルーターを導入するメリット
・オフィス向けWi-Fiルーターの選び方
・オフィス向けWi-Fiルーターの情報セキュリティ対策
・オフィス向けWi-Fiルーターの選択に迷ったら
・まとめ

Wi-Fiルーターは、家庭用とオフィス用では性能が異なります。家庭用Wi-Fiルーターは数人程度で使用する想定で開発されていますが、オフィス向けWi-Fiルーターは、一度に多くの人が接続する想定で開発されています。
また、オフィス向けWi-Fiルーターは、家庭用Wi-Fiルーターと比べて機密性が高いデータや大容量データの通信と親和性が高いことも特長です。機種にもよりますが、一例としては来客向けWi-Fi設定機能などが挙げられます。
オフィスにWi-Fiルーターを導入することで、「配線環境に縛られない」「フリーアドレスの導入が行いやすい」「レイアウト変更が行いやすい」「ペーパーレス化が促進できる」などのメリットが得られます。これらのメリットについて見ていきましょう。
メリット1:配線環境に縛られない
有線で社内ネットワークに接続する場合、LANケーブルや有線に対応したルーター、スイッチングハブなどを使って各従業員のパソコンやOA機器などをつなげる必要があります。Wi-Fiルーターを導入すれば、無線対応のパソコンやOA機器を社内ネットワークに接続できるため、多くのLANケーブルが不要となり配線に頭を悩ませる必要がなくなります。
メリット2:フリーアドレスの導入が行いやすい
フリーアドレスとは、オフィスに従業員の固定席を設けず、共有デスクや大テーブル、会議室など自由な席で仕事ができる形式です。導入することでオフィス内のスペースを有効活用可能な他、従業員同士のコミュニケーション強化も期待できます。
また、Wi-Fiルーターを導入すると従業員のパソコンをLANケーブルにつなぐ必要がなくなるため、フリーアドレスがよりスムーズに導入できるようになります。更に、多くの従業員のパソコンが無線環境に対応できるものになれば、働く場所をオフィスに縛らないフリーアドレスの発展形である「ABW(Activity Based Working:アクティビティ・ベースド・ワーキング)」も実現しやすくなります。
メリット3:レイアウト変更が行いやすい
有線で社内ネットワークに接続していると、レイアウト変更時にLANケーブルの配線を考慮する必要があります。場合によっては、動かす必要のないOA機器の移動が発生したり、配線工事が必要になったりするケースも考えられるでしょう。
Wi-Fiルーターを使ったネットワーク環境を構築していれば、多くのケーブルが不要になるため、レイアウト変更時にLANケーブルの配線を考慮する必要もなくなります。結果、配線工事費や人件費などのコスト軽減にもつながる可能性があります。
メリット4:ペーパーレス化が促進できる
紙を主体とする業務体制から脱却し、ペーパーレス化を促進する際、Wi-Fiルーターの導入が役立ちます。Wi-Fiルーターを使ったネットワーク環境を導入すれば、タブレットやノートパソコンなどを社内で持ち歩けるようになるため、わざわざ資料をプリントアウトすることなく、手元ですぐ確認できる環境が実現できます。更に、企業が保管する膨大な量の書類も電子化すれば、管理・保管する物理的なスペースが不要になるうえ、資料の管理・検索も楽になり、業務効率や生産性の向上につながります。
ペーパーレス化を推進すれば、企業が環境問題に取り組んでいることを対外的にアピールできるため、企業イメージの向上といった副次的な効果も期待できます。
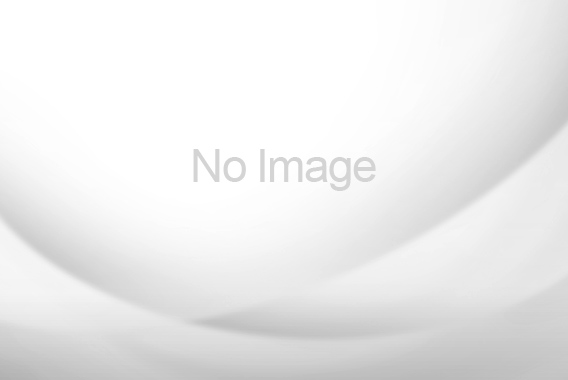
オフィス向けWi-Fiルーターの選び方には、さまざまな観点があります。以下の5つに分けて紹介します。
家庭用Wi-Fiルーターは避ける
オフィスでWi-Fiを使用する場合、家庭用のWi-Fiルーターは避けたほうが良いでしょう。家庭用Wi-Fiルーターは安価で入手しやすいメリットはあるものの、同時接続可能数が少なかったり、Wi-Fiの届く範囲が狭かったり、情報セキュリティ機能が不十分など、オフィス向けWi-Fiルーターに比べると性能が劣る傾向にあります。
オフィス用のWi-Fiルーターであれば、同時に多くの端末が接続でき、Wi-Fiの届く範囲も広く、必要十分な情報セキュリティ機能が用意されるなど、オフィス利用を想定した機能が搭載されています。
通信規格を確認する
Wi-Fiの通信規格には、2023年1月時点で「11b(IEEE802.11b)」「11g(IEEE802.11g)」「11a(IEEE802.11a)」「Wi-Fi 4:11n(IEEE802.11n)」「Wi-Fi 5:11ac(IEEE802.11ac)」「Wi-Fi 6:11ax(IEEE 802.11ax)」の6つがあります。「Wi-Fi 4」「Wi-Fi 5」「Wi-Fi 6」と、規格の数字が多くなるほど、最大通信速度が上がります。
2022年9月からは、新たに6GHz帯の電波を使用する「Wi-Fi 6E」に対応したWi-Fiルーターも登場しています。
同時接続可能台数に余裕があるものを選ぶ
Wi-Fiルーターは、基本的に同時接続できる端末台数が決まっています。そのため、事前にオフィスで使用するパソコンやタブレット、スマートフォンなどの台数を確認してから選ぶ必要があります。
たとえ自社の利用端末台数で同時接続できるWi-Fiルーターであっても、ギリギリの台数である場合は要注意です。従業員が増える場合もあるため、同時接続可能台数は想定より余裕のある機種を選ぶことが大切です。
強固な情報セキュリティ機能を有したものを選ぶ
自社の重要な情報を守るため、オフィス向けWi-Fiルーターには強固な情報セキュリティ機能が必要です。例えばRADIUSなどの外部認証サーバーと連携可能なWi-Fiルーターを使用すれば、アクセスが許された従業員しか接続できなくなり、外部からの不正な社内データへのアクセスを防ぐことができる可能性が高まります。
また、Wi-Fiに接続する際に表示されるネットワーク名(SSID)が外部の端末から見える状態になっていると、アクセスされるリスクが生じます。オフィス向けWi-FiルーターにはSSIDを隠して外部から見えない状態にする「ステルス機能」がついている機種もあります。
ゲスト用のWi-Fiを設定できるものを選ぶ
従業員用のWi-Fiとは別に、ゲスト用のWi-Fiを設定できる機能も重要です。社内データにアクセスできるネットワークをゲストに開放してしまうと、社内の情報が外部に漏えいするおそれがあります。オフィスに来訪者が多い場合、あるいは運営する店舗に多数の来客がある場合は、ゲスト用のWi-Fiを設定できる機能を有したオフィス用Wi-Fiルーターを選ぶべきです。
オフィス向けWi-Fiルーターを導入した際は、以下の情報セキュリティ対策を実施すべきです。
対策1:定期的なアップデートを行う
サイバー攻撃が後を絶たず、新しいウイルスなども次々発見されている中で、Wi-Fiルーターの脆弱性は狙われやすいポイントの1つです。オフィス向けWi-Fiルーターを導入した場合は、定期的にファームウエアをアップデートする必要があります。
対策2:通信を暗号化させる
オフィス向けWi-Fiルーターを介してデータをやり取りする際の情報セキュリティ対策として、Wi-Fi通信の暗号化が挙げられます。万が一、悪意のある第三者によりWi-Fi通信を傍受・盗聴された場合でも、暗号化されていればリスクは低減できます。
Wi-Fi通信には、主にWEPやWPA、WPA2、WPA3などの暗号化方式があり、この中で最もセキュリティが強固なのはWPA3です。
ここまでオフィス向けWi-Fiルーターについて解説しました。オフィス向けWi-Fiルーターの選択については慎重に検討する必要があります。しかしオフィス向けWi-Fiルーターはさまざまなサービス提供事業者より提供されており、どれを選べば良いか悩むという人もいるでしょう。
そのような場合、NTT西日本の「スマート光ビジネスWi-Fi ハイエンド6プラン」を選択肢の1つに入れる手があります。同サービスはオフィス・店舗向けに安心・快適な通信環境を実現する業務用Wi-Fiサービスです。前述のWi-Fi 6やWPA3に対応しているのはもちろん、ゲスト用のWi-Fi設定も可能です。またWi-Fiアクセスポイント装置の初期設定を事前に行ってくれたり、トラブル時には遠隔サポートが用意されていたりと、サポート体制も充実しています。
※「スマート光ビジネスWi-Fi」のご契約には、NTT西日本が提供する「フレッツ光」等の契約が、最低1契約必要です
オフィス向けWi-Fiルーターを設置することで、オフィスのフリーアドレス化が可能になったり、ペーパーレス化が促進できたりなど、さまざまなメリットが生じます。ただし、社内ネットワークに外部の第三者がアクセスできるような状態では、企業の重要な情報資産が漏えいするおそれがあります。情報漏えいのリスクを防止するためには、情報セキュリティ対策も同時に行うことが重要です。
※Wi-Fi はWi-Fi Allianceの登録商標、または商標です
※掲載している情報は、記事執筆時点のものです
執筆= NTT西日本
【M】
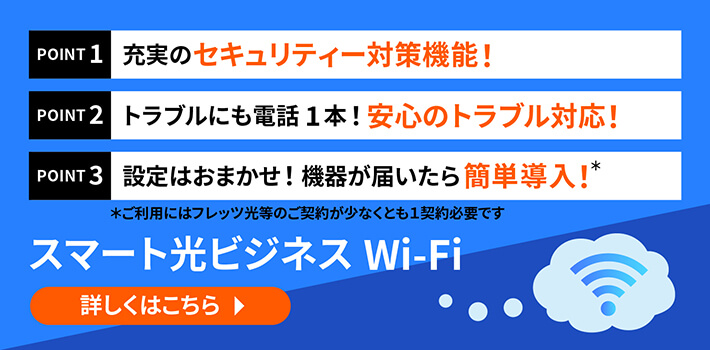
覚えておきたい情報セキュリティ&ネットワークのキホン
審査 22-1258-1