
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
パフォーマンス心理学の最新の知見から、部下をやる気にする方法を紹介する連載。今回は、その前提となる、言葉に出ていない部下の心を見抜く技術の第3回です。部下の態度で、さまざまな心理を読み取ることができます。あなたは部下の相づちに注意を払っていますか。
相づち(言語調整動作)が
オートマトン(自動操縦)になったら要注意
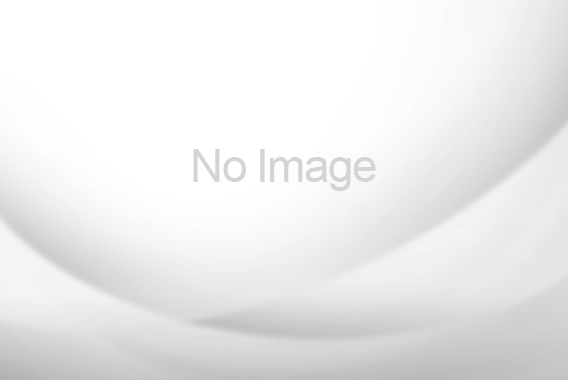 人の話を聞いていて、「まあ」とか「そうですか」とか、「素晴らしいですね」「それはどういうことですか?」などと上手に相づちや感嘆符を挟み込むと、相手は気分が良くなり、どんどん話を続けます。
人の話を聞いていて、「まあ」とか「そうですか」とか、「素晴らしいですね」「それはどういうことですか?」などと上手に相づちや感嘆符を挟み込むと、相手は気分が良くなり、どんどん話を続けます。
このような相づちや途中の感嘆を「言語調整動作(レギュレーターズ)」と呼びます。相手の話のスピードを遅らせたり速めたりする大事な動作です。だから、自分が実はよく内容が分かっていなくても「そうですか」「まあ、本当に」などと相づちを打つ人の前では、ついたくさんしゃべるようになります。
ところで、敵もさる者、部下もさる者。自分が一生懸命うなずけば上司が気分よく話すということに次第に気が付きます。そこで、「そうですか」「ビックリしました」「なるほど」「ほう」などと大げさに相づちを打ちながら、どんどん上司に気持ちよく話をしてもらおうというスキルが身に付いてしまいます。
人間は皆、「自己表現欲求」があります。実はこの「自己表現欲求」は、社会的人間に不可欠な「自己実現欲求」の条件欲求なので、地位が上がっていく人は自己表現欲求も大きく、自己実現欲求も大きいのが一般的です。そこで、聞き上手な部下がいると、ついたくさんしゃべり、何だか部下がよく言うことを聞いてくれたような満足感を味わうわけです。
ところが、実際に部下はなかなか行動しない。あれだけ相づちを打っていたのに、と不満になります。そこで、部下の相づちが本物かどうかを見抜くヒントがあるのです。「オートマトン(自動操縦)」になっていないかにまず気を付けてください。
「ほう」とか「へえ」とか「そうだったのですか」などと、言葉が毎度同じリズムで同じ言葉が出てくるようになれば、これがオートマトンです。こんなときは、部下は相づちを打つことに一生懸命なので、内容を必ずしも理解していません。
そこで、突然に話を止めて、「ところで、君はこのことをどう思うの?」と疑問文を途中で挟むようにしましょう。そうすると、相づちを打っていたのに実は理解していなかったということがはっきりと見て取れることがあります。
ずっと相手が相づちを打っているからと気分よく話してしまえば、時間の無駄になります。オートマトンを見破ったら、「ところで、君はそれについてはどう思うの?」と聞き返してみましょう。
言葉に出ていない部下の心を見抜く技術(4)
| ◆ | 大げさな相づちや同じリズム、同じ言葉での反応が続く場合は注意しましょう。 |
◆ | 何を言っても「ほう」「へえ」「そうだったのですか」などと言い続けているときには、本心と異なる可能性があります。話の途中で部下の意見を聞くなどしてみましょう。 |
※本記事は、2017年に書籍として発刊されたものです
執筆=佐藤 綾子
パフォーマンス心理学博士。1969年信州大学教育学部卒業。ニューヨーク大学大学院パフォーマンス研究学科修士課程修了。上智大学大学院博士後期課程満期修了。日本大学藝術学部教授を経て、2017年よりハリウッド大学院大学教授。国際パフォーマンス研究所代表、(一社)パフォーマンス教育協会理事長、「佐藤綾子のパフォーマンス学講座R」主宰。自己表現研究の第一人者として、首相経験者を含む54名の国会議員や累計4万人のビジネスリーダーやエグゼクティブのスピーチコンサルタントとして信頼あり。「自分を伝える自己表現」をテーマにした著書は191冊、累計321万部。
【T】
部下のやる気に火をつける方法