
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
働き方改革に消極的な企業はますます人材確保が難しくなるかもしれない。総務省の「ICT利活用と社会的課題解決に関する調査研究」(2017年3月)によると、企業が働き方改革に取り組む目的は「人手の確保」(47.9%)が最も高く、「労働生産性の向上」(43.8%)、「業務に対するモチベーションの向上」(36.3%)が続く。働き方改革に積極的な企業と、そうでない企業のどちらの方が人材を確保しやすいかは言うまでもないだろう。
働き方改革の中でも代表格が、柔軟な働き方を可能にするテレワークだ。企業のテレワーク導入の目的は「人材の採用・確保、流出の防止」(29.7%)、「社内事務の迅速化」(29.2%)、「社員のワークライフバランスの実現」(27.2%)が上位を占める。
同調査ではテレワークを導入している企業と、導入していない企業の直近3年間の業績(売上高、経常利益)を分析。「導入している企業の方が、直近3年間に業績が増加傾向にある企業の比率が高く、また減少傾向にある企業の比率が低くなっていた。テレワークの導入状況による業績の違いは、売上高よりも経常利益においてより顕著」と説明している。テレワーク導入で労働生産性が向上し、効率的な企業活動が業績の向上につながっていると分析する。一方、テレワークの課題として「情報セキュリティの確保」(43.7%)、「適正な労務管理」(37.4%)を挙げる企業が多い。
テレワークの仕組みを整えれば、インターネットやモバイル端末を利用して、社外の営業先、自宅、サテライトオフィスなどでも仕事ができる。社内やクラウド上のサーバーにアクセスし、業務アプリケーションを利用したり、Web会議で打ち合わせをしたりするといった働き方が可能だ。
これまでセキュリティの観点から業務用パソコンの社外利用に慎重だった企業も、テレワークによる働き方改革を進めるに当たり、パソコンそのものにデータを残さないなどのセキュリティ対策が求められる。
その手段として仮想化技術がある。オフィスで利用されているパソコンの環境そのものを仮想化するのが仮想デスクトップだ。仮想デスクトップはパソコンを操作する画面やキーボード、マウスといった入出力機能とパソコン本体を切り離し、データはサーバー室やデータセンター、クラウド上のストレージに保存する仕組みだ。手元の端末にデータが保存されないため、パソコン経由での情報漏えいリスクを低減できる。
また、仮想デスクトップの端末は、パソコンのほか、スマートフォンやタブレットでも利用できる。オフィスはデスクトップパソコン、会議室ではタブレット、外出先はスマホ、自宅はノートパソコンというように、適材適所で端末を使い分けながら、業務に必要なデータを利用でき、効率的な業務が行える。
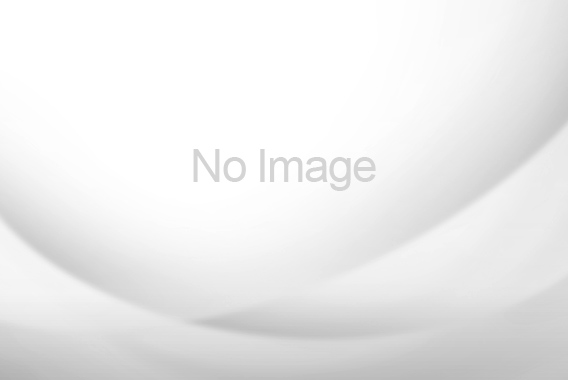 操作するパソコンそのものを仮想化する仮想デスクトップに対し、操作するアプリケーションのみを仮想化する手もある。それがアプリケーション仮想化だ。アプリケーションをパソコンではなく、データセンター、クラウド上のサーバーに置き、ネットワークを介して利用する。仮想デスクトップ同様にアプリケーションを閲覧、操作したデータは端末に残さず、パソコンやタブレット、スマホなど多様な端末の利用が可能だ。
操作するパソコンそのものを仮想化する仮想デスクトップに対し、操作するアプリケーションのみを仮想化する手もある。それがアプリケーション仮想化だ。アプリケーションをパソコンではなく、データセンター、クラウド上のサーバーに置き、ネットワークを介して利用する。仮想デスクトップ同様にアプリケーションを閲覧、操作したデータは端末に残さず、パソコンやタブレット、スマホなど多様な端末の利用が可能だ。
例えば、会社独自の業務アプリケーションを利用している場合、オフィスにある業務用パソコンからの操作のみを許可する企業もある。これでは仕事はオフィスでしかできず、社外や在宅勤務などの働き方改革を進めるのは難しい。そこで、アプリケーション仮想化により、外出先からもスマホやタブレットを使って、本来オフィスのパソコンからしか操作できなかった業務アプリケーションを参照できる仕組みにする。
経営層にとってもメリットは大きい。出張先からスマホで業務アプリケーションを参照し、スピーディーな意思決定を行うなど、経営層の仕事の仕方、働き方も変わるはずだ。
執筆=山崎 俊明
【MT】
働き方再考