
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
実例からドラッカーのマネジメントを学ぶ連載。今回は、クリーニング業界で起死回生を懸けた新規事業が次々に頓挫する中、きっかけを得てビジネスを回復させた共生社の取り組みを紹介します。クリーニングのタグというニッチな分野の技術革新にこだわった同社に起こった奇跡にはどんな秘密があったのでしょうか。
「ゼロ成長を当然のこととしてはならない。ゼロ成長企業の経営にあたっては、『われわれの強みは何か。その強みは、人口、市場、流通、技術の変化によって生ずる機会のどこに適用できるか』を問わなければならない。人的資源の能力を維持し、その生産性を向上させ続ける会社は、必ずや大きな成長の機会に出合う」
(『実践する経営者』39ページ)
<解説>どれほど苦戦している企業でも、過去を振り返れば、今の事業を確立するために必要な知識、能力を苦労して身に付けてきたはずだ。それらが蓄積されると、やがて強みと呼ばれる。しかし日々の活動で当たり前に生かされるうちに、強みであることを忘れる。
強みは実績の中にしかない。しかも多くの分野で強みを持つことはない。それゆえ「真の強みは何か」を、常に問い続けなければならない。真の強みを見つけたとき、イノベーションが可能になる。「イノベーションは強みを基盤としなければならない」(『イノベーションと企業家精神』)と、ドラッカー教授は説いた。加えて「自分たちに最も適した機会」を探せという。
さらに必要なものがある。人的資源の維持、向上だ。アイデア1つで成功することはまれである。社員の献身が生きる持続的な仕事でなければ、イノベーションとして結実することはない。結局、手持ちのものでしか勝負できない。
(ドラッカー学会理事=佐藤 等)
起死回生を懸けた新規事業が次々に頓挫。共生社(兵庫県尼崎市)の槙野雅央社長は、空回りしていた。
共生社の主力事業は、クリーニングタグの製造販売。1970年、槙野社長の父が設立した。クリーニングタグは、クリーニング店が顧客から預かった衣類に取り付ける小さな紙片。例えば下の写真のように、シャツのボタンホールにタグを通し、ホチキスで留めて顧客に返す。タグに番号や記号が印刷され、誰からいつ預かったものかが分かる。
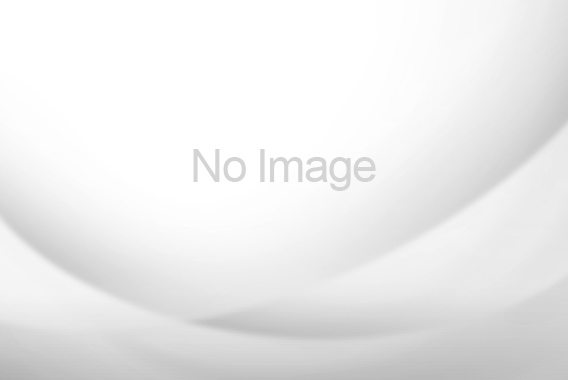
共生社の槙野社長。縮小する一途のクリーニング業界で悪戦苦闘してきた(左写真)、共生社の主力商品はクリーニングタグ。洗濯する前に衣類に取り付け、持ち主などを識別するのに使う(右写真)
クリーニングタグは、洗濯する前に衣類に付けるので、用紙やインクに耐洗性が求められる。このような特殊な資材の調達ルートを確保するのが難しく、業界の参入障壁となってきた。
槙野社長の父親は、独立前の勤務先で培ったネットワークで、このカベを突破。共生社は、競合4社の最後発ながら、唯一の専業メーカーとしてスタートした。創業から約20年、90年代初頭まで、右肩上がりの成長が続いた。クリーニング市場の拡大に、タグの供給が追い付かず、作れば作るだけ売れた。そんな最中の84年、槙野社長は24歳で入社した。
しかし、クリーニング市場は92年をピークに縮小に転じる。ここから槙野社長の奮闘が始まった。94年、タグの輸出を営業部長として指揮。国内ではクリーニング店向けのPOSシステムを販売するなどして、顧客1社当たりの売り上げを増やした。
しかし、市場縮小は止まらない。オフィスファッションのカジュアル化や形態記憶シャツの普及など、クリーニング需要を減退させる要因がいくつも浮上。90年代後半から、共生社の売り上げはジリジリと減り始めた。
何か手を打たなければ――。
99年、社長就任。その4年後、賭けに出た。クリーニング店の接客を省人化するシステムを機械メーカーと共同開発した。店内にコンベヤーを設置し、顧客が機械にカードを通すと、クリーニングを終えた衣類が自動的に出てくる。しかし、試験導入したチェーンでは「スペースを取るだけ」と不評で、本格導入には至らなかった。
それでも挑戦を続けた。06年、クリーニング店が、顧客との衣類の受け渡しに使う専用ロッカーを発売。10年には、洗濯する衣類の識別にICチップを使うシステムを開発、発売した。しかし、いずれもコスト高などが嫌気され、ほとんど売れなかった。
これらの新規事業への投資額は、約1億円に上った。しかし、すべて成果を上げることなく終わり、共生社はじり貧に陥った。一筋の光明が見えたのは、13年。知人の紹介でドラッカーの勉強会に参加したのがきっかけだ。
ドラッカーは自身の著書「実践する経営者」で、「ゼロ成長企業における経営の心得」を説く。特に成長が止まった企業のタブーとして、「軽はずみな多角化」を挙げる。なぜなら「楽な商売はない。ゼロ成長企業の大部分は、今日の平凡な事業に頼らざるを得ない」からだ。
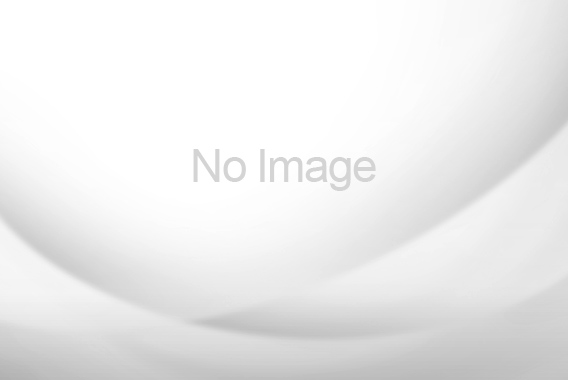
槙野社長が繰り返し読んだドラッカーの解説書
さらに「多角化や企業買収に際して問うべきは、『われわれがその事業に貢献できるものは何か』である。もし答えが『資金だけ』あるいは『何もない』であるならば、そのような多角化の結果は無残なものになる」と、付け加える。
槙野社長は、思わず考え込んだ。自分が手掛けてきた新規事業は、クリーニング業界に対し、自社ならではの貢献ができるものだったか。いずれもアイデアを出しただけで、実際に機械やシステムを作るのは、業者任せだった。しかも、そんな新規事業を可能にしたのは良好な財務体質。高収益を誇った父の時代の遺産だ。資金くらいでしか貢献できない「悪い多角化」だったのではないか。
今度こそ、タグ専業で蓄積してきた自社の強みで社会に貢献できる、新しい事業を生み出そう。
ふと思い出すことがあった。父が生前、試行錯誤を繰り返していた課題があった。それは「ホチキスを使わないクリーニングタグ」の開発だ。顧客にとって、ホチキスで留めたタグを外すのは厄介な作業だ。ケガをしたり、衣類に傷が付いたりすることもある。
そう考えて父は、さまざまな方法を試していた。あと一歩まで行ったアイデアもあったが、結局いずれも実用化に至らなかった。この課題はまだ克服されてなく、エコロジーの観点から重要性は増している。今こそ原点回帰。父が果たせなかった夢を実現しよう。
翌14年の冬、槙野社長は寒空の下、連日、大量の毛布を抱えて、コインランドリーへと走っていた。
ホチキス不要のタグについて社員と話し合ったところ、ある妙案が出た。細長いタグの真ん中に短い切れ目を入れる。そこに、タグの先端を縦方向に折ってから差し込み、開く。すると開いた部分が引っかかって留まる(下写真)。
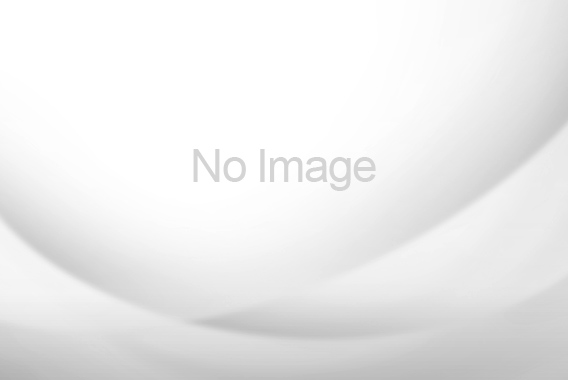
社員のアイデアから生まれた、ホチキスを使わないクリーニングタグ。紙の中ほどの切れ目に、折り曲げた先端部分を差し込んで開くと、輪になって留まる。特許取得済み
うまくいくか、試作品を毛布に付けて何度も洗濯機にかけ、テストした。そして14年「スマートエコタッグ」として製品化。特許も取得した。
しかし、クリーニング店の現場では不評だった。タグの端を折って穴に通す作業は、ホチキスで留めるより手間がかかるからだ。
槙野社長はここでいったん、このタグの拡販を諦めた。現場の声に耳を傾けるうち、別のニーズに気付いた。従来のタグに対し、「ボタンホールなどに通す際、突っかかりやすい」という不満が多く聞かれた。この問題が生じるのは、タグの端が四角く角張っているから。そこで端に丸くカーブを付けた「角丸タッグ」を開発。衣類に傷が付きにくく、顧客のためにもなる。
クリーニングチェーンに売り込むと、大手2社から受注を獲得した。1社はもともと、タグのほぼ全量を共生社から調達していたが、それらを単価が3~5%ほど高い「角丸」に切り替えた。もう1社は、共生社を含めて2社から購買していたタグを角丸1本に絞った。結果として、少なからぬ売り上げアップにつながった。
しかし、槙野社長はホチキス不要のタグを諦めたわけではなかった。売り上げのためだけではない。「今までの常識が覆り、クリーニング店でホチキスを使わないのが当たり前になる」――。そんな世の中を想像すると、思わずワクワクしたからだ。
【あなたへの問い】
■あなたの会社が創業したときの商品やサービスを現在と比べたとき、変化させてきた部分はどこですか?
■逆に、創業時と現在で共通している部分はどこですか?
■あなたの会社で「社員の努力の積み重ね」が、最も生きる部分は、どこですか?
<解説>創業時と現在を比べれば、多くの企業で商品やサービスの内容が驚くほど変わっているはずです。こうした変化は、闇雲に起こしても失敗します。あなたの会社が今、生き残っているとすれば、時代を超えて守るべき原点と、時代を先取りして変化させる部分を、先人がきちんと区別していたからです。これからも同じこと。会社のこれまでを、経営陣と共につくってきた現場をよく観察し、その声に耳を傾ける。こうして自社の軸足を確認することが、変革への第一歩です。(Dサポート代表※ 清水祥行)
※ Dサポートは、ドラッカーのマネジメント体系を活用した人材開発支援を手掛け、本連載を監修するドラッカー学会理事の佐藤等氏と清水祥行氏の2人が、代表取締役を務める
※ ドラッカーの著作からの引用ページは、ダイヤモンド社刊行の書籍に準拠
日経トップリーダー 構成/尾越まり恵
執筆=佐藤 等(佐藤等公認会計士事務所)
佐藤等公認会計士事務所所長、公認会計士・税理士、ドラッカー学会理事。1961年函館生まれ。主催するナレッジプラザの研究会としてドラッカーの「読書会」を北海道と東京で開催中。著作に『実践するドラッカー[事業編]』(ダイヤモンド社)をはじめとする実践するドラッカーシリーズがある。
【T】
実例で学ぶ!ドラッカーで苦境を跳ね返せ