
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
ドラッカーは、外部にある経営資源を活用して、外部における成果すなわち経済的価値に転換することこそ企業活動の本質と捉えている。今回はどのような外部資源に注目して、どうやって活用したのか、具体的なケースを紹介する。
●ドラッカーの言葉
「企業とは、外部にある資源すなわち知識を、外部における成果すなわち経済的な価値に転換するプロセスである」
(『創造する経営者』)
〈解説〉企業の成果とは、顧客の心理や行動に変化を起こすことである。例えば「美味しい」「安心した」など。企業はすべてこうした変化を外部にもたらして対価を得る。変化を起こすのに必要な資源も外部にある。ただし、ヒト、モノ、カネは通常、外部から調達された後、社内に備蓄される。北海道健誠社は、外部にあってほとんど生かされていない重要な資源に着目した。顧客だ。自社の顧客を活用し、「顧客の顧客」を増やした。その成果は企業の枠を超え、広く地域に広がった。
創業以来、売り上げは右肩上がり。しかし、悩みは深かった。
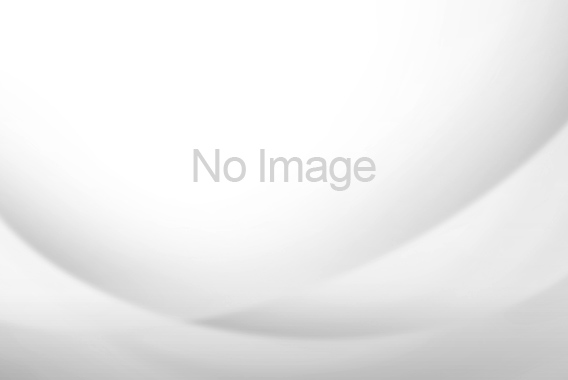 北海道健誠社(北海道旭川市)の瀧野雅一専務は、1992年、20歳のときに父母と起業した。最初に手掛けたのは病院向けの布団のリース。木綿布団が主流だった業界に羽毛布団を導入したのがヒットした。これを足掛かりに、病院やホテル向けのリネンクリーニングや個人向けのクリーニング店の展開に事業を拡大。社長と副社長に就任した父母が、障がい者雇用に積極的に取り組んだことから、メディアでも注目された。
北海道健誠社(北海道旭川市)の瀧野雅一専務は、1992年、20歳のときに父母と起業した。最初に手掛けたのは病院向けの布団のリース。木綿布団が主流だった業界に羽毛布団を導入したのがヒットした。これを足掛かりに、病院やホテル向けのリネンクリーニングや個人向けのクリーニング店の展開に事業を拡大。社長と副社長に就任した父母が、障がい者雇用に積極的に取り組んだことから、メディアでも注目された。
だが、収支は厳しかった。瀧野専務は赤字回避に奔走するストレスから体調を崩しがちで、入院することすらあった。
そんなときに、ドラッカーに出合った。「われわれの事業は何であるべきか」を問えと、ドラッカーは説く。すぐに思い付く答えは「クリーニング業」。だが、この位置付けでは現状を脱せない気がした。
クリーニング業界は、価格競争が激しい。特に法人顧客にとって、クリーニング料金の値下げは利益に直結するので歓迎される。だが、そうすると北海道健誠社の利益は減ってしまう。逆に、値上げに成功すれば、自社の利益は増えるが、顧客の利益は減る。要するに、限られたパイの奪い合いだ。そんなシーソーゲームのような関係に気づき、疑問を感じた。
顧客との関係をウィン・ウィンにすることはできないだろうか。
そこで瀧野専務が思いついたのが「顧客の顧客を増やす」というアプローチだった。北海道健誠社の売り上げの約半分を占めるのが地元のホテル向けのクリーニングで、約600施設と取引がある。営業の際に、冬になると道外からの観光客が減り、客室が埋まらないという悩みをよく耳にしていた。この時期の集客に貢献できれば、ホテルは喜ぶ。クリーニングの需要も増えるので、最終的には自社の利益にもなる。まさにウィン・ウィンだ。
地元の観光地を盛り上げるため、自社の経営資源を使ってできることはないか、と考えた。北海道健誠社は、個人向けのクリーニング店「ランドリーム」を展開しているので、地元住民との接点があった。さらに障がい者が多い従業員のために通勤用のバスを保有していた。そこで、このバスを使ってクリーニング店の個人客を法人顧客のホテルに送り込む、無料の日帰り温泉ツアーを企画した。
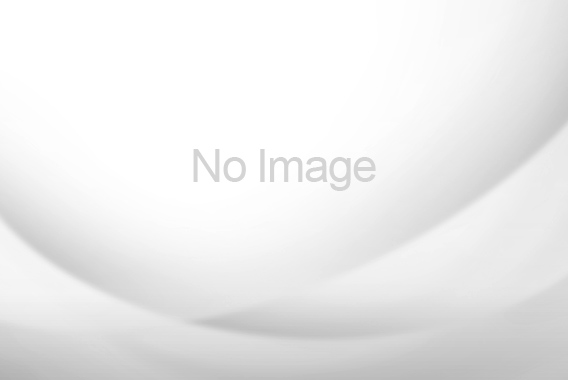 ツアーに参加できるのは、入会金と更新料を払っている「ランドリーム」会員に限定。告知にはチラシの裏面を利用した。送迎は北海道健誠社が無料で行い、ホテルには大浴場を開放してもらった。無料で温泉を楽しめるとあって、個人客には大好評だった。「ツアーに参加したいという理由で、新たに会員になる人までいた。ここまでの反響は想定外だった」と瀧野専務は話す。
ツアーに参加できるのは、入会金と更新料を払っている「ランドリーム」会員に限定。告知にはチラシの裏面を利用した。送迎は北海道健誠社が無料で行い、ホテルには大浴場を開放してもらった。無料で温泉を楽しめるとあって、個人客には大好評だった。「ツアーに参加したいという理由で、新たに会員になる人までいた。ここまでの反響は想定外だった」と瀧野専務は話す。
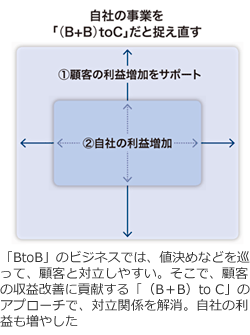 そもそも目的は、あくまでホテルの顧客を増やすこと。実際、無料日帰りツアーに参加した後、宿泊に訪れた個人客も現れ、客室稼働率の改善につながった。すると、それまではホテルから頻繁にあった値下げ要求がなくなった。それどころか、「このごろのインフレで、おたくも大変でしょう。値上げしましょうか」と切り出された。
そもそも目的は、あくまでホテルの顧客を増やすこと。実際、無料日帰りツアーに参加した後、宿泊に訪れた個人客も現れ、客室稼働率の改善につながった。すると、それまではホテルから頻繁にあった値下げ要求がなくなった。それどころか、「このごろのインフレで、おたくも大変でしょう。値上げしましょうか」と切り出された。
「われわれの事業は何であるべきか」というドラッカーの問いに今、瀧野専務はこう答える。「『B to B』でも『B to C』でもない。地域の企業同士が連携して、地域住民の喜びを生み出す『(B+B)to C』という構造を目指す。そうすれば、顧客と利益を奪い合う対立関係が解消し、協働するパートナーになれる」。
日経トップリーダー 構成/尾越まり恵
【あなたへの問い】
■あなたのお客様には、どんなお客様がいて、何を求めているでしょうか?
〈解説〉お客様のお客様が誰かを知れば、自社の事業を、広い視野で捉え直せるはずです。例えば、学習塾が得意客の印刷会社ならば、自分たちは教育産業に属していると考えてはいかがでしょう。B to Cの事業でも、お客様の家族や恋人、仲間のことを考えれば視界が開けます。
お客様と自社がチームを組んで、お客様のお客様や、お客様の家族に、今までにない価値を提供できないかと考えたとき、自社の新たな役割が見えてきます。自社の隠れた強みを発見するはずです。(佐藤 等)
次号:実例で学ぶ!ドラッカーで苦境を跳ね返せ(第6回)
「潜在的な機会編 将来の不安をチャンスに変える」2016年3月7日公開
執筆=佐藤 等(佐藤等公認会計士事務所)
佐藤等公認会計士事務所所長、公認会計士・税理士、ドラッカー学会理事。1961年函館生まれ。主催するナレッジプラザの研究会としてドラッカーの「読書会」を北海道と東京で開催中。著作に『実践するドラッカー[事業編]』(ダイヤモンド社)をはじめとする実践するドラッカーシリーズがある。
【T】
実例で学ぶ!ドラッカーで苦境を跳ね返せ