
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
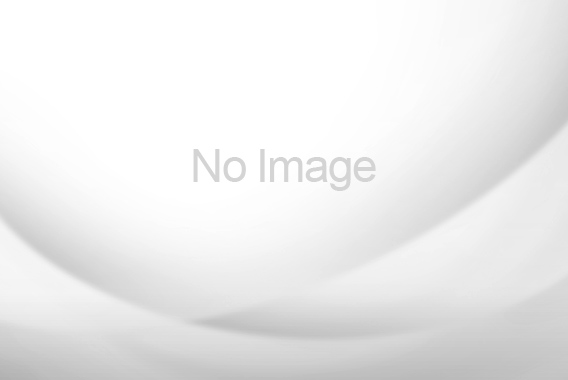
メールを使っていない人、スマートフォンを持っていない人、ソーシャルメディアを避けている人を、私たちは誰かしら知っている。「テクノロジー(あるいは新たなテクノロジー)を恐れる人は、現状で満足しているように見える」ので、そうした人をさしてラッダイトと呼ぶこともある。この言葉は、2世紀以上前にイギリスで起きた工業化への抗議運動に由来する。
現在、私たちは当時とは異なる世界に、特に経済的見通しに関しては、当時とは異なる世界に生きている。ただ、新しいテクノロジーが私たちの仕事と私たちが働く組織に及ぼす影響については、不確実性が増す一方である。安価で効率的なテクノロジーのために仕事を失うのではないかという恐れが、この不確実性に含まれる場合もある。過去20年の間にテクノロジーによってもたらされた変化に何とか適応しようと企業は悪戦苦闘してきたが、このディスラプションが速度を緩める気配はまったくない。それどころか、今後10年か20年の間に訪れる変化が与える衝撃は、恐らくさらに破壊力が増すはずである。
ここでは、進行中のディスラプションが個人と組織に与える影響について検討していこう。テクノロジーが人間の仕事を破壊する場合、恐らく2段階で発生することになるだろう――最初に人間の働き手の価値を拡大し高めて、次にその人間にすっかり取って代わるのだ。つまり多くの仕事は、テクノロジーに完全に取って代わられる直前に、テクノロジーによって改良され改善されることになる。人間の働き手の価値がテクノロジーによって短期間だけ高められるからといって、ディスラプションが起こらないなどと思い違いをしてはいけない。
来るべきテクノロジーのトレンドだけでも――自動運転車、AI、ブロックチェーン、付加製造、AR、VR――今後10年の間に仕事に多大な影響を及ぼし得るだろう。だが、総合的に考えれば、こうしたいくつものテクノロジーのトレンドは、仕事の未来に生じる甚大な破壊の前触れに当たる。実のところ、前方に延びるデジタルディスラプションの道は、テクノロジーが仕事に及ぼす破壊的影響の終わりではなく、始まりに近づいていることを示唆する。私たちの経験から言って、この破壊がやってくることを多くの人が知りながら、テクノロジーが自分たちのキャリアにどんな影響を与えるのか、たいていは社員もリーダーも考えていない。
こうしたテクノロジーによる仕事への影響は複雑で、完全に予測できるわけではない。例えば、MITの経済学者デイヴィッド・オーターによれば、現在の銀行窓口係の仕事は、ATM導入時と比べて2倍近いが、その仕事は以前とは極めて異なるという。金銭を数えたり記録をつけたりする仕事は減り、顧客との関係構築や、財務的アドバイスを与える仕事が増えているのだ。
多くの学識経験者が「今回の破壊はこれまでと異なる」と言っているが、自分たちの経験した破壊は前回の破壊とは異なると、いつの時代の人間も言うものだと、オーターは指摘する。前の世代が当時直面した破壊にどのように適応したか、私たちは過去を振り返って理解できるが、現在直面している破壊にどう適応すべきか正確に理解しようと、未来に目を向けることはできないのだ。
デロイトのCEOキャシー・エンゲルベルトはこれに同意し、一般に用いられる「仕事の未来」という表現よりも、こうしたトレンドを「未来の仕事」として論じるほうを好むと言っている。後者のほうが前者よりはるかに楽観的(かつ、正確だと私たちは考える)なので、私たちもこの用い方に賛成だ。後者には、仕事に未来があるかどうか、仕事は存在するのかどうかという疑問ではなく、将来仕事はどのように行われるのかという変化の意味合いがある。
かつてテクノロジーによる破壊が起きた時代のように、働き手と経済は新しい需要に適応するだろうと、私たちは考える。さらに、過去のそうした時代のように、人々が適応しようとするとき、そのプロセスは往々にして痛みを伴い破壊的になるだろう。過去の事例を振り返り、解決策にたどり着くまでに経験する不確実性と困難を経なくても、解決策に飛びつくことができるので、今回は以前とは違うように見えるかもしれない。
未来の仕事が個人に与える影響はどんなものだろうか? 恐らく最も重大な影響は、誰もが“生涯学習者”になる覚悟が必要になるということだろう。テクノロジーが勢いを増して変化を続けるとき、これについて行くために新しいスキルを学ぶ必要があることは明白だ。基本的には、キャリア全体にわたり、「しなやかマインドセット」を持ち続けることが求められる。テクノロジーの進歩と、人間とマシンのパートナーシップによってもたらされた変化に人間が適応するに伴い、私たちは新しいスキルを身に付ける必要がある。
選択した職業を続けるために新しいスキルを継続的に学ぶことも、確かに必要になるだろうが、一生涯のキャリアというコンセプトが過去の遺物になると考えるほうが、このダイナミックな変化の解釈としてはふさわしい。テクノロジーによる破壊のスピードには勢いがあるので、キャリアをスタートさせたときにしていた仕事は、キャリアを終えるずっと前に、世間で必要とされないものになるだろう。たとえその職がまだ存在していたとしても、テクノロジーがその仕事を再編成し、その職をこなすために求められるスキルは、それまでとはほぼ完全に異なるものになるはずだ。それどころか、ある仕事または部門でスキルの価値が低下するとき、その仕事をしている人たちを新しい役割や業界に振り向ける必要があるので、人々は新しいキャリアに向けて“方向転換する”ことになる。
方向転換が必要になるということは、職場の変化のただ中に、個人が自らのキャリアの道を描く必要があるということだ。未来に向かうこの種のキャリアパスは、サーフィンにたとえられる。サーファーは波をつかまえて、波が自然に消えるまで波に乗り、それから沖にこぎ出して、次の波を待たなくてはならない。サーファーの中には、できるだけ長い間波に乗ることを選ぶ者もいるが、次の波を好位置でつかまえられるように、ピークが過ぎたらその波から離れる者もいる。同様に、働き手の中には、特定の道にできるだけ長くとどまることを選ぶ者もいるが、早い段階で方向転換を試みて、絶頂期から絶頂期の仕事へと移動する者もいる。いずれにしろ、必要な人材を確実に手に入れるためには、組織は社員に異なるキャリアパスを支援する必要があるだろう。
一生涯のキャリアという保障を失ったことを嘆きたくもなるが、このキャリアパスの破壊と創造には、実は利点もある。新たな機会を追い求める余裕がないと思い込んで、好きではない仕事に縛られている人たちを、誰もが知っているだろう。このような行き詰まりは、仕事の未来でははるかに少なくなるはずだ。テクノロジーの変化により、直線的なキャリアパスは時代遅れとなり、特定のキャリアは行き詰まるほど長く続かないかもしれないからだ。企業はすでに、個人のキャリアパスにおけるこうした変化に適応し始めている。
キャリアの終盤で新しいスキルを学ばなくてはいけないと、年配の働き手は不満の声を上げるかもしれないが、これは主に、継続的学習に参加する必要がないと彼らが考えているからではないだろうか。1980年代や90年代に社会に出た人たちは、身に付けたスキルは、全キャリアを通して通用するものだと思っていた。そのもくろみが外れて、彼らが落胆するのも無理はない。これまで生涯学習を実践してこなかったのだから、彼らにはやはりこうしたスキルの習得は難しくなる。現代の働き手はそうした思い込みを抱いておらず、必要なスキルを学ぶことに慣れているので、継続的に学べる。
次に来るキャリアの波に向けて絶えず方向転換する必要性には、もう一つの意味がある。社員が自身のキャリア探索のコースを、情熱を込めて描く必要性および能力だ。情熱とは必ずしも、特定の目標達成のために、願望を長期にわたり最優先事項として抱くことを意味しているわけではない。私たちはむしろ、環境を見渡して、個人的関心と市場機会が最大化できるポイントを見つけるための機会として、その必要性を思い描く。
世界経済フォーラムはこの交わりを、日本語の「生きがい」というコンセプトの観点から述べている。つまり、あなたの愛すること、あなたの得意なこと、あなたが収入を得られること、そして世界が必要とすること、このすべてが一緒になった合流点のことである。情熱が変化し、破壊された世界によって新たな機会が生み出されるときに、こうした継続的キャリアの波は、生きがいを獲得する大きなチャンスを社員に与え、彼らは新しい冒険を追求できるようになるだろう。
執筆=訳者=庭田 よう子
翻訳家。慶應義塾大学文学部卒業。おもな訳書に『目に見えない傷』(みすず書房)、『ウェルス・マネジャー 富裕層の金庫番』(みすず書房)など。
【T】
MIT×デロイトに学ぶ DX経営戦略