
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
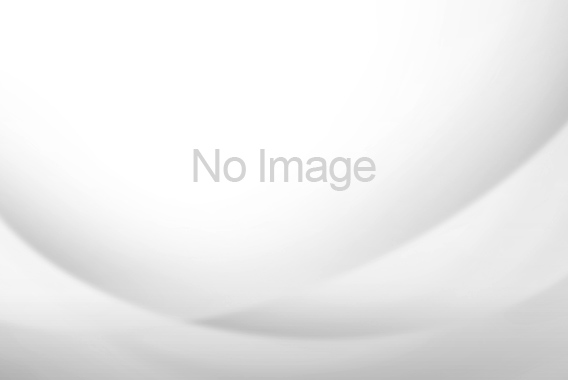
デジタルディスラプションにバランスよく取り組むためには目前の変化にきちんと対処する必要があるということを示すために、私たちの研究では、「デジタル成熟度」という野心的な目標を掲げ推進している。
「デジタルディスラプション」や「トランスフォーメーション」、その他似たような用語やフレーズを使うのは、現在ほとんどの人がこの用語を使っているからにすぎない。だが、テクノロジーに特徴づけられる競争環境に、組織や人材や経営陣が効率的に適応するために必要とされる、有意義で包括的な継続する変化を表現するときには、デジタルトレンドと結びつけられることの多い仰々しい物言いを、できるだけ避けられたらと思う。
私たちは「デジタル成熟度」を次のように定義する。
効果的に競争するために、組織内外のテクノロジーのインフラストラクチャーによる機会を活用して、組織の人員や文化、業務の足並みをそろえること。
この定義は、デーヴィッド・A・ナドラーとマイケル・L・タッシュマンの考案した、定評ある組織理論(“A Model for Diagnosing Organizational Behavior,” 1980)を参考にしている。二人は、企業の最適なパフォーマンスの主な構成要素として、「組織の整合性(organizational congruence)」という概念を主唱した。この概念は、企業に不可欠な要素――文化、人員、構造、業務――がしっかりと足並みをそろえているときに限り、企業は大きな成果を得られるというものだ。
例えば、保守的で階層的組織が活力あふれる起業家を採用しても、彼らの意欲やエネルギーを生かせないかもしれない。同様に、完全にフラットな構造の組織でも、リスクを避ける企業文化であるならば、その組織はなかなか成果を上げられないかもしれない。
整合性の要素は一見、直観的あるいは時代遅れに思われるかもしれない。だが、多くの企業では時を経ても組織のこうした要素の調和を果たせていない。デジタルプラットホームの導入は、新たなデジタル競争環境で必要とされる連携に不可欠だとはいえ、このようなプラットホームを利用するだけでは、デジタル成熟度にとって十分ではない。現代の複雑なビジネスのかじ取りをするためには、絶え間ない変化という難題に幹部が効果的に取り組めるように、企業はその文化、人員、構造、業務の間で、そしてデジタル環境とも、足並みがそろうようにすべきである。
企業が直面する主な難題は2点ある。一つは、多くの企業は、過去10年ほどにわたるテクノロジーの発展に合わせて組織を再調整していないことだ。このような企業は、いかに組織を運営すべきかということと、現在の環境で可能なこと、期待されることとの間に横たわる、かなりのギャップを埋めなくてはならない。
もう一つは、変化のスピードが速まっているので、急速に進化する環境に組織を絶えず適応させなくてはいけないことだ。組織のデジタル成熟度が高まり、すばやく適応できるようになるにつれて、組織のいくつかの側面は変化する必要があるだろうが、変化する必要がない側面もある。デジタル成熟度を高めるために、優れたマネジメントの戦術を捨てる必要はないが、現在の環境に合わせてその戦術を更新する必要がある。それを把握すること――何を変える必要があるか、変える必要がないか――は、デジタル環境におけるマネジャーの主な目的の一つである。
従って、ここでいうデジタル成熟度の概念を、組織の退屈な最終状態だと誤解してはいけない。むしろ、デジタル成熟度――さらに正確に言うなら、デジタルに成熟すること――とは、環境に応じて人員、文化、業務、構造の足並みを再びそろえて、変化するテクノロジー環境に組織が絶え間なく適応するという、柔軟性のあるプロセスである。従来型の組織にとっては、この難題は不可能ではないにしても、厄介に思われるだろう。組織が大きな変化を取り入れていなければ、確かにそうかもしれない。リーダーは組織がどのように機能するか再考し、次に、この流動的環境に対応しやすい人材モデル、文化の特徴、業務の定義、組織構造を開発する必要があるだろう。
どんな企業でもデジタルディスラプションの難題に立ち向かえるという私たちの見解は、選ばれた少数の者だけがデジタル的に考えられると説く、いわゆる多くのグルたちの処方箋とは対照的だ。彼らは、デジタルトランスフォーメーションにたどり着くためには、ミレニアル世代(デジタルネイティブ)に生来備わっているか、シリコンバレーのテクノロジー企業で働く少数精鋭だけが持つ、秘密の知識が必要だと信じてもらいたがっている。この秘密をほとんど持たない企業は、豊かな未来から締め出されると信じてもらいたがっている。
古代ギリシャで生まれた〝グノーシス〞という哲学概念は、それを得れば悟りを開けるとされる秘教的知識のことをさす。この秘密の知識は、少数の選ばれた者だけが持っており、持たない者より上位の特権的地位を占めたという。だが有能なデジタルリーダーになるには、秘密の知識など必要ない。そのようなリーダーであるということは、ほとんどコントロールできない変わりゆく環境条件の中で組織を率いるということを意味する。
「それは、有能な組織がこれまでずっとやってきたことではないのか?」とあなたは思うかもしれない。こうした反応が返ってくることは多い。手短に言えば、その答えは「イエス」だ。デジタル成熟度を獲得するために私たちが授ける処方箋の多くは、新しいものではない。しかし、マネジャーによってはこのような基礎が目新しく思われたり、デジタルディスラプションに直面して基礎を忘れたりすることがよくあり、私たちは衝撃を受ける。
デジタルトランスフォーメーションから「デジタル成熟度」にフォーカスを移すことは、競争が激化するデジタル環境に適応しようとする組織にとって、いくつかの利点がある。心理学における定義によれば、成熟とは、「適切な方法で環境に反応する能力。この反応は通常、本能的なものではなく学習されるものである」。これを踏まえて、デジタル環境に関連した5つの要素が、成熟にはあるといえる。
(1) 成熟は時間とともに現れる漸進的かつ継続的なプロセスである
企業はその発展のさまざまな段階でさまざまな課題を経験する。企業は絶え間ない成長を続け、デジタル成熟度を高めるために適応することができる。
(2) 漸進的な成熟をあまり重大ではない変化と混同してはいけない
ちょうど幼児やティーンエージャー、成人がそれぞれ異なるやり方で世界と関わるように、デジタル成熟度の高い企業は段階に応じて変化するものだ。
(3) 組織が成熟し始めたとき、最終的にどんな姿になるのか組織にはよく分からない
デジタル成熟度が自社にとってどんなものか、それに向かって歩き始めたときに分かってくるのかもしれない。実のところ、その環境について学び、その中で自分の立場を試すことは、成熟の重要な部分を占める。
(4) 成熟は自然なプロセスだが、自動的に発生するものではない
マネジャーは組織が正しく適応できるように、デジタルトレンドの知識を身に付けなくてはならない。
(5) 成熟は決して完了しない
デジタル成熟にとりかかるのに遅過ぎるということはないし、そのプロセスに終わりはないのである。
自分の組織が理想に少々届かない――そして今後もずっと届かないだろう――という健全な認識は、成熟の重要な要素である。進歩するテクノロジーの変化に敬意を示すことと、まだ改善の余地があるという認識を持つことは、むしろ成熟の極みかもしれない。デジタルに成熟している企業でも、やはりその成熟度を保つことには苦労する。デジタルの成熟を継続するためにリーダーが意識的に努力しなければならないなら、リーダー以外の者は同様のアプローチをとることで十分役に立てるかもしれない。従って企業は、絶え間ない変化に適応できるようなプロセスを進めることが必要になる。
※本連載は、『DX経営戦略――成熟したデジタル組織をめざして』(NTT出版、2020年)からの抜粋をもとに作成しています。
<著者について>
ジェラルド・C・ケイン
ハーバードビジネススクール客員研究員、ボストンカレッジ教授。『MITスローンマネジメントレビュー』や『MISクォータリー』の編集にも携わる。
アン・グエン・フィリップス
デロイトインテグレーテッドリサーチセンターのシニアマネージャー。組織のリーダーシップ、人材、文化へのデジタルテクノロジーが与える影響について研究する。
ジョナサン・コパルスキー
マーケティング理論家、成長戦略家。ブランド、マーケティング戦略、コンテンツマーケティング、マーケティングテクノロジーなどで35年以上の実績を持つ。
ガース・R・アンドラス
デロイトコンサルティングLLPのプリンシパル。デロイトコンサルティング取締役会メンバー。
執筆=訳者=庭田 よう子
翻訳家。慶應義塾大学文学部卒業。おもな訳書に『目に見えない傷』(みすず書房)、『ウェルス・マネジャー 富裕層の金庫番』(みすず書房)など。
【T】
MIT×デロイトに学ぶ DX経営戦略