
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
超高齢社会に入った日本。医療・介護のニーズが高まり、医療機関の規模・機能に応じて役割分担が進む。地域の基幹病院はがん医療などの高度先進医療に取り組み、診療所などはかかりつけ医の役割を担う。中核医療を担う基幹病院や地域の医師会などが協力しながら、地域住民の医療情報を医療機関同士で共有する病病連携や病診連携が加速している。
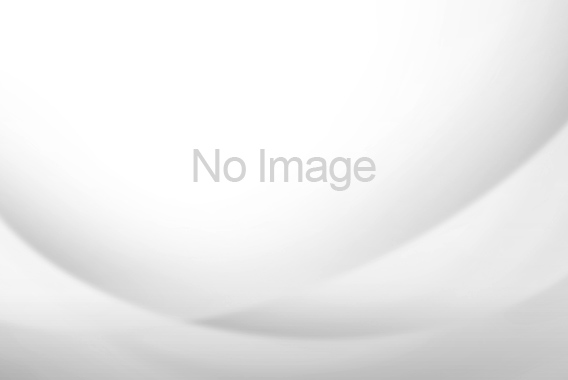 北海道の登別市などでは、連携医療機関が紹介した患者の放射線画像や検査結果などの医療情報を、ネットワーク経由で参照する医療情報連携システムを構築・運用している。病院・診療所の医師は患者の検査結果などをすぐに確認でき、迅速かつきめ細かな対応が可能だ。また、病病連携、病診連携により、患者は検査の重複が避けられ、身体への影響や検査費用の負担も軽減できる効果もある。
北海道の登別市などでは、連携医療機関が紹介した患者の放射線画像や検査結果などの医療情報を、ネットワーク経由で参照する医療情報連携システムを構築・運用している。病院・診療所の医師は患者の検査結果などをすぐに確認でき、迅速かつきめ細かな対応が可能だ。また、病病連携、病診連携により、患者は検査の重複が避けられ、身体への影響や検査費用の負担も軽減できる効果もある。
いわゆる病気やケガではなく、地域住民の総合的な健康管理を担う動きもある。医療、介護、福祉、予防医療などの各分野で一元化した情報を活用する動きも広がっている。富山県の医療法人・双星会では、病院、診療所のほか、老人保健施設、居宅介護施設、通所介護施設などを運営する。各施設では毎日、利用者の血圧や脈拍、体温などの生体データを計測し、ネットワーク経由で病院の電子カルテシステムに送信。グループのどこのクリニックや病院、介護事業所を利用しても同じ情報を共有できる。
疾病や検査などの医療情報を、病院、診療所、介護施設の間でやり取りするインフラとなるネットワークは、患者のプライバシーに関わる。だからセキュリティが重要になる。また、検査ではエックス線に加え、CT(コンピューター断層撮影装置)やMRI(磁気共鳴画像装置)のデータは大容量だ。画像データは圧縮してやり取りするものの、通信網内の遅延などに影響されにくい安定したネットワークが必要だ。
セキュリティが確保されたネットワークとしてVPN(仮想閉域網)がある。病病連携、病診連携のネットワークインフラとして、インターネットVPNを利用する医療機関もある。インターネットVPNは、データ暗号化や認証の仕組みを備えているが、通信網にインターネットを使う。通信時の安全性や安定性に懸念を持つ医療機関もあるだろう。
強固なセキュリティを確保できる専用線もあるが、高速・広帯域の専用線はコスト的に割高になる。大規模ではない診療所が導入するには敷居が高い。
セキュリティや通信速度、コスト、拡張のしやすさなど、医療機関の要件を満たすVPNもある。IP-VPNと呼ばれるVPNサービスだ。通信事業者の通信網内に医療機関ごとの閉域網を設け、安全に通信できる。
IP-VPNサービスを選択する場合、高速性や安定性を検討しよう。これが確保されれば、高精細のCT画像を専門家に読影してもらったり、診療所から基幹病院に患者の疾病の画像を送って診断に役立てたりできるようになる。今後の遠隔医療を支えるインフラになる。
また、セキュアで高速なネットワークであれば、大容量データのビデオなども医療機関でやり取りできる。研修目的で学会などのビデオ収録を配信し、研修医の最新医療の知識習得に役立てられる。
厚生労働省では団塊の世代が75歳以上になる2025年をめどに、高齢者が住み慣れた地域で暮らしを続けられるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供する地域包括ケアシステムの取り組みを進めている。地域包括ケアシステムの実現には、医療・介護などの情報を安全・安定してやり取りする必要がある。病病連携、病診連携をうまく進めるカギは、ネットワークが握っているともいえる。
執筆=山崎 俊明
【MT】