
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
前回は、女性力活用のための環境整備の土台として「ワーク・ライフ・バランス」について説明しました。今回からはもう1つの土台として欠かすことのできない「法律」について、複数回にわたって詳しく説明していきます。
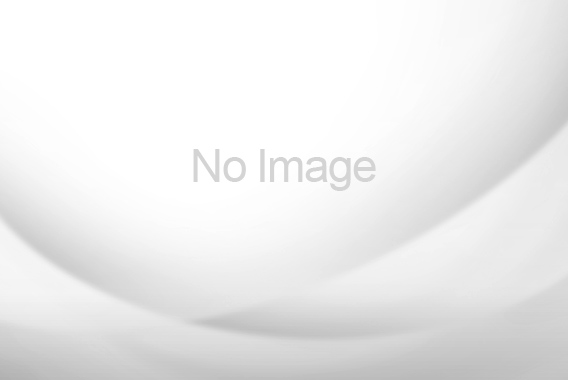 人材活用論において「ワーク・ライフ・バランス」は非常に重要であり、女性活用に限らず、モチベーション・マネジメントや生産性の高い就業環境づくりには欠かすことのできない論点です。
人材活用論において「ワーク・ライフ・バランス」は非常に重要であり、女性活用に限らず、モチベーション・マネジメントや生産性の高い就業環境づくりには欠かすことのできない論点です。
しかし「ワーク・ライフ・バランス」がいかに重要であっても、それはあくまで概念や心がけといった類いのものであり、たとえそれが欠けていたとしても、現実的には目に見える問題が起きるケースはなかなかありません。
極論をいえば、現在の日本のビジネスシーンにおいては「(ワーク・ライフ・バランスの心がけが)あればより良いが、なくても特に問題はない」と言っても差し支えないような存在です。
(実際にはワーク・ライフ・バランスの心がけすらないと人事活用制度はうまく運用できませんし、時がたつにつれ徐々に社員の不満もたまっていくため、後々目に見える問題が発生する可能性は格段に高くなります)
しかし「法律」は違います。法律を順守するのは当たり前、しなければ相応の罰則やペナルティが与えられます。また「ワーク・ライフ・バランス」とは異なり、「法律」はその内容や基準が細かく明文化されています。
企業が女性労働者保護の立場に立って“それなりの”制度を構築・運用していても、その内容にわずかなズレや乖離があれば、それは違法行為によって罰せられる対象になります。実際にはそこまで厳密ではありませんが、本質的にそこまでの厳しさを持っているのが法律です。当然経営者は「知らなかった」では済まされません。「ワーク・ライフ・バランス」と「法律」はいわば車の両輪。どちらかを重要視すればいいというものではなく、どちらも同じように重視し、かつ制度に組み入れていかなければなりません。
経営者としては、罰則や拘束力、ペナルティーやその他さまざまな規制のある法律の方を重視したくなるところですが、法律だけ重視した制度は間違いなく失敗します。あくまで法律は土台の「1つ」に過ぎません。制度を上乗せしても崩れないしっかりした土台をつくるには、「ワーク・ライフ・バランス」と「法律」の双方を、等しく制度に盛り込む必要があります。
ではまず労働関係法の基本中の基本である「労働基準法」から説明を始めます。
労働基準法は1947(昭和22)年に公布・施行された法律で、「労働組合法」と「労働関係調整法」と合わせて「労働三法」と呼ばれています。この法律は、労働協約・就業規則・労働(雇用)契約などの各種契約の最上位に位置しており、前述の規則や契約のすべてに優先する、いわば労働における最高法令といえます。
ここで注意してほしいのは、労働基準法に示されている規制や基準はあくまで「最低限」のものであり、「労働基準法に書かれている内容を満たせば問題ない」というわけではありません。労働基準法には、「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない(労働基準法第1条2項)」とあります。
つまり、労働基準法に規定されている基準を下回っている労働契約(就業規則・労働協約など)は、その下回る分については無効になり労働基準法の基準が適用されますが、同時に使用者は、さらにより良い労働条件を労働者に与えるよう努めなければいけません。
また「当社の基準を労働基準法に書かれている基準にそろえて人件費を極力抑えよう」というのも第1条違反になります。「法律を(ギリギリのラインで)守ればいい」というわけではないことを理解しておきましょう。
執筆=坂本 和弘
1975年栃木県生まれ。経営コンサルタント、経済ジャーナリスト。「社員の世代間ギャップ」「女性社員活用」「ゆとり教育世代教育」等、ジェネレーション&ジェンダー問題を中心に企業の人事・労務問題に取り組む。現場および経営レベル双方の視点での柔軟なコンサルティングを得意とする。
【T】
経営者のための女性力活用塾