
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
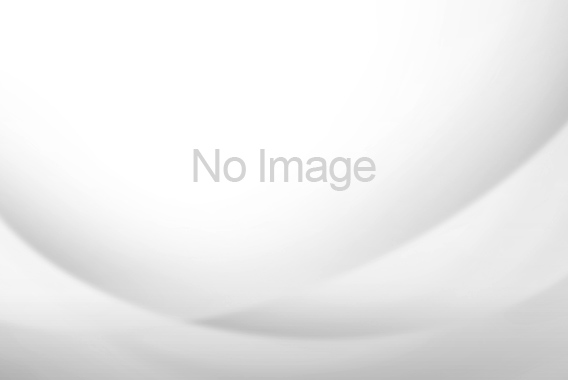
デジタル技術の進展とそれに伴う経営環境の大きな変化により、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」が注目されるようになっています。
DXという言葉はもともと、2004年にウメオ大学(スウェーデン)のエリック・ストルターマン教授が「デジタル技術の浸透により、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」ことを表す概念として提唱したのが始まりと言われています。
DXは単なる変化ではなく、ITを始めとしたデジタル技術によってフォーメーション(形態、構造、姿)を全面的にトランス(変容)するところに特徴があります。ビジネスの世界では、IT化が主にIT技術による個々の業務プロセスの最適化を意味していたのに対し、DXはAIなどを含むデジタル技術による製品、サービス、ビジネスモデル、業務フローなどの大きな変革を意味します。
DXが注目されている理由の1つに、2018年に経済産業省が「DXレポート」で指摘した「2025年の崖」があります。
多くの企業には、長年受け継がれてきているITシステム、いわゆるレガシーシステムがあります。こうしたレガシーシステムがブラックボックス化して誰も触れることができない状態になっていると、ビジネスモデルを柔軟かつ迅速に変更できず、デジタル競争についていけないことになります。また、システム維持管理費が高額化したり、システムトラブルやデータ滅失といったリスクが高まったりするなど、レガシーシステムにはさまざまな課題が生じます。
DXレポートでは、2025年には21年以上稼働しているレガシーシステムがシステム全体の6割を占めると予測しています。そしてこうしたレガシーシステムの課題が改善されない場合、2025年以降は年間で最大12兆円の経済損失が生まれると試算しています。この「2025年の崖」が迫っているため、DXの必要性がクローズアップされているのです。
また、多くの企業がDXにより業務効率や生産性を向上させたり、進化した製品やサービス・ビジネスモデルを提供したりするようになっている今、競争力の維持・向上という観点からもDXの推進が求められています。
経済産業省のDXレポートでも触れられているように、経営者の多くは将来の成長、競争力強化のためにDXが重要だという認識を持っています。しかし、DXを実践できていない企業は少なくありません。
課題の1つとして指摘されているのが、経営戦略の中でのDXのビジョンの欠如です。経営者にDXが重要だという認識はあっても、どのようなパーパス(目的)・ビジョンのためにDXを実践するかという位置づけがなされておらず、DXに着手できない、あるいは着手しても中途半端な取り組みに終わることも少なくありません。
そうならないためにも経営戦略の中にDXをしっかり位置づけ、DXのパーパス(目的)・ビジョンをスタッフと共有し、社内の仕組み・体制を構築し、予算を計上することが重要です。
また、IT人材の不足も課題になっています。DXの実践には、知識・経験のあるIT人材が必要です。しかし、そうした人材がレガシーシステムの維持・管理に追われ、新たにDXに着手する余裕がないケースが少なくありません。経済産業省は、2030年に45万~79万人のIT人材が不足すると試算しています。社内でのIT人材の確保・育成、もしくは新規の獲得が求められます。DXの取り組みが全社的なものになる場合、そうした人材でチームを組み、DX実現に向けたプロジェクトを推進することになります。
DXによって実現することは多くあります。その1つが業務の可視化です。ある大手不動産会社や関連鉄道会社は、経理財務部門の煩雑さに課題を抱えていました。また、人材確保や属人化防止などの観点から、DX推進を重視していました。
そこで、社内システムを統合管理するクラウド型プラットホームを活用したタスク・ワークフロー管理サービスを導入。事業部門から上がってくる決算情報などの定型報告、問い合わせなどの業務を一元的に可視化しました。これにより、各担当者の作業状況の確認が可能になり、業務の平準化が達成されました。また、事業部門からの膨大な資料を電子データ化し、郵送や押印などの業務の効率化を実現しています。
このシステムは連結各社の将来的なDX基盤とすることを念頭に置いており、大規模な業務変革が目指されています。
現在、従来推し進められてきた働き方改革にコロナ禍が加わり、リモートワークがニューノーマル時代の働き方として標準化されつつあります。このリモートワークの実現にも、DXが大きな役割を果たします。
ある大手建設会社は、リモートワークを含んだネットワーク型ワークフィールドの実現に取り組んでいます。これはコミュニケーションのハブとなる本社や支店、そしてサテライトオフィスや自宅などでリモートワークする社員をデジタル技術で結び、1つのオフィスにいるような仮想空間を作るものです。
キーとなっている技術は、高精度測位が可能な位置情報システム。このシステムにより、フィールドにいる社員のタグから個々の社員を認識し、フロアのレイアウト図上に個人の所在を表示します。社員は勤務地を問わず、同じ空間にいるような感覚で同僚や上司の居場所や仕事の状況を確認でき、またタイミングを見計らってコミュニケーションを交わすことができるようになっています。リモートワークを前提とした新しいオフィスのあり方として、多方面から注目を集めています。
業務の可視化、リモートワークの事例を紹介しましたが、DXによって実現できることは多岐にわたります。そして、それがゆえに「DXが重要なのは分かるが、何から手を着けたらいいか分からない」という事態に陥りがちです。
DXはデジタル技術による変革で、「社内体制の変革」と「製品やサービスの変革」に大きく分けて考えられます。社内体制の変革は、業務フローの可視化や生産プロセスの効率化による生産性の向上などです。製品やサービスの変革は、ビッグデータ解析によるマーケット分析はもちろん、サービスの向上、サービスのアプリケーション化、映像配信などを用いた新しいビジネスモデルの創造などです。
企業では、長年残存しているレガシーシステムによって業務フローや生産プロセスが非効率になっているケースが珍しくありません。まずこうした点を見直し、DXによる「社内体制の変革」を行う。そして、「製品やサービスの変革」の可能性を検討する。このように考えると、DXへの道筋が見えやすくなるでしょう。
執筆=山本 貴也
出版社勤務を経て、フリーランスの編集者・ライターとして活動。投資、ビジネス分野を中心に書籍・雑誌・WEBの編集・執筆を手掛け、「日経マネー」「ロイター.co.jp」などのコンテンツ制作に携わる。書籍はビジネス関連を中心に50冊以上を編集、執筆。
【TP】
雑談力を強くする時事ネタ・キーワード