
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
今回も、前回に引き続き、メンバーをやる気にさせ成長させるための影響力のポイントを紹介します。
メンバーから現場リーダーになると「自分たちはこれまでリーダーに守られていた」と実感するようになります。経営層からのむちゃな要求、ステークホルダーの不満の調整など、メンバーであったときには見えていなかった状況が見えてくるからです。
そんなリーダーに対し、時にメンバーは不満をぶつけます。リーダーからすれば「人の気持ちも知らないで」と思うのも無理はないでしょう。
しかし、ここで肝に銘じておくべきは「リーダーとメンバーは相互依存の関係にある」ということです。つまり、メンバーあってのリーダーであり、リーダーあってのメンバーなのです。
私も自分がリーダーになりたての頃、これをよく理解していませんでした。当時、数十人のチームの現場リーダーだったのですが、チームの中に文句の多いメンバーがいたのです。他のメンバーも巻き込んで、不満を言い募っていました。
そのメンバーはパフォーマンスが高くなく、チームにあまり良い影響も与えないので、チームから外すことを考えろと上司から言われていました。しかし「もう少し様子を見させてください」とかばっていました。それにもかかわらず文句ばかり言うメンバーにうんざりしていたのでした。
そして「メンバーは守られていることに気づいていない」と上司にグチったのです。すると上司から「せやな。確かにメンバーは上司に守られていることが分からん。でも、上司はメンバーに生かされていることが分かってない」と言われたのです。このとき言い返す言葉が見つからないほど、衝撃を受けたのを覚えています。
どんなメンバーでも、チームにアサインされているからには、そのメンバーがいなくなれば困るはずです。例えば、メンバーが急に病欠したら、プロジェクトへの影響が小さくなかった。そんな経験を持っている人も多いでしょう。
リーダーの役割を担っていると「自分がチームを守っている」と思い込みがちです。しかし、実際には「リーダーはメンバーによって生かされている」部分のほうが大きいのです。
現場リーダーとメンバーはその両方が互いの役割を果たし、初めてプロジェクトを成功に導けます。どちらかが優先ではないのです。リーダーになると時間に追われてしまい、さもリーダー優先であるように振る舞いがちですが、そうではありません。互いの成果は、互いに依存していることを理解しなければなりません(図1)。
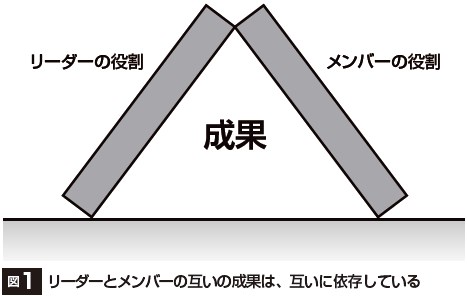
デスマーチとは、見通しが立たない状況をいいます。つまり、「どれぐらい頑張ればいいのか分からない」というコントロールを失った状態を指します。デスマーチがつらいのは、体力的な要素と同時に、「先が見えない」という精神的な要素が大きいのです。
私がエンジニアとして働き始めた1年目の頃、あるプロジェクトにアサインされました。プロジェクトリーダーであるクライアントから数週間の作業指示が出されるだけで、全体スケジュールが示されませんでした。「半年先ぐらいが最終納期だろう」と何となくに負わされるのですが、どう考えても半年で終わるような内容ではありませんでした。
それでも進めなければ始まりませんから、みんな必死で作業を進めます。マイルストーンが細かく切られ、各マイルストーンの直前には徹夜が続きます。そして、限界まで働き続けて、最終納期の直前になって「実はあと1カ月あるんだ」と宣告されるのです。結局この宣告は数回続き、半年以上にわたり限界以上に働き続けたのでした。
見通しを示さないまま、メンバーを限界まで働かせるやり方は、最も忌むべき行為です。このような方法では決してパフォーマンスは高まりませんし、あえて失敗する方法を取っているに等しいといえます。リーダーは、メンバーが安心して仕事に打ち込めるように、見通しを示す必要があります。そのためには、まず、ロードマップを示すことです。
執筆=芝本 秀徳/プロセスデザインエージェント代表取締役
プロセスコンサルタント、戦略実行ファシリテーター。品質と納期が絶対の世界に身を置き、ソフトウエアベンダーにおいて大手自動車部品メーカー、大手エレクトロニクスメーカーのソフトウエア開発に携わる。現在は「人と組織の実行品質を高める」 ことを主眼に、PMO構築支援、ベンダーマネジメント支援、戦略構築からプロジェクトのモニタリング、実行までを一貫して支援するファシリテーション型コンサルティングを行う。
【T】
システム構築のための調整力向上講座