
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
ドラッカーのマネジメント手法の中でも重要な「廃棄と集中」に挑んだ企業のケースを取り上げる。まず今回は何を「廃棄」したのか説明し、次回、その後、「廃棄」による売り上げ減をどうリカバーしたのか、経営者の決断を紹介する。
●ドラッカーの言葉
「トップ本来の仕事は、昨日に由来する危機を解決することではなく今日と違う明日をつくり出すことであり、それゆえに、常に後回しにしようと思えばできる仕事である」
(『経営者の条件』)
〈解説〉今、目の前にある問題は過去の意思決定と行動の結果である。従って、過去を優先すると、問題の抜本的な解決は遠のく。いくら計画を立てても未来は変わらない。では、何から着手すべきか。未来を計画する前に、生産的でなくなった過去の活動を廃棄するのだ。廃棄の本質は資源の解放である。過去に縛りつけられている資源を、今の自分の手に取り戻すことだ。その資源を明日の機会に集中するとき、成果が上がる。「選択と集中」ではなく「廃棄と集中」である。
突然の事業承継だった。祖父が創業した日興電機製作所(埼玉県桶川市)に、和光良一社長が入社したのは2003年、31歳のときだった。わずか半年後に、先代の父が急逝。心の準備が整わないまま、社長に就任した。
売り上げは右肩下がりだった。主力は、通信用ケーブルの接続や配線に使う端子かんといった通信設備。当時、通信業界では金属製ケーブルから光ケーブルへの移行が急速に進んでいたが、その波に乗り遅れた。光ケーブルに対応する新製品の開発が滞る中、携帯電話が普及。強みだった金属製ケーブル用通信設備の需要は減少の一途をたどっていた。
売り上げはピークの約15億円から3分の1の約5億円に減少。利益は、わずかに出ていた。和光社長が入社する前、父は苦渋の末に大規模な人員削減に踏み切り、人件費を圧縮した。最盛期には100人ほどいた社員は30人ほどに減っていた。
社長就任後、最初に力を入れたのは、地道なコスト削減で利益率を上げること。しかし、その戦略は4年ほどで行き詰まる。市場の縮小による売り上げの低下は止まらない。新市場を開拓しなくては、次の展望は見えなかった。
経営者としてカベにぶつかった。「コスト削減は課題がはっきりしているから、知識で解決できた。しかし、新市場を切り拓くには、自ら課題を設定しなくてはならない。そこで途方に暮れた」。
知識とは違う勉強を求めて、たどりついたのがドラッカーだった。そこで和光社長の琴線に触れた考え方が「廃棄と集中」。日興電機製作所には、父が残したもうからない事業が多くあった。「いつか切り捨てなくてはならないと気づいていたが、なかなか覚悟が決まらなかった。そんな自分の背中を押してくれたのが、ドラッカーだった」。
08年、和光社長はある重要な製品の製造中止を決断した。売り上げの9割を占める得意先に納入してきた、通信用の接続端子盤だ。売り上げに占める材料費が93%。ほぼ赤字の状態が何年も続いていた。
葛藤はあった。亡き父がコンペで勝ち取った仕事だったからだ。しかし、どんな製品でも、社員は真剣に取り組む。古い製品だけに、部品が製造中止になることがよくあり、その都度、社員は代替品探しに奔走する。不良を出さないように日々、細心の注意も払っていた。そんな努力の行き先が、赤字の積み上げだとしたら。社員の時間とエネルギーというかけがえのないリソースが奪われている。そう考え、勇気を振り絞った。
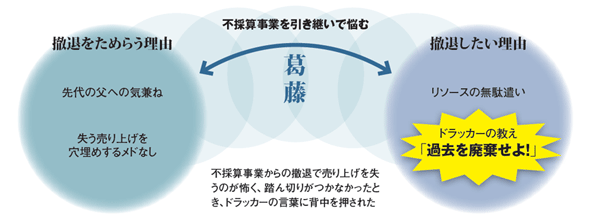
 最初にためらった理由は、父への気兼ねだけではない。2000万円以上の売り上げがあったこの製品に代わる、新しい収益源の当てがなかった。だが、ドラッカーはこう記す。「集中のための第一の原則は、生産的でなくなった過去のものを捨てることである」。この言葉は「集中すべき事業を定める前に、非生産的な事業を廃棄せよ」という順序を説くものだと理解し、納得した。
最初にためらった理由は、父への気兼ねだけではない。2000万円以上の売り上げがあったこの製品に代わる、新しい収益源の当てがなかった。だが、ドラッカーはこう記す。「集中のための第一の原則は、生産的でなくなった過去のものを捨てることである」。この言葉は「集中すべき事業を定める前に、非生産的な事業を廃棄せよ」という順序を説くものだと理解し、納得した。
赤字事業からの撤退によって、売り上げは減ったが、人手に余裕が生まれた。そこで和光社長は、製造工程を抜本的に改革した。1人の社員が1つの製品の製造工程すべてを担当する「セル生産方式」を導入。工場の生産性を引き上げた。
10年、和光社長は、もう一つの大きな「廃棄」を決断した。得意先のために15年続けてきた、光通信設備の敷設に使う部品や材料の開発を打ち切った。
年1回ほど開かれるコンペに向けて、開発の人員を割いてきた。だが、コンペでは良いところまで残るものの一度も採用されていない。15年かけても成果につながらないのは「自社の強みに合致していないからだろう」と考え、決断した。
大胆な廃棄で、和光社長にも社員にも時間の余裕ができた。そこで思わぬ自社の強みに出合う。軒並み赤字の自社製品の中に、売り上げが右肩上がりの黒字製品があった。売り上げの絶対額は小さく、売れている理由が不可解なので見過ごしていた。この小さな発見を足掛かりに、日興電機製作所は新たな突破口を開く。(第4回に続く)
日経トップリーダー 構成/尾越まり恵
【あなたへの問い】
■「いつかはやめたい」と思ったことがある商品やサービスはありませんか?
〈解説〉経営者の多くは「こんな商売はいつかやめたい」と思う事業を1つは抱えています。ただ、やめられない理由はいくらでも思いつく。「売り上げ規模が大きい」「お世話になったお客様の要望だから」など。こんな葛藤が起きるのは、事業に対する主体性を失っているからです。今は難しくても「こんな変化が起きたらやめよう」と条件を検討する。あるいは、「1年後にやめるため、得意先にこんな申し入れをしよう」と計画を立てる。そんなところから始めてはいかがでしょう。(佐藤 等)
次号:実例で学ぶ!ドラッカーで苦境を跳ね返せ(第4回)
「予期せぬ成功編 小ヒットの深掘りで赤字脱却」2015年1月5日公開
執筆=佐藤 等(佐藤等公認会計士事務所)
佐藤等公認会計士事務所所長、公認会計士・税理士、ドラッカー学会理事。1961年函館生まれ。主催するナレッジプラザの研究会としてドラッカーの「読書会」を北海道と東京で開催中。著作に『実践するドラッカー[事業編]』(ダイヤモンド社)をはじめとする実践するドラッカーシリーズがある。
【T】
実例で学ぶ!ドラッカーで苦境を跳ね返せ