
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
「太上は下これあるを知るのみ。その次は親しみてこれを誉む。その次はこれを畏る。その下はこれを侮る」(『老子』)
今回は経営者のあり方について考えてみます。中国古典で『老子』と『荘子』などを総称して「老荘思想」と呼んでいます。老荘思想というと、白いあごひげを生やした老人が俗世間を離れ、大自然の中で悠然として生きるといったイメージをお持ちの方も多いと思います。
しかし、実は現代ビジネスに役立つエッセンスが満載なのです。実際、米国の経営者の間ではリーダーシップの教本として読まれています。例えば、『老子』には、こんな理想のリーダー(君主=指導者、経営者)像が示されています。
「太上は下これあるを知るのみ。その次は親しみてこれを誉む。その次はこれを畏る。その下はこれを侮る」
(訳)最も理想的な君主は、人民はただ君主がいるということを知っているだけである。次によい君主は人民から親しまれ褒められる君主で、次は人民から恐れられる君主。最低なのは人民から侮られる君主だ。
なんと老子は、ただいることを知っているだけで、普段は存在すら意識されない、いわば空気のようなリーダーが最も理想的だと言うのです。
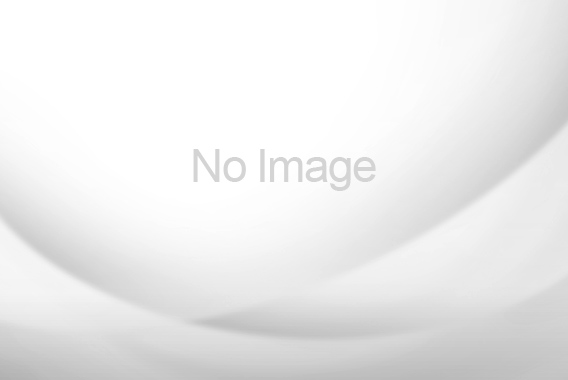 リーダーシップということばがあるように、リーダーたるもの、先頭に立って部下を鼓舞しながら率いていかねばならない。あるいは進んでいく方向を指し示して導くべきだ。こんなふうに考えていませんか。でも老子が語る理想的なリーダー像は、そんな姿とはかけ離れています。
リーダーシップということばがあるように、リーダーたるもの、先頭に立って部下を鼓舞しながら率いていかねばならない。あるいは進んでいく方向を指し示して導くべきだ。こんなふうに考えていませんか。でも老子が語る理想的なリーダー像は、そんな姿とはかけ離れています。
こうしたリーダーを理想とするのは、老子は「無為自然」という考え方を大切にしているからです。「無為自然」とは「なんら作為をせず、あるがままの状態」です。注意が必要なのは、この「無為」は「なにもしないこと」ではなく「なんら作為(=わざとらしいこと)をしない」ことだということです。
まだふに落ちない方がいるかもしれませんね。企業経営で考えてみましょう。例えば、起業したばかりの頃は業務のほとんどを経営者(リーダー)がやる場合がよくあります。社員が少ないうえ、一番業務に精通しているのは経営者だというケースも多いからです。でも、なんでも経営者がやっていると、ある程度の規模までしか企業は大きくなりません。徐々に社員に業務を任せていくことが必要になります。そう、権限委譲が必要です。
リーダー一人でできることは限られています。このため先人たちは権限委譲を行い組織が自律的に動くように創意工夫を重ねてきました。例えば、経営の神様・松下幸之助さんが始めた、製品など事業部ごとに収支計算や意思決定を行う「事業部制」、組織を小集団に分けて独立採算とする京セラの「アメーバ経営」などが代表的な手法です。
ここまで説明するとお分かりのように、権限委譲を行い、自分がいなくても組織が回り、成長する仕組みを作ることもリーダーの役割なのです。リーダーが引っ張るのではなく、部下が主体的に動く組織を作り上げれば、リーダーの存在感は薄くなるかもしれません。しかし、そうした組織こそ強いのです。老子が示した究極のリーダー像もそう考えれば、理解できるでしょう。
首都圏などで生花店「青山フラワーマーケット」をチェーン展開するパーク・コーポレーション社長の井上英明さんは、こんな理想像に近づくことを心がけている経営者といえるかもしれません。井上さんは、毎週火曜日と木曜日は会社に出社しません。その時間を活用し、店舗を回ったり、新しい商業施設を見学したりしています。また毎年9月の1カ月間は完全に会社を休み、メールのチェックもしないそうです。
こうした働き方でも会社が回っていくようにするため、以前から部下への権限委譲を積極的に進めてきました。研修などにも力を入れ、社員の成長を後押ししています。井上さんが会社に出勤せず長期休暇をとるのは、経営者が会社にいると、結局社員が経営者を頼ってしまい、新しいことを考えなくなってしまうからだといいます。
もちろん「いくら空気のような存在が最高のリーダー」といっても、社員に「社長は高い給料をとっているのになにもしない」などと思われてはいけません。社長は社長にしかできない仕事をしっかりやる。部下に任せるところは思い切って任せるというメリハリが大切です。
大きな声で叱咤激励して無理やり部下を動かすのではなく、空気のような存在でなにも指示していないのに、部下が自然に自分の役割を果たしてしまう。こんなリーダーを老子は理想と考えているのです。権限委譲がきちんと機能して、社員が自律的に動いている組織は、ちょっと目には経営者の存在感が薄く見えるかもしれません。しかし、それこそが成長を続けることができる強い組織なのです。
【T】
ビジネスに生かす中国古典の言葉