
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
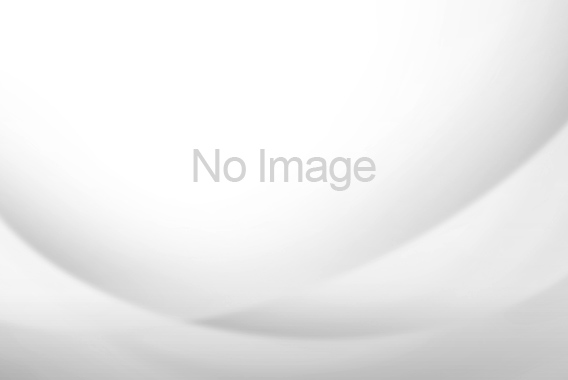
いま話題のトレンドワードをご紹介する本企画。第4回のテーマは、「インボイス制度の各種特例など」です。言葉の意味、そしてその背景や関連する出来事を解説していきます。みなさまのご理解の一助となれば幸いです。
インボイス制度の各種特例などとは、
2023年10月からスタートするインボイス制度。4月に消費税法などの一部を改正、インボイス発行事業者として登録している事業者およびインボイス発行事業者になることを検討している事業者に対し、小規模事業者に対する負担軽減措置である「2割特例」、1万円未満の少額取引について一定の帳簿のみを保存することで仕入税額控除が可能になる「少額特例」などが設けられた。
2023年10月に迫ったインボイス制度の施行ですが、一定規模以下の事業者の実務に配慮し、柔軟な対応が可能となるよう事務負担の軽減措置を目的に、いくつかの特例・制度が設けられています。以下でその概要を紹介します(詳しくは、国税庁の「令和5年度税制改正関係(インボイス関連)」を参照するとよいでしょう)。
「2割特例」
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった事業者は、仕入税額控除の金額を特別控除税額とすることができる。簡単にいえば、この特例を適用した場合、売上税額の2割を納付することとなる。
「少額特例」
少額(税込1万円未満)の課税仕入れにつき、インボイスの保存がなくとも一定事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能。これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても適用される。
その他
・「少額な返還インボイスの交付義務免除」
インボイス発行事業者が国内で行った課税資産の譲渡等につき、返品や値引き、割戻しなどの売り上げに係る対価の返還等を行った場合には返還インボイスの交付義務があるが、その金額が税込1万円未満である場合には、返還インボイスの交付義務が免除される。
・「登録制度の見直しと手続の柔軟化」
2023年4月以降の登録申請であっても、2023年9月30日までに登録申請書を提出した場合は、制度開始日である2023年10月1日から登録を受けることが可能。また、免税事業者が2023年10月2日以降に登録を受ける場合、登録申請書に登録希望日(提出日から15日以降の希望する日)を記載することとし、登録希望日から登録が受けられることとなった。
なお、改正の概要などは、パンフレット「消費税 インボイス制度に関する改正について」がわかりやすく参考になります。また、そもそものインボイス制度については、国税庁の「特集 インボイス制度」を参照するとよいでしょう。困ったときには「インボイス制度に関する各省庁の相談窓口」が頼りになります。
こうした支援制度にはそれぞれ、対象者と対象期間が異なるため、よく注意して利用する必要があります。インボイス制度の支援措置については財務省「インボイス制度、支援措置があるって本当!?」を参照するとよいでしょう(ここでは、小規模事業者、中小事業者、すべての方、のように対象別にまとめられ、対象期間もそれぞれ明記され、わかりやすく理解できます)。以下で各ポイントについて簡単に紹介していきます。
特例の主な対象は?
・2割特例は、制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった事業者で、2年前(基準期間)の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす事業者が対象となる。
・少額特例は、2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下、または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売上が5千万円以下の事業者が対象となる。
特例の活用ポイントは?
・2割特例は、仕入税額控除の金額を「特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)」とすることができるのがメリット
・少額特例は、1万円未満の課税仕入れについて、インボイスを保存することなく、帳簿のみの保存で、仕入税額控除の適用が可能となるのが利点
対象者と対象期間に加え、支援を受けるための手続きや、特例を選択した場合のその後の継続適用、少額特例の対象単位など、細かなルールが定められているので、先述の国税庁「特集 インボイス制度」などを参考に、状況に応じて専門家の知見を活用するなど、慎重に判断を行いましょう。財務省「インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答」は、これら支援措置に対し、よくある質問が図入りで解説され、参考になります。
中小事業者に対する事務負担軽減目的の時限措置である点を理解、変更の可能性を想定して情報をチェック
中小事業者に対する事務負担軽減措置とはいえ、2割特例と少額特例の適用期間が異なることや、少額特例は2029年9月30日までの適用で、課税期間の途中であっても2029年10月1日以後に行う課税仕入れは適用されないなど、不便と思える点もあります。
特例の目的から考えて、今後、状況改善や利用・対応状況に応じたルール変更が行われる可能性が想定されます。国税庁や財務省のページなど、インボイス制度に関する情報を、定期的にチェックするのがおすすめです。変更があった際など、必要に応じて社内などで情報共有を行うのも有効でしょう。
2024年1月から義務化予定の「電子帳簿保存法」、さらに「デジタルインボイス」も視野に入れ、先を見据えたシステム対応を
これら「インボイス制度の各種特例など」は時限措置であるため、期間終了後に慌てないよう、措置後の方向を事前に探っておくのがおすすめです。来年1月から義務化予定の「電子帳簿保存法」も猶予がありません。加えて、インボイスの電子化も視野に、バックオフィス業務のオール電子化も検討しましょう。
また、デジタル庁は、グローバルな標準仕様「Peppol(ペポル)」(ベルギーのOpen Peppolが管理する電子文書を相互運用するための国際規格)をベースとしたわが国におけるデジタルインボイスの標準仕様「JP PINT」の普及・定着の取り組みを行っています。「JP PINT」は昨年10月28日に発表され、業務ソフトなどを開発するベンダーの間で、対応製品の開発の動きが広がっています。デジタルインボイス製品については、「EIPA(デジタルインボイス推進協議会)」の情報も参照しましょう。
バックオフィス業務をデジタルで完結すれば、経理業務の効率化はもちろん、ヒューマンエラーの防止、取引先や海外企業との効率的な取引など、大きなメリットが想定されます。未来を見据えた効率的なシステムを検討・相談していくとよいでしょう。
※掲載している情報は、記事執筆時点のものです
執筆=青木 恵美
長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「Windows手取り足取りトラブル解決」「自分流ブログ入門」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。
【T】
知って得する!話題のトレンドワード