
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
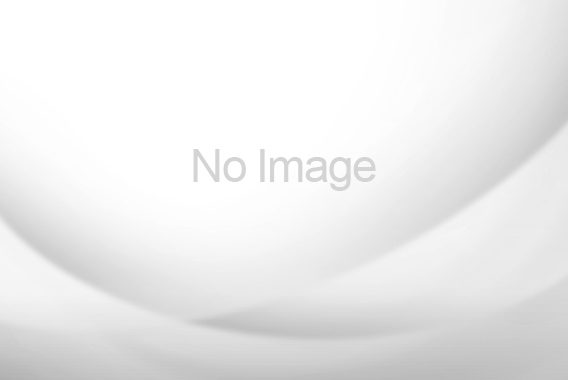
いま話題のトレンドワードをご紹介する本企画。第5回のテーマは、「令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直し」です。言葉の意味、そしてその背景や関連する出来事を解説していきます。みなさまのご理解の一助となれば幸いです。
令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しとは
2024年1月から行われる「電子帳簿保存法による電子取引データの保存」の義務化を目の前に、「令和5年度の税制改正による電子帳簿保存制度の見直し」において、事務負担軽減のための優遇措置がとられている。優遇措置は「優良な電子帳簿」の範囲の見直し、国税関係書類についてのスキャナー保存制度の見直し、電子取引情報についての電磁的記録保存制度の見直しの3つが盛り込まれている。
2022年1月1日より、改正電子帳簿保存法が施行され、国税関係の帳簿・書類のデータ保存について、抜本的な見直しが行われました。この改正電子帳簿保存法の大きなポイントは、電子取引における電子データ保存の義務化で、「電子取引でやりとりした書類(電子メールやオンライン上で受け取った領収書や請求書など)は、データのまま保存しなければならない」とされました。ところが、2021年12月に発表された「令和4年度税制改正大綱」において、2023年12月末までに行われた電子取引については従来どおり紙での保存を認めるという猶予措置がとられました。
2022年12月、与党の税制調査会は「令和5年度税制改正大綱」を発表。この改正では、上記猶予措置の終了による2024年1月からの「電子取引データ保存の義務化」を目の前に、事務負担軽減のための優遇措置がとられています。
電子帳簿保存法における「電子帳簿等保存制度」は、税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など(国税関係書類)」を、紙ではなく電子データで保存することに関する制度で、電子帳簿等保存、スキャナー保存、電子取引データ保存の3つに区分されています。まずはこの制度について、おさらいしておきましょう。
「電子帳簿等保存制度」とは
①電子帳簿等保存(希望者のみ)
自身で最初から一貫してパソコンなどで作成している帳簿や国税関係書類は、プリントアウトして保存するのではなく、電子データのまま保存ができる。例えば、会計ソフトで作成した仕訳帳やパソコンで作成した請求書の控えなどが対象となる。さらに、一定の範囲の帳簿を「優良な電子帳簿」の要件を満たして電子データで保存していると、後からその電子帳簿に関連する過少申告が判明しても、過少申告加算税が5%軽減される優遇措置がある。
②スキャナー保存(希望者のみ)
決算関係書類を除く国税関係書類(取引先から受領した紙の領収書・請求書など)は、その書類自体を保存する代わりに、スマホやスキャナーで読み取った電子データで保存できる。
③電子取引データの保存(法人・個人事業者は2024年1月から対応が必要)
申告所得税・法人税に関して帳簿・書類の保存義務がある者は、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子取引データを保存しなければならない。例えば、電子メールに添付した・添付されたPDF形式の請求書、ECサイトでの買い物をした際にダウンロードした領収書、請求書発行システムを経由してやりとりした請求書や発注書、などが該当する。
なお、①~③の保存には、記録の改ざん防止などのため、一定のルールに従う必要があるので注意が必要です。令和5年度税制改正の内容も含めた最新の情報は、国税庁「はじめませんか、帳簿・書類のデータ保存」「はじめませんか、書類のスキャナー保存」「電子取引データの保存方法をご確認ください」などを参照するとよいでしょう。
「令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直し」における今回の改正の内容は、①「優良な電子帳簿」の範囲の見直し、②国税関係書類についてのスキャナー保存制度の見直し、③電子取引情報についての電磁的記録保存制度の見直し、の3つです。概要は「電子帳簿保存法の内容が改正されました」が分かりやすいでしょう。
2024年1月からの電子取引データの保存の義務化、および、任意での電子帳簿やスキャナー保存において、今回の措置により改ざん防止や検索機能への要件が取り除かれるなどで、本来の方向よりも、事務処理の負担が大幅に軽減します。古い情報に基づいていては、不要な作業を行ってしまう可能性があるので、常に最新の情報を参照し、対応するのがよいでしょう。
「令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直し」の内容
①「優良な電子帳簿」の範囲の見直し
「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」の対象となる帳簿の範囲が見直され、申告所得税・法人税について、措置の適用を受ける場合に「優良な電子帳簿」として作成しなければならない帳簿の範囲が「仕訳帳、総勘定元帳、その他必要な帳簿(全ての青色関係帳簿)」から、「仕訳帳、総勘定元帳、その他必要な帳簿(売り上げ、仕入れ、売掛金、買掛金、手形などに限定。「電子帳簿保存法の内容が改正されました」2ページ参照)」に見直された。
②国税関係書類についてのスキャナー保存制度の見直し
(1)解像度・階調・大きさに関する情報の保存が不要に
国税関係書類をスキャナーで読み取った際の解像度・階調・大きさに関する情報の保存を必要とする要件が廃止され、これらの情報の保存は不要となった。
(2)入力者等情報の確認要件が不要に
スキャナー保存時に記録事項の入力を行う者またはその者を直接監督する者に関する情報を確認できるようにしておく要件が廃止された。これは電子取引データの保存についても同様。
(3)帳簿との相互関連性の確保が必要な書類が重要書類限定に
スキャナーで読み取った際に、帳簿と相互に関連性を確認できるようにしておく必要がある国税関係書類が「重要書類(契約書・領収書・送り状・納品書などのように、資金や物の流れに直結・連動する書類)」に限定されることとなった。この見直しにより一般書類(見積書・注文書や納品書の写しのように、資金や物の流れに直結・連動しない書類)」については、相互関連性の確保が不要となった。
③電子取引情報についての電磁的記録保存制度の見直し
(1)検索機能の全てを不要とする措置の対象者の見直し
税務調査などの際に電子取引データの「ダウンロードの求め(調査担当者にデータのコピーを提供すること)」に応じられるようにしている場合、検索機能のすべてを不要とする措置につき、基準期間(2課税年度前)の売上高が「1000万円以下」から「5000万円以下」の保存義務者に拡大された。さらに、「電子取引データをプリントアウトした書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができるようにしている保存義務者」が検索機能不要の対象者に追加。
(2)令和4年度税制改正で措置された「宥恕(ゆうじょ)措置」は2023年末で終了
令和4年度税制改正による「宥恕(ゆうじょ)措置」は2023年末に終了する。この「宥恕(ゆうじょ)措置」を適用して、その間やりとりした電子データを紙で保存している場合、保存期間が満了するまでその書面を保存し、税務調査などの際に提示・提出できるようにしておけば問題はない。
(3)新たな猶予措置の整備
下記要件2件をいずれも満たしている場合は、改ざん防止や検索機能など保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくだけでよい。
・保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要)。
・税務調査などの際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」およびその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めに応じることができるようにしている場合。
2022年1月施行の改正電子帳簿保存法が大きく話題となった理由は、電子取引データの保存の義務化が盛り込まれたことですが、そこで2年の猶予措置が図られたのは、中小企業、小規模企業・個人事業者にとって、準備期間が短く対応が難しいといった背景がありました。
電子帳簿保存制度における電子取引データ保存の義務化は、2023年末で猶予措置が終了し、来年1月分からすべての事業者が対応しなければならないので、注意が必要です。その一足先に2023年10月からは「インボイス制度」もスタートします。こうした気ぜわしい変化の中では、日々の忙しさもあって「義務化部分のみ」への対応となりがちです。
しかし今後、あらゆる分野で電子化が進む未来を考えると、業務の効率化や人的ミスの軽減のためにも、早めにバックオフィスのオール電子化を進める姿勢が重要です。今回の改正で敷居の下がった電子帳簿やスキャナー保存への整備も併せて行っていくのがおすすめです。なお、電子帳簿保存制度については今後さらなる措置や義務化など、改正が行われる可能性もあるので、情報を常にチェックしておきましょう。
現在、電子帳簿保存制度に対応した会計ソフトやクラウドサービス、各種ソリューションが多く登場しており、それらを検討・導入するのが効率的ともいえます。中にはネットバンキングやクレジットカード/キャッシュレス決済のデータと連携するシステムもあり、経理業務のさらなる効率化も可能です。インボイスと電子帳簿保存制度の相次ぐ義務化により、オフィス業務を取り巻く環境が大きく変化していくこの状況を機に、電子化による経理の効率化や財務管理の見える化などを行い、企業の成長につなげていきましょう。
※掲載している情報は、記事執筆時点のものです
執筆=青木 恵美
長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「Windows手取り足取りトラブル解決」「自分流ブログ入門」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。
【T】
知って得する!話題のトレンドワード