
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
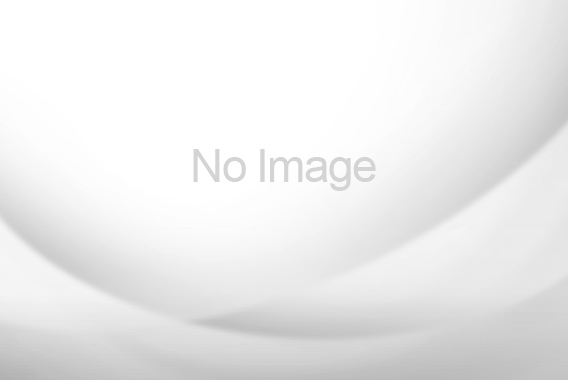
記事やブログや本は、速く失敗すること、早い段階で失敗すること、何度も失敗することを盛んに勧める。シリコンバレーの時代精神は、要はラピッドプロトタイピング、実用最小限の製品をリリースすること、欠陥をすばやく見つけて修正すること、そして成功に必要な前兆として失敗をたたえることだ。問題となるのは、レガシーな組織にいる、とりわけ、失敗を減らすかなくすことを目的とした組織にいるデジタルイノベーター志望者が、この概念をどうしたら適切に応用できるかということだ。
まずは、私たちの調査にあてはめて話を始めよう。デジタルに成熟している企業は、成熟していない企業よりもイノベーティブであることは、何ら驚くようなことではない。だが、イノベーティブであるということは、単にイノベーティブなことをするという意味ではない。むしろ、イノベーションを伝導する組織環境を育てることなのである。どこで見つけたものであれ、新しいアイデアにオープンであるということである。
さらに重要になるのは、イノベーティブであるということは、そうしたアイデアに基づいて行動しようという意欲があるということだろう。急激に変化する環境で、イノベーションがビジネスの成功に不可欠だということに、大半の企業のリーダーは理論の上では同意するだろう。現実には、デジタル時代以前に誕生した組織の大半は、次の二つの理由からイノベーションに悪戦苦闘している。
1.大半のレガシー組織の文化は、変動を減少または除去するように発展してきた。変動は実験に不可欠であり、実験はイノベーションを引き起こす。
2.企業の中核をなすビジネスを効率よく効果的に営みながらイノベーションを起こすことは困難だと、リーダーが感じている。
私たちは調査対象者に、デジタル環境において、組織の効果的な競争力に影響を与えている最大の問題について質問した。圧倒的に多かった答えは、実験および人員にリスクを冒させることである。競合他社よりも成功裏にイノベーションを進めている企業でさえ、実験および人員にリスクを冒させることは、彼らが直面する唯一最大の課題だと話している。
なぜ多くの企業で実験がこれほど難しいとされるのだろうか? 実に簡単なことだが、過去50年以上にわたり、大半の企業は効率性を最適化し、運用上の変動を最小化するように構築されてきた。実験はこれに真っ向から反することなのである。従来型の企業が実験の必要性に苦労しているようすを、わたしたちは目の当たりにしてきた。それは、彼らが失敗することへの恐れに駆られているからだ。
若いデジタル企業の中には、「目的を達成するために」失敗を「来る日も来る日も」経験し、「それを心地良く感じている」企業もある。それは何とも魅力的だと、ANZの経営幹部でデジタルバンキング担当のマイレ・カーネギーは語る。その心地よさは、「彼らのミッションの大胆さに端を発する」。その一方で、老舗企業の多くは、まさに彼らの文化に「織り込まれた、失敗することへの恐れ」を抱いている。
カーネギーは続ける。「グーグルのような会社では、その目的は文字通り世界を変えることだ。同社は、崇高で達成不可能なミッションを自らに課している。多くのレガシー企業の場合、彼らは達成可能で、漸進的なミッションを抱いている。その結果として、漸進的なものを求めているなら目標を達成するだろうが、小さな、漸進的な結果しか得られないことは明白だ」。
多くの企業が実験に悪戦苦闘する主な理由は、失敗は忌避すべきものだと彼らが信じ込んでいるからだ。デジタル時代には、企業がどのように挫折に対処するかが、企業の生存能力を決めるかもしれない。新たな課題に直面することが当たり前になりつつあり、未知のものや実証されていないものがたくさんあれば、失敗は避けられないからだ。
よって、組織が実験を得意になるために重要な要素は、アイデアを試すこと、そこから学習すること、そして試した結果から生産的知見が導き出された場合には、迅速に評価できるようになることだ。企業は生産的失敗を受け入れる環境を作る必要があるが、イノベーターや起業家の速く失敗するというマントラは、失敗を見つけて除外するように仕込まれた組織からは疑わしく思われるかもしれない。速く失敗するというマインドセットよりも、「試して学ぶ」というマインドセットを採用するほうが、簡単かもしれない。
「速く試す」ためには、短期間のスケジュールを定めて実験する方法が良いだろう。実験を行う組織は、短い“スプリント”(例えば6週間から8週間の構想)で、組織の一つの側面を変えようとする。スプリントの最後に実験が終了し、成功か失敗か結論が出される。この一定のタイムフレームのおかげで、不安定なプロジェクトを長期間引き延ばすことなく、実験を辞めるのか再びフォーカスするのか、マネジャーは決断しやすくなる。
「速くテストする」に加えて、「小さくテストする」ことも重要である。企業は何十億ドルもかかるIT導入プロジェクトを、何か重大な教訓を得るためだけに失敗させたくはないだろう。よって企業は必ず、実験と学習の許容範囲を設けるようにしなくてはいけない。何かを学んで次に進めるように、失敗で被る損害を制限する小さな実験を設定すべきである。
最後に、「十分に試す」。企業はリスクをポートフォリオとして管理する必要があり、失敗を一定の許容レベル内に抑える必要がある。適切な失敗率は10パーセントか90パーセントか? それぞれの数字を、別々の企業のマネジャーから聞いたことがあるが、自分の企業にとっての生存可能領域を、必ず見つけなくてはいけない。しかし、十分に失敗していない場合は大胆さが足りない可能性もあることを、マネジャーは念頭に置くべきである。
「失敗」という言葉にはやはり否定的な意味合いがあるが、失敗をめぐる議論は変わりつつある。それでも、組織が速く失敗する必要性についての議論は、スピードの側面に重きが置かれ、“学習”の側面には重きが置かれていない。これは、ただ単にすばやく失敗して次のアイデアに移るという考え方ではない。失敗を価値あるものにするためには、失敗から知見を得なくてはいけない。「Aがうまくいかなかったから、Bを試そう」とわかっただけでは、十分ではない。Aがうまくいかなかった“理由を理解すること”から、知見が得られ、組織に学びが生じるのだ。
科学者によれば、彼らは仮説とアイデアを試すために実験を行うという。仮説の証明や反証から、科学者は知識を得る。同様に、組織も学ぶべき目標をもって実験に取り組むべきである。この観点からすると、試すことは(失敗と共に)、うまくいかなかったこと、もっとうまくできたかもしれないことについてのインプットまたは知見として重要になる。
組織レベルにおける学習のプロセスは、いくつもの異なる形をとることがある。ある組織にとっては正式な事後報告書かもしれないし、教訓を引き出すために実験結果を報告するセッションかもしれない。別の組織にとっては、プロジェクトチームが進行中の実験結果を提示し、別のチームからフィードバックを得るような、全員参加の会議かもしれない。また単に、チームに属していない社員が、プロジェクトの一環として生み出されたアイデアや情報を得るために、コラボレーションプラットフォームでチームの電子データを考察するだけということもあるだろう。さらにはチームを分割し、メンバーを新しいチームに組み入れて、社員の知識を新しい方法で結合させることもあるかもしれない。
要するに、組織はいくつかの異なる方法でその成功と失敗から学習できるが、組織で学習が意図的に行われている方法を明確に特定できない場合は、間違いなく成功と失敗から学べないということだ。大切なことは、組織が経験から学べるプロセスを明確に特定し、意図的に関わることである。
冒頭で挙げた、企業がイノベーションに悪戦苦闘する二つ目の理由は、何もかも投げ出して、新しいテクノロジーを用いた学習と実験にフォーカスを移すわけにはいかないからである。コア・ビジネスに影響を与えながら、そのコア・ビジネスを機能させるような方法で、彼らはイノベーションを進めなくてはいけない。BIDMCのCIOであるジョン・ハラムカはそれを、飛行中の飛行機を修理するようなものだと見なす。
「現在の環境の中でデジタルリーダーの立場にいることは本当に大変だ。飛んでいる最中にボーイング747の翼を変えるように頼まれているのだから。全面的な安全性や確実性、安定性を保ちながら、同時にイノベーションを達成する。いったい誰がこんな役目を引き受けたいと思うだろう? あるいは、この役割は別の役目に振り替える必要があるのかもしれない……タスクが多くの人たちに『分割され』変化のペースやストレスに対処できるように」。
デジタルに成熟している企業は、事業運営をしながらも、イノベーティブである方法を見つけている。その一部は、彼らのデジタルイノベーションによってもたらされる。企業が今まで以上に実験をするようになると、実験と効果的な深化とのバランスをとる必要性にさらに圧力がかかる。組織学習の基礎をなす論文で、ジェームズ・マーチは組織学習における探索と深化のバランスの重要性について述べた。組織は、実行可能なビジネスを維持し、認められた能力を深化させながら、探索と実験を通して、新たなビジネスの方法を見つける必要がある。オライリーとタッシュマンは、このバランス行為をうまく達成している企業のことを「両利きの組織」と呼んだ。
シスコのジェームズ・マコーレーはこの必要性に同意し、次のように述べる。「デジタルトランスフォーメーションとなると、どんな大企業も直面する主な課題の一つは、新規ビジネスに進出しながら、既存ビジネスを維持することだ。この二つの間には、ときにあつれきが生じるかもしれない。これは、イノベーションを起こし、その言葉のもっとも肯定的な意味で自らを破壊しようとするときに、すべての大企業が乗り越えなくてはいけないことである」。
執筆=訳者=庭田 よう子
翻訳家。慶應義塾大学文学部卒業。おもな訳書に『目に見えない傷』(みすず書房)、『ウェルス・マネジャー 富裕層の金庫番』(みすず書房)など。
【T】
MIT×デロイトに学ぶ DX経営戦略