
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
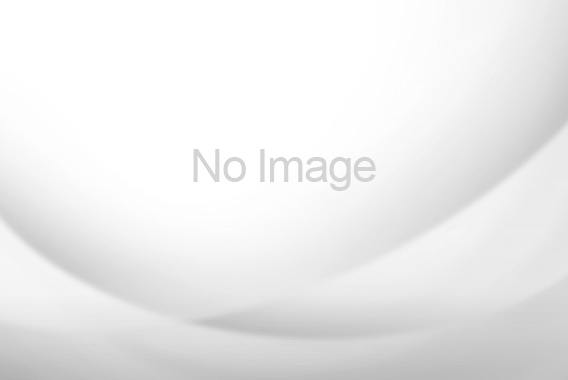
近年「ほめて育てる」ことの大切さに触れる機会が多くなりました。挫折しそうになったとき、思うような結果が残せなかったとき、気持ちが弱ったとき、親や友人からほめられることで自信とポジティブさを取り戻し、素晴らしいパフォーマンスを発揮できた……という話は、スポーツ界や教育界などさまざまなところで耳にします。子育てや部下の育成を成功に導くキーワードとして、「ほめる(叱らない)」を軸に置く例も少なくありません。
この原稿では「ほめて、育てる」をテーマに、部下の育て方を論じていきます。
今の日本では「精神論」や「厳しいだけの教育・訓練」などは時代遅れであるとして、敬遠・否定される傾向にあります。教育界や子育て分野では、「ほめて育てる」という考え方が半ば常識として定着したと考えられます。
しかし従来の「厳しい教育の効果」を信じる世代からは、この常識に懐疑的な目を向ける人もいます。この「成長を促すためにはほめるべきか、叱るべきか」という疑問に関するある実験結果があるので紹介しましょう。
1964年、アメリカの心理学者ローゼンタールは教師と生徒を使った教育心理実験を行いました。ローゼンタールは「生徒に期待し、ほめる教師」と「生徒に期待せず、無関心な教師」にそれぞれ生徒を持たせ、その経過や結果の違いを明らかにしようとしました。
実験終了後、「期待を受けて教育された生徒は成績が伸び、期待されなかった生徒はもともとの能力以上の成長は見られなかった」という結果が導かれました。そして前者は「ピグマリオン効果(人は周囲から示された期待通りの成果を出す、あるいは期待があったときのほうがないときよりも高い能力を発揮できる)」、後者は「ゴーレム効果(周囲の期待が低い場合、人はその低い期待通りの結果しか出せなくなる)」と名付けられました。
実験結果を一言でまとめると、「人は周囲の期待の有無によりパフォーマンスが変わる」ということになるでしょう。この実験が普遍的な真理を証明したというわけではありませんが、時代や国が違っても、人は他人に期待され、認められると能力をますます発揮する傾向があるということは、しっかり理解しておいてください。
「ピグマリオン効果」の説明に頼るまでもなく、ほめられたときの気持ちや行動の変化は、多くの人が自身の経験に基づいて理解できているはずです。簡単に説明すれば「人はほめられたらまずうれしくなり、その後前向きな気持ちで以前よりも自発的・積極的・能動的になる」となります。
ここでは人をほめた後に起きる変化について、「ほめた側」「ほめられた側」「職場の雰囲気」の3つに分けて説明します。
1.ほめた側/相手が心を開き、距離感が縮まる
人をほめたときの効果の代表例。「ほめる」ということは、すなわち「相手(の人間性・行動の結果・努力の経過など)を受容し、理解し、評価する」ことです。
結果に結びつかない努力が会社の中で見過ごされることはしばしばあるものですが、「ほめる」という行動を相手に示すことで、相手は「この人は自分のささいな成果や努力を認めてくれた上で、高い評価をしてくれている」と受け止めます。良い評価をしてくれる人の周りに人が多く集まる理由は、もはや説明する必要はないでしょう。
2.ほめた人自身の高評価につながる
厳しい環境で育てられた人は、「ほめたほうがいいのは頭では分かっていても、なかなか相手をほめることができない」と悩んでいることがあります。
日本では昔から慎みや謙遜を美徳としており、欧米各国のように感情をあらわにしたり、人前で誰かをほめたりすることに慣れていないことも影響しているかもしれませんが、だからこそほめるという行動をとれる人はそれだけで他の人よりも魅力的な人物に映ることでしょう。
3.相手が変わる
周囲から期待されると、人はその期待に応えたくなるもの。「あなたは優しい人なんだね」とほめられたら、その人は次から「優しい人」として振る舞いたくなるのではないでしょうか。
他人がほめた通りに変化するわけではなく、また短期間に効果が出るというものではありませんが、ほめられた人は(性格的・行動的に)以前よりも好ましい方向に変化する可能性は高いでしょう。ただし、言うまでもなく「ほめること」がただの人心操作のテクニックとして使われた場合は論外です。心から相手を認め評価したとき、その効果が表れます。
執筆=坂本 和弘
1975年栃木県生まれ。経営コンサルタント、経済ジャーナリスト。「社員の世代間ギャップ」「女性社員活用」「ゆとり教育世代教育」等、ジェネレーション&ジェンダー問題を中心に企業の人事・労務問題に取り組む。現場および経営レベル双方の視点での柔軟なコンサルティングを得意とする。
【T】