
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
私は企業の人事部や教育研修担当の方と話すとき、「皆さんの会社ではどのような教育をしていますか?」と必ず聞きます。すると「うちの会社は説明会でけっこう厳しいことを言っているから、(新入社員の心がまえができていて)大丈夫です」という答えが多く返ってきます。
しかし、これはたいていの場合、間違っています。会社と新入社員の関係は、恋愛に似ています。恋愛は、相手を好きになるときに、良いところを見て好きになりますよね? 好きになるときは、相手の悪いところは見えません。
相手が「私は、わがままだよ?」と言っていても、好きになるときはそれが気になりません。いざ、付き合い出してから「お前はわがままだなぁ?」「だから言ったじゃん?」と徐々に悪いところが気になり出します。
その会社に入ることを選んだ新入社員にとって、説明会で良いところ、悪いところの説明を両方受けたとしても、良いところが気に入っているから、入社するわけです。悪いところの説明は頭に入りません。新入社員の会社への期待値は、こうして上がります。その期待値がぐっと上がった新入社員に対して、一般的な新入社員研修で何を教えているでしょうか?
仕事に取り組む姿勢や、やる気を養う「モチベーション教育」あるいは実際の業務に必要な専門知識や社会人としてのマナーを教える「スキル教育」「知識教育」がほとんどです。 ここで、新入社員の職場に対する期待値は、さらに上がります。「ようし、やってやるぞ」と思うわけです。ところが実際の現場は、新入社員にそんな活躍を期待していません。それどころか、ゆとり世代が社会に出始めて以降、上司世代の新入社員に対する期待は年々下がっています。
メンタルが弱く、叱ればすぐに落ち込み、パワーハラスメントだと騒ぐ。私の経験から言って、現在の上司世代は新入社員が嫌いで、いらないと思っている人のほうが多いです。新入社員の現場に対する期待の大きさと、現場の新入社員に対する期待の小ささ。ここに大きなギャップがあるのです。
従来通りの新入社員研修では、このギャップを調整することが難しくなっています。結果、期待を高めた新入社員が現場の厳しさにぶち当たり、大きなギャップで心が折れてしまうのです。人事部は新入社員にとって、「大丈夫か?がんばろうね」とやさしく励ましてくれる、学校の先生のような存在です。それが人事部の仕事ですから仕方ありませんが、ちょっと問題があります。
現場の上司は、人事部のような人ばかりではないからです。新入社員研修を終えて現場に配置されると、いろいろなタイプの上司のもとで働くことになります。ちょっと仕事ができなければ、簡単に見放されてしまうこともあるでしょう。あまりにも大きなギャップに、新入社員がモチベーションクライシスを起こしてしまうのです。
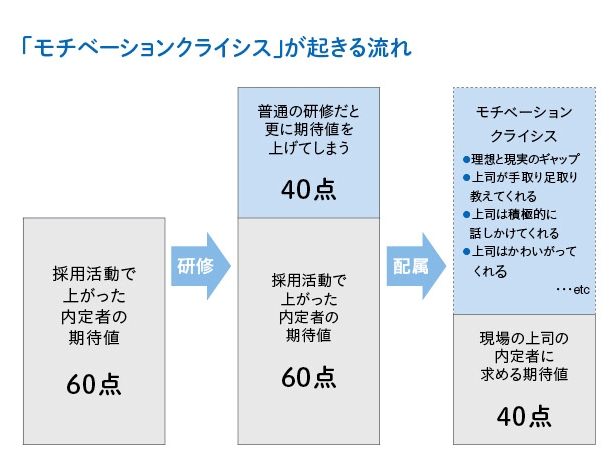
最初の新入社員研修で、実際の現場にはさまざまな上司がいることを教えなければいけません。「お前ら、現場は厳しいぞ」とはっきり言うのです。例えば、スキル研修でホウレンソウ(報告・連絡・相談)がビジネスの基本だと教えているとします。しかし、新入社員が配属された先の上司が、すべてホウレンソウを重視しているとは限りません。部下が念のために物事を確認してくるのを好まない上司もいます。「何度も聞いてくるなよ」と言う上司も、「なんで確認しないんだ」と言う上司もいます。上司によって仕事の進め方がまったく違うという現実を研修中にしっかりと教え、新入社員が抱く、現場への期待値を思い切って下げておくことです。これで、モチベーションクライシスを防ぐことができます。
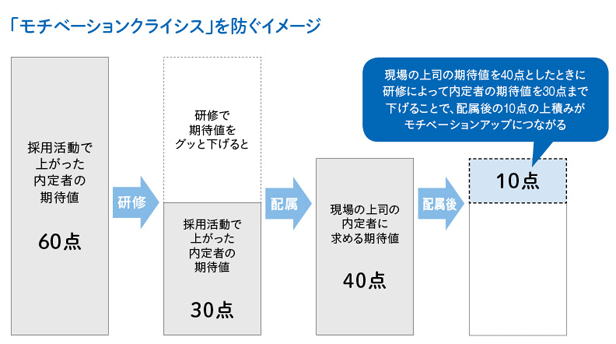
それと同時に、新入社員に対する期待値、例えば「半年後にアシスタントのリーダーになってもらう」といったことを、上司はもちろんOJT指導員や同僚など、配属される職場の全員が共有して、新入社員と接するのが大切です。ゆとり世代は環境依存度が高いため、周囲に異なることを期待する人がばらばらに存在すると、それだけで混乱してしまうからです。
ゆとり世代の若者にちょっと冗談めかしたことを言ったとき、真に受けてしまった経験はありませんか? 彼らはそのくらい「素直」です。1カ月後の目標、3カ月後の目標、半年後、1年後と小刻みな目標を立ててやり、先輩や上司が共通してその目標を口にすることで、ゆとり世代はその用意された環境に安心し、「素直に」取り組むのです。
モチベーション教育やスキル教育だけでは足らない、ゆとり世代の社員教育には何が必要なのでしょうか。第1回で「マイナスのところにいるゆとり世代を、スタートライン、つまりゼロのところまで引き上げる教育が必要」と書きました。それが「社会人としての心がまえ=教えられ上手・育てられ上手・怒られ上手になる」教育です。
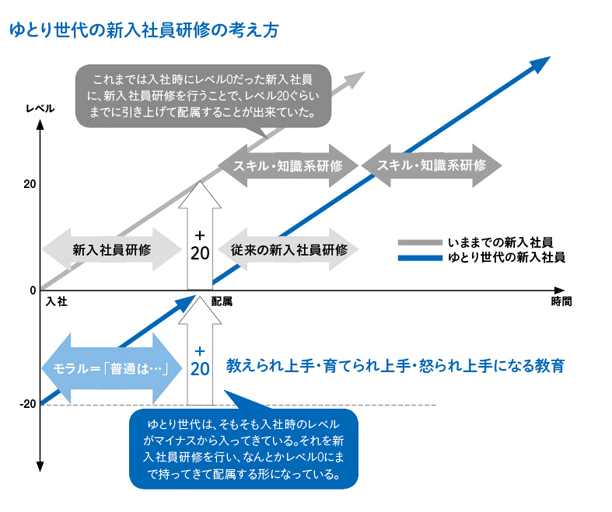
現実のビジネス社会に適さない価値観を持ったまま大人になったゆとり世代を、モチベーション教育やスキル教育といった普通の教育を始めてもいいレベルまで引き上げるのです。そのために、社会人としての心がまえ、働くということに対するモラルを徹底的に教えることが必要になります。
では、ゆとり世代には、どんな心がまえが足りないのでしょうか? 私が教育・研修の現場を通じて「必要不可欠」と痛感したものをまとめると、次の4つになります。
1.「自立・自責」の考え方
2.会社は「お金儲けの筋肉の訓練所である」の考え方
3.会社には必ず「期待値」があること
4.「教えられ上手を目指せ」という考え方
この4つの心がまえを身に付ければ、ビジネス社会でもまれても簡単には腐らないメンタル力を持たせることができます。その後から、モチベーションやスキルを教えていけばいいのです。
執筆=柘植 智幸(じんざい社)
1977年大阪生まれ。専門学校卒業後、自分の就職活動の失敗などから、大学での就職支援、企業での人財育成事業に取り組む。就職ガイダンス、企業研修、コンサルテーションを実施。組織活性化のコンサルティングや社員教育において、新しい視点・発想を取り入れ、人を様々な人財に変化させる手法を開発し、教育のニューリーダーとして注目を集めている。さらに、シンクタンクなどでの講演実績も多数あり、毎日新聞、読売新聞、産経新聞、経済界、日経ベンチャーなど多数のメディアにも掲載される。
【T】
“ゆとり君”と働くために覚悟しておくこと