
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
私は就職氷河期といわれた1990年代末に専門学校を卒業しましたが、就職にことごとく失敗しました。専門学校の恩師に誘われて就職セミナーの手伝いのようなことを始めました。それを大学に売り込んだり、企業に新入社員研修を売り込んだりするようになり、今の仕事の基礎を築きました。
25歳のときに会社をつくり、それまでの儲けがほとんど出ないNPO的な仕事ぶりを改め、きちんとしたビジネスにしようと一念発起しました。でも、そう簡単にことは運びません。専門学校時代の後輩を中心に7人のメンバーで今の会社、じんざい社を興したもののなかなか儲からない。最終的には、そのうち5人が辞めてしまいました。
当時の私は、事業がうまくいかないことをほかのメンバーのせいにしていたんです。つまり、「他人の責任」=他責にしていました。社員に「お前のレベルが低いからだ」なんてことを本気で言っていました。レベルが低いやつには辞めてもらいたい、でも一人にはなりたくないという中途半端な気持ちでした。そんなとき、ある先輩にいただいたアドバイスが「柘植くん、もしかしたら本当にそいつの能力がないのかもしれない。でも、能力がないから辞めたんじゃなくて、そうさせてしまっている柘植くん自身に責任があるんじゃないの? それが分からないと成長しないよ」というものでした。
そのとき、「自分の責任」=自責という考え方をまったく持っていなかった自分に気が付いたのです。辞めてしまったメンバーと一緒にやろうと決めたのも、そのメンバーに仕事をまかせたのも自分なのに、すべて他人の責任にしていたのです。仕事を始めて5年、25歳になって初めて「これからは全部、自責でやっていこう」と決めました。それから、すべてがうまく回り始めました。
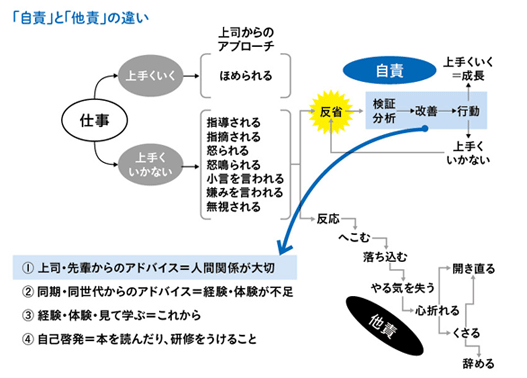
さて、ゆとり世代は競争をほとんど経験していませんから、誰かに負けたり、失敗したりという経験が極めて少ないです。また、根拠のない自信を持っていますから、失敗したり、仕事で成績が上がらなかったりしたときに「自分が悪い」と考えず、反省する価値観がありません。「責任は他にある」と当然のように考えます。常にいい環境に置かれ、「ほめて伸ばす」良い先生に囲まれて生きてきましたから、「頑張れない原因は環境や先生にある」という「他責」の考え方が当たり前になっているのです。
職場でも仕事の失敗を周りの同僚や仕事の環境のせいにしたり、あるいは単に不景気のせいにしたり、自分のことは棚に上げて責任を相手に押し付けるようになりやすいのです。そう考えれば楽だし、簡単だという面もあるのでしょう。こうした考え方を持ったままでは、いつまでたっても「自分を成長させよう」と思えません。まずはゆとり世代の「責任」を外に向けたままでなく、自分自身に向けさせることです。「目の前で起きている事実や結果は、すべて自分自身がやったことだと捉えて結果を謙虚に見つめ直そう」と教えてください。
例えば「こんな会社だとは思わなかった」と不平不満を言う部下がいるでしょう。その場合は「最終的にこの会社を選んだのは自分なんだから、いつまでもそんなことを思っていても一歩も先に進まないよ」と気付かせましょう。自分のイメージと違ってしまったのは、どこかで自分が間違ってそう思ってしまったからであり、その間違いを見つけて改善することで、次の間違いを起こさないようにするのが大切です。
執筆=柘植 智幸(じんざい社)
1977年大阪生まれ。専門学校卒業後、自分の就職活動の失敗などから、大学での就職支援、企業での人財育成事業に取り組む。就職ガイダンス、企業研修、コンサルテーションを実施。組織活性化のコンサルティングや社員教育において、新しい視点・発想を取り入れ、人を様々な人財に変化させる手法を開発し、教育のニューリーダーとして注目を集めている。さらに、シンクタンクなどでの講演実績も多数あり、毎日新聞、読売新聞、産経新聞、経済界、日経ベンチャーなど多数のメディアにも掲載される。
【T】
“ゆとり君”と働くために覚悟しておくこと