
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
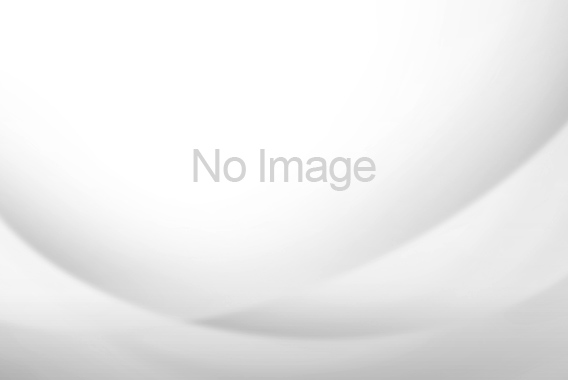
前回は、SNS個別の特徴と、「浅く広く」と「深く狭く」のどちらなのかを考える視点について紹介しました。そして、「浅く広く」タイプの代表であるツイッターについて詳しく説明しました。今回は、インスタグラムなどの残りのSNSについて解説しましょう。
インスタグラムはツイッターの次に広く浅いSNS。若い女性に人気で、ブランドイメージを上げるのにも向きます。インスタグラムでは、ツイッター以上に「#」を使った検索が活発です。
例えば、今の10代、20代の女性などは、「ハワイに行きたい!」と思ったら、グーグルではなく、インスタグラムで「#ハワイ」と検索します。グーグルだと、企業のホームページやウィキペディアが先に出てきてしまうので、物足りないのですね。「そんな公式情報では、本当のことは分からない」と、もっとリアルな情報を得るために、インスタグラムで検索するのです。逆に、企業がインスタグラムを上手に使えば、そんな若い人たちにとって身近で信頼性の高い情報共有のコミュニティーの中に入っていけます。
インスタグラムは写真がメインのメディアなので、写真映えする商材を持つ会社には非常に適しますが、写真に撮るものが特にない、という会社もあるでしょう。それでも若い人にアプローチしたいのならば、自社の世界観を表現できる何か具体的な物や風景、絵がないかを考えてみるといいと思います。考えるだけの価値はあると思います。
次に、フェイスブック。基本的に、友達として承認し合った人たちのコミュニティーであるという特徴があります。信頼関係のある人同士のコミュニティーの中で、「いいね!」が交わされ、情報がじわじわと広がっていくという性格のSNSです。流し読みされにくいのもいいところです。
フェイスブックの利用者は、30代から40代以上が中心と年齢が高めで、向上心の強いユーザーが多いのも特徴です。しっかりとビジネスをしている富裕層などに情報を広げたいという企業には非常に適しています。そうした特徴を持つフェイスブックは、自社を深く理解するコアなファンを育てるのに向くSNSです。
最後にLINE@。基本的に家族や友人との1対1のコミュニケーションツールであるLINEの中で、特定の会社やお店の情報を届けます。顧客の日常生活に深く狭く、入り込めるのが長所。クーポンを配るのに利用するお店が増えていますよね。
ツイッターとは逆で、ユーザーは登録しないと読めないですし、会社やお店にしてみれば、登録してもらわないと読んでもらえません。なので、広く情報を拡散するのには向きませんが、しっかり読まれる傾向があります。濃いファンを増やすのにピッタリですし、クーポンのようにダイレクトに購買につながりやすいのもいいところ。LINE@は今後、大切にしたいSNS。私はそう考えています。
図1 代表的な4つのSNSの特徴 
ここまで、4つのSNSの特徴を見てきました。こうした特徴を押さえた上で、前回紹介した男女別や年齢別のユーザー数(図2)も踏まえて、自社が主に活用すべきSNSを選びましょう。インスタグラムは、20代、30代の女性の利用者が比較的多く、フェイスブックは40代以上を取り込んでいるのが特徴。ツイッターの利用者は、年齢、性別とも幅広い、といった傾向が見えてくると思います。こうした違いを理解して、自社の製品、サービス、販売戦略などとのマッチングを考えましょう。
ほかにも今、人気があるSNSとしては、「TikTok(ティックトック)」と「Pinterest(ピンタレスト)」があります。15秒の短い動画をアップできるTikTokは、インスタグラムと同様、「#(ハッシュタグ)」で情報が拡散されます。「広く浅い」のもインスタグラムと似ていて、機能は「興味」を引くのと「シェア=拡散」が中心。利用者は男女を問わず10代、20代中心です。
Pinterestは画像がメイン。利用者は女性が多く、20代、30代中心。インスタグラムと比べると、インテリアや生活雑貨など実用的でコレクション性の高い画像が多いのが特徴。その分、情報の広がり方は狭く深く、検索されることも多いです。
これからも、さまざまな新しいSNSが登場するでしょう。そんな中で大事なのは、目先のことに惑わされずに、しっかりした判断軸を持つことだと思います。AISASというフレームワーク、そして、広く浅いのか、狭く深いのか。利用者の属性をデータで見るとどうなのか。こんな判断軸から本質的な特徴をつかみ、自社に役立つ形でフル活用していただきたいと思います。
さて、私は仕事柄、いろいろなSNSを利用してきましたが、本気でビジネスをしている忙しい人が、個人でそのすべてをやるのは現実的ではないと思います。経営者など忙しいビジネスパーソンが個人的にSNSをやるならば、「フェイスブックだけでいい」というのが、私の結論です。
それでは最後に、第8から第11回を通じて、絶対に押さえておいていただきたいポイントをクイズ形式で質問します。
Q:会社の公式SNSアカウントで、やってはいけないことは?
A 担当者一人に任せてしまう
B 上司が投稿内容を事前にチェックする
C 他社アカウントの投稿にツッコミを入れる
A:私の考える正解は「B上司が投稿内容を事前にチェックする」です。SNSの魅力は「人対人」のコミュニケーション。企業アカウントでも、担当者個人のキャラクターを生かすのが○。トラブル回避は、事前チェック以外の方法で。
本連載は、SNS時代におけるお金をかけないPRのポイントをお伝えしてきました。ここ数年でスマートフォンが当たり前のようにどの世代にも普及し、情報であふれかえっています。そのような中で消費者は企業が出す広告よりもリアルな口コミや、インフルエンサー、知人・友人からの情報を信頼できる情報として選別しているといえます。
メディアからの情報をSNSで発信し、拡散してもらう。費用をかけなくても売り上げにつながるPRとSNSを実践してみてください。まず何事も実践です。恐れず、PDCAを回しながら、長期的にブランドを育てていきましょう。
執筆=笹木 郁乃
山形大学工学部卒業後、アイシン精機で研究開発に従事。その後寝具メーカーのエアウィーヴの第1号正社員として転職し、PRに注力。売上高を5年で1億円から115億円に伸ばす急成長に貢献。鍋メーカー・愛知ドビーでもメディア露出により注文殺到でお届けまで12カ月待ちに貢献。その後、2017年ikunoPRを設立、2019年LITAに社名変更。企業のPR支援のほか、経営者や個人事業主、広報担当者などにPRスキルを伝える「PR塾」も主催し、約1000名が長期講座で学ぶ。これまで5年間常に満員御礼開催。2021年7月に2冊目となる著書「SNS×メディアPR100の法則」(日本能率協会マネジメントセンター)を上梓。発売日即日重版。プライベートでは一児の母。
【T】
ゼロ円販促