
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
国民のワクチン接種が進み、ワクチン接種証明書や陰性証明による行動緩和の議論に期待を寄せる業界は少なくないだろう。コロナ禍と緊急事態宣言により、営業時間の短縮や消費者の外出自粛が余儀なくされ、特に飲食や宿泊関連の企業・店舗の影響は計り知れないほど大きい。
コロナ禍と共存しなければいけない時代において、飲食店や宿泊施設では、利用者と従業員の感染防止対策の徹底がますます重要になる。これまで飲食店や宿泊施設のレストランなどでは「3密」(密閉、密集、密接)を避け、飛沫感染防止策を実施してきた。座席をアクリル板などのパーティションで仕切る、座席の間隔を離して着席する、食事中以外はマスクを着用して会話を控えるように注意書きを掲示するといったさまざまな対策が講じられてきた。
飲食店・レストランの感染防止対策の参考になるガイドラインが公表されている。一般社団法人日本フードサービス協会と一般社団法人全国生活衛生同業組合中央会が協力して作成した「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(改正)に基づく外食業の事業継続のためのガイドライン」だ。2020年11月30日に改正版が公表された。入店時や客席への案内、テーブルサービスとカウンターサービス、会計処理などの場面ごとに具体的な感染防止策を説明している。
飲食店・宿泊施設では、入り口に消毒薬を置いて、手指の消毒の徹底を促したり、センサーで検温するサーモグラフィーを置いたりして、発熱症状のある人の入店を規制するといった感染防止対策も広がっている。
ただ、検温で悩ましいのは「何度の場合、入店を断るか」だ。例えば検温で37度の場合、どう対処するか。平熱が37度を超える人もいるなど体温は個人差がある。また、検温するサーモグラフィーの精度に誤差が生じる可能性もある。店舗の接客マニュアルでも、具体的にお客さまにどう断るかを明記しない・できないケースも散見し、現場の判断に委ねている実情がある。
そこで一つの判断基準になる数字がある。感染症法では37度5分以上を「発熱」、38度以上を「高熱」と分類。検温で37度5分以上の人がいた場合、飲食店側は丁寧に説明して入店を断るといった対応も考えられる。前述のガイドラインでは、店舗の入り口に「発熱やせきなどの異常が認められる場合は店内飲食をお断りさせていただく旨を掲示する」としている。
Wi-Fi接続が考えられる機器
コロナ禍の中で、飲食店や宿泊施設で重要になるのがITの活用だ。宿泊施設では予約や会計処理、施設運営、顧客管理などですでにITを活用している施設は多い。そこで、飲食店を中心に新常態でのIT活用を考えてみよう。
例えば、飲食店ではタブレットを利用したPOSレジの導入が広がっている。コロナ禍で「非接触」のニーズが高まる中、会計は現金でなく、スマホによるQRコード決済などにも対応する必要がある。
Wi-Fi環境も重要だ。従来は利用者の利便性向上を目的として導入するケースが多かった。スマホやタブレットで店内や料理の写真を撮ってSNSに投稿するといった「口コミ」の効果が期待できるからだ。今は感染対策を支援する環境としてもWi-Fiは欠かせない。
例えば、料理のオーダー内容を店舗スタッフがスマホやハンディーターミナルに入力し、Wi-Fiを介して厨房のディスプレーやプリンターに注文内容を送信する。スムーズな注文と料理の提供に加え、店舗と厨房スタッフが接触する機会を減らせる。感染防止対策としても有効なIT活用術だ。
業務だけでなく、利用者にも快適なWi-Fi環境を提供するためには、無線アクセスポイントのタイプや同時接続数、通信速度、セキュリティなどに留意する必要がある。ビジネス利用に適したWi-Fiサービスも提供されており、店舗・宿泊施設のIT活用に向け、導入を検討するといいだろう。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です
執筆=山崎 俊明
【MT】
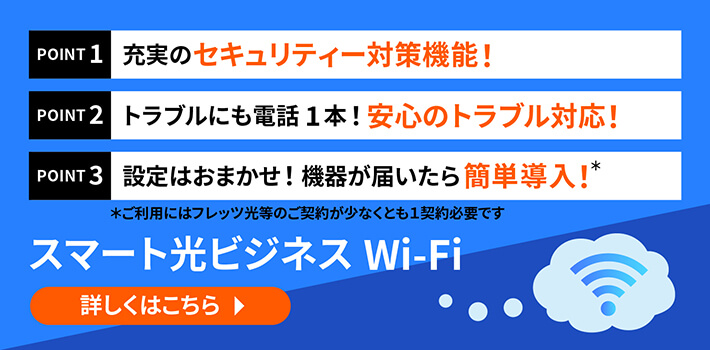
“新常態”に対応せよ