
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
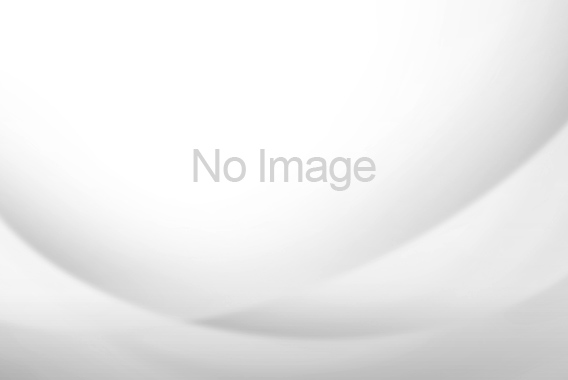
パフォーマンス心理学の最新の知見から、部下をやる気にする方法を紹介する連載。今回からは、どんなに苦労してもへこたれないリーダーのメンタル講座に移ります。上の立場に立てば立つほど、大きなプレッシャーやストレスを感じることも増えるでしょう。リーダーの心を支える考え方と技法をお伝えします。
どんなに苦労してもへこたれないリーダーのメンタル講座(1)
上司のためのストレスコーピング
ストレスは人間の心や体をむしばむものだと長くいわれてきました。けれど、この考え方がごく最近になって見直されています。ご存じかもしれませんが、スタンフォード大学のケリー・マクゴニガル教授の『スタンフォードのストレスを力に変える教科書』(大和書房)などのストレス研究の一群の発表によると、不安やプレッシャー、過去のつらい経験がエネルギーのもとになるのだという考え方です。
例えばマクゴニガルは、ある面白い実験を紹介しています。彼女の仲間のアリア・クラムの研究によるものです。全米の7つのホテルで客室係の実験参加者を募集しました。そして太って体格のいい彼女たちのカロリー消費量を調べてみました。重労働のため忙しいし、スポーツクラブに行くこともできないので太っていると話す女性たちです。
計測すると、客室係は1時間に300kcalも消費していたことがわかりました。シーツを換えたり、掃除をしたり、非常にたくさんの肉体労働をしますから当然でしょう。
一方、オフィスでパソコンに向かって作業をしている女性たちの消費カロリーは、1時間当たり100kcalにすぎません。でも、彼女たちは週末にスポーツクラブに行き、泳いだり走ったりしています。
そこでクラムはこの客室係たちに、客室係の仕事はオフィスで働く女性の3倍ものカロリーを消費していることをきちんと伝えました。スポーツクラブに行かなくても、彼女たちは十分運動していると説明してあげたのです。
すると、どうでしょうか。この女性たちは、数週間後にもう一度測定をしたところ、体つきが引き締まり、血圧、ウエスト・ヒップ比、体重などが理想通りになっていたのでした。この変化が起きるのに4週間あれば十分だったと言っています。
ここから得られるのはどんなことでしょうか。客室係の仕事がつまらなくて重労働でスポーツクラブにも行けないと思えば、それはストレスです。でも、今の仕事はオフィスで働く女性より3倍もカロリーを消費していると思った途端に、彼女たちは仕事が楽しくなり、痩せたというわけです。ストレスも考え方次第だという結果が出たのです。
実は私も20年前から、「ハーディネス(hardiness)」というテーマで「ストレスコーピング、3つのC」というビジネス研修をしています。ハーディネスとはストレス耐性のこと。人は同じ物事に直面しても、その物事に対する認知の仕方でストレス反応に違いが生じるというものです。
これはもともとアメリカのコバサ(Kobasa)という研究者が発表した理論です。3つのCはcommitment(関与)、control(統制)、challenge(挑戦)です。仕事に対しても、「自分に関係ないや」と思っていれば、会議で居眠りが出てしまう。これがコミットメントへの捉え方。そして、やらされている、つまりコントロールされていると思うと疲れます。でも、事態を自分がコントロールしていると思ったら、やる気満々で疲れません。
チャレンジもそうです。無理なことをさせられているのではなく、自分の潜在能力を開花させているのだと思えば、精神科医のロロ・メイが言うように(※)これは人間にとっての生きがい(快感)になるわけです。
※アメリカの精神科医で、多くの研究者に影響を与えたロロ・メイも「貢献」について、著書『失われし自己をもとめて』(誠信書房)でこう述べています。「あらゆる人間にとって共通の快感は、自己の潜在能力を開花することである」。できないことができるようになった自分の成長に、喜びを感じるというわけです。実は私は、全ての心理系研究者の中でロロ・メイが一番好きです。考え方が主体的だからです。私は講演の中で、仕事とはそういうものだと話しました。
上司も同じです。3つのC――関与、統制、挑戦の考え方を活用して、前向きに捉えてみてください。不遇にも自分がデキない部下を引き連れて苦労していると思えばストレスです。でも、部下の能力を引き出そうとしていることは、自分の上司力の成長のためであって、なかなかこれは挑戦しがいのある仕事だと思うと、部下指導はチャレンジですからストレスにならないでしょう。
また、あれもこれもいちどきに考えて決断し、指示を下さなければならない。もしも部下が失敗しても自分の責任だ、というふうに責任の重さを感じれば、上司のストレスは上がるばかりです。でも、部下たちが成功したときには、やはりこれは自分の名誉だと考え、万が一部下が失敗をしても、新たな学びを得られたと捉えれば、またとない有意義な経験になります。
実際、私は面白い場面を経験しました。エイチ・アイ・エスの澤田秀雄社長とジャパネットたかたの髙田明社長(当時)ともう1人のA社長が、あるシンポジウムの後、聴講者からの質問を受けるため、3人そろって登壇したときのことです。
1人の大学生が質問しました。「3人とも大きな失敗をしたと聞きましたが、損失を抱えて頭が痛くなったとき、どうしましたか。眠れなくなりましたか」と。
質問が終わると同時に、澤田社長と髙田社長はアハハと声を出して笑いました。「眠れなくなったことはないですねえ。とにかく寝てしまって、明日何とかしようと考えることにしましたよ」と2人とも異口同音。「胃が痛くなったこともない」とその場での答えでした。
そして3人目のA社長は、お2人とは違い「とんでもない事態になってしまった」と思って眠れず、結果、胃炎で入院したとの答えでした。「何とかしよう」という言葉は、これがつぶやきだったとしても「チャレンジ」です。一方で「とんでもない事態になってしまった」という言葉は自分のコントロール下で物事が動いていないというつぶやきです。つまり、起こった事態のほうが自分をコントロールしていると言っています。この時点ですでに3人のストレス耐性……ストレスに対する覚悟、受け止め方の違いは明らかです。
取りあえず寝てしまって明日考えれば大丈夫だという態度を心理学では「楽観主義的傾向」と呼びます。心理学的にきちんと比較していうならば、「楽観主義的傾向」とは、いわゆる楽天家とは異なります。楽天家は、困難は起きないと思っているいわゆる「能天気」な人であり、「楽観主義者」は、困難が起きても自分が才能、人脈、金脈などさまざまな資質を使って切り抜けられると信じている人です。例えば、大学生でさえ「楽観主義的な傾向のスコアが高い大学生のほうが悲観主義的傾向の大学生より長時間集中して勉強する」という面白い研究データもあります。
これについては私もいくつかの実験データを持っているので、確かにいえることです。悲観主義者よりも楽観主義者のほうがストレスを乗り越えていく力が強いのです。
上司になったら楽観主義に切り替えましょう。「問題は起きるだろう。しかし自分は乗り越えられる。なぜなら3つのCを持っている」と日ごろから口に出してみてください。
リーダーのメンタルを支える方法(1)
◆ ストレスは、考え方次第で、良いエネルギーへと変わります。
◆ コントロールされているのは自分ではなく、自分が事態をコントロールしているのです。
◆ 難問は、自分の成長にとって得がたいチャンスに挑んでいると捉えましょう。
※本記事は、2017年に書籍として発刊されたものです
執筆=佐藤 綾子
パフォーマンス心理学博士。1969年信州大学教育学部卒業。ニューヨーク大学大学院パフォーマンス研究学科修士課程修了。上智大学大学院博士後期課程満期修了。日本大学藝術学部教授を経て、2017年よりハリウッド大学院大学教授。国際パフォーマンス研究所代表、(一社)パフォーマンス教育協会理事長、「佐藤綾子のパフォーマンス学講座R」主宰。自己表現研究の第一人者として、首相経験者を含む54名の国会議員や累計4万人のビジネスリーダーやエグゼクティブのスピーチコンサルタントとして信頼あり。「自分を伝える自己表現」をテーマにした著書は191冊、累計321万部。
【T】
部下のやる気に火をつける方法