
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
パフォーマンス心理学の最新の知見から、部下をやる気にする方法を紹介する連載。部下に対して効果的にメッセージを伝える方法を紹介する第13回は、論理つまり理屈で迫ることへの戒めです。「理屈っぽい」と思われたら、相手の心に言葉が届きにくくなります。それよりもまずは感情を捉えることを考えるべきなのです。
部下の感情にまで届くメッセージ発信の技術(13)
理論や理屈を言い過ぎず簡潔でソフトな言い方をする
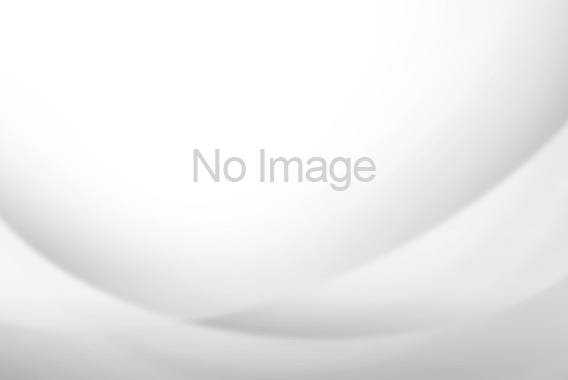
本連載第21回では「LEP理論」をご紹介しましたが、理屈で迫ると、実は相手の心にあっという間に防衛の壁が建ってしまいます。要するに文豪・夏目漱石がいみじくも言ったように、論理だけに頼れば、それは逆に反感や反発も強くなり、言った上司の首を絞めることになります。
上司も中堅以上になるとそのことが体験から分かっているのですが、入社数年後に主任や係長など、グループ内でのリーダー格になった人々は注意が必要です。彼らは自分に自信を持ち、ある意味仲間より優位に立っているという自負も手伝って妙に理屈っぽいことを言うことがあります。
私も最近、ビジネスマンのパフォーマンス研修で「僕はなぜか社内で仲間ができない。というか煙たがられている気がします」と相談に来た男性のTさんを見てすぐに「ハハン」と原因が分かりました。
彼は勉強家です。人より本も読んでいます。知識も豊富で、ちょっとした会話でも自分の考えと違うことがあると、相当にしつこく理屈を言います。「ウンチク男」と呼ばれそうな感じです。そこで私はこう言ったのです。
「理屈ではTさんは正しいですね。そして、もう少しそれをみんなが気持ち良く受け入れてくれるように簡潔でしかもソフトな言い方で言ってみない?」
彼には理屈でねじ伏せる手よりも、共感が重要であることを気付いてほしかったのです。「簡潔でしかもソフトですか……」と彼はやや不満そうでしたが、1週間後にメールが来て「先生に言われたようにちょっと理屈を控えて、『違っているかもしれないけれど』という一言を添えて発言したらなかなかいい調子です」とありました。
自信過剰で頭でっかちの部下は、何でもかんでもロゴスで片付けようと思います。「この問題のエビデンスはこれであり、それは何百何十何万円の損失をカバーするものであり、それは過去の取引で証明されています」という具合です。
全て言っていることは正しいのです。ただ、もしもあなたの部下がロゴス派で、例えば理屈や数値やエビデンスだけで、営業に行ったら、ほとんど営業成果は上がらないでしょう。成功者でしかも「支配欲求」の強い目上の人であれば、聞くや否や「この若造が」と反感を持ちかねないからです。
上司のあなた自身がロゴス(論理性)に走らず、パトス(感情)を捉えてから、ロゴスに入るという話し方をしていると、部下も自然にこれをミミクリ(模倣)します。
部下の感情にまで届くメッセージ発信の技術(13)
◆ どんなにそれが正しくても、理論や理屈を言い過ぎないようにしましょう。
◆ 部下が受け入れやすいように、簡潔でソフトな言い方に変えることでかえって伝わりやすくなります。
※本記事は、2017年に書籍として発刊されたものです
執筆=佐藤 綾子
パフォーマンス心理学博士。1969年信州大学教育学部卒業。ニューヨーク大学大学院パフォーマンス研究学科修士課程修了。上智大学大学院博士後期課程満期修了。日本大学藝術学部教授を経て、2017年よりハリウッド大学院大学教授。国際パフォーマンス研究所代表、(一社)パフォーマンス教育協会理事長、「佐藤綾子のパフォーマンス学講座R」主宰。自己表現研究の第一人者として、首相経験者を含む54名の国会議員や累計4万人のビジネスリーダーやエグゼクティブのスピーチコンサルタントとして信頼あり。「自分を伝える自己表現」をテーマにした著書は191冊、累計321万部。
【T】
部下のやる気に火をつける方法