
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
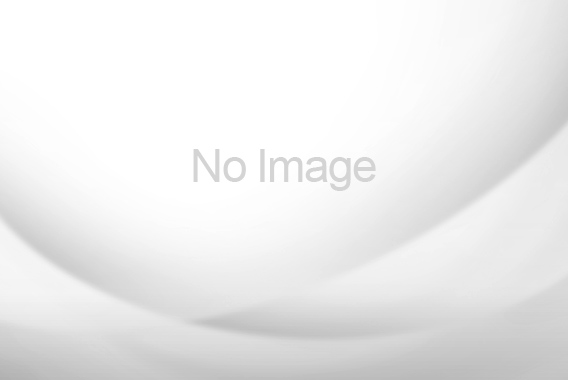 中国人にとって、現金を使わないキャッシュレス決済は当たり前になりつつある。かたや日本ではまだまだ現金主義が根強く、キャッシュレス決済への対応は後手に回っている。
中国人にとって、現金を使わないキャッシュレス決済は当たり前になりつつある。かたや日本ではまだまだ現金主義が根強く、キャッシュレス決済への対応は後手に回っている。
従来、私たちは、買い物やサービスを受ける際、現金を使って決済してきた。キャッシュレス決済として、以前から用いられていたのが、手形や小切手を使った決済だ。1960年代以降クレジットカードによる決済が普及。最近は、電子マネーやスマートフォンを利用した決済が広がっている。
日本でも電子マネーの1つである交通系ICカードの普及に見られるように、徐々にキャッシュレス決済は拡大している。しかし、国際的に見るとキャッシュレス決済の比率は低い水準にとどまる。2018年4月に経済産業省が公表した「キャッシュレスビジョン」によると、2015年時点では18.4%だ。韓国の89.1%、米国の45%と比較してかなり低い。
中国のキャッシュレス決済の比率は60%と非常に高い水準にある(2015年)。その要因として挙げられるのが、銀聯の設立とスマートフォン決済(スマホ決済)の普及だ。
中国ではVISA、マスターといった、欧米や日本でよく利用されているカードよりも「銀聯カード(Union Pay)」がスタンダードだ。2002年に中国国内の金融機関が共同で設立した銀聯は、決済オンラインネットワークを整備。中国全土で2000万店以上の店舗で利用可能だ。2016年の中国国内における銀聯の取扱高は72.9兆元(1116兆円)に達する。銀聯カードの多くは、決済と同時に銀行預金口座から引き落とされる「デビットカード」だ。
そうした決済環境に慣れた中国人訪日客に向けて、日本国内でも免税店やデパート、家電量販店をはじめ、コンビニやファミリーレストランなどが、続々と銀聯カード対応を開始。そうした店舗では銀聯カード利用者を対象にした優待、割引を行うキャンペーンも実施されている。
中国では海外への現金持ち出し額が厳しく規制されていて、高額な買い物ではカード決済を選択しなくてはならないケースもある。その意味では、中国人客に高額な商品やサービスを提供するビジネスでは、銀聯カード対応が必須といえる。
銀聯カードの普及に続き、中国国内で、最近急激に増えているのがスマホ決済だ。日本で、スマホを使った決済として有名なものには「おサイフケータイ」や「Apple Pay」がある。これらは利用可能な端末の機種やOSが限られる。一方、中国で普及しているのは、基本的にはスマホ端末を選ばず使える、画面にQRコードを表示するタイプの決済方法だ。QRコードは1994年に日本のデンソーが開発した四角形の二次元コードである。
中国で普及しているスマホ決済の代表が「AliPay(支付宝)」と「微信支付(WeChat Pay)」。AliPayは、中国の代表的なショッピングサイト「淘宝網(タオバオワン)」の決済用に生まれたサービスで、他の多くのネット店舗や実店舗で利用可能になっている。
一方、微信支付は、日本における「LINE」のように中国で広く使われているインスタントメッセンジャーアプリ「微信(WeChat)」に装備された決済サービスで、現在、4.5億人以上の中国人が銀行口座を登録して利用している。中国国内の店舗では、こうしたスマホ決済を導入しているところが多く、中国人は少額の買い物でも利用している。
日本において、スマホ決済は免税対応をしていない。そのため少額な買い物中心の業種・業態のほうが利用される可能性が高い。また一般的なカード決済より、決済手数料が低く設定されているケースが多いのも魅力だ。
今後、中国人訪日客にさらにお金を落としてもらうには、少しでも彼らが使いやすい決済サービスの導入を考えるべきだ。銀聯カードやスマホ決済の導入で、国内で普段やっている通りに支払いができる環境を整備してはどうだろうか。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です
執筆=林 達哉
【MT】
販路拡大のキモ