
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
地球温暖化はさまざまな場面で大きな影響を及ぼしている。ゲリラ豪雨などもその影響の一つだ。気温が上昇することは農産物の収穫を左右するだけでなく、産業構造にも大きな変化をもたらす。中小企業であっても地球上の一員であることに変わりはなく、サステナブルな企業としてCO2削減が求められる。しかし、規模の小さな企業にとってどんなことができるのだろうか。具体的なポイントを考えてみたい。
サステナブルへの対応は、世界的な潮流だ。地球温暖化がもたらす変化は産業構造を変えるだけではない。対応が遅れれば、やがて地球が人類にとって生きづらい星になってしまうことが危惧されている。その主な要因はCO2排出による気温の上昇。まず地球全体でCO2排出量を削減しなければならない。
企業にとっても、CO2削減への取り組みが社会的な要請となりつつある。目標とするCO2削減を実現しなければペナルティーが科されることにもなり、サステナブルであることを求める消費者からは受け入れられず、サプライチェーンからも閉め出されるおそれもある。
逆に、サステナブル企業への進化には多くのメリットがもたらされる。地球に優しい企業として認知されることで、好感度が上がって売り上げ増の結果がもたらされ、ESG経営ができていることで銀行などから好条件で融資が受けられたりする。資本家からも事業継続性が高い企業として評価される。事業規模の小さい中小企業も、同じ事業環境にあると考えるべきだろう。大企業は今後サステナブルであることを取引先にも求めるようになるだろう。安定的な調達ができることがサプライチェーンを構成する企業としての条件だからだ。こうしたビジネス環境の変化の中で、サステナブルな企業であれば優先的に取引してくれる可能性も高まる。
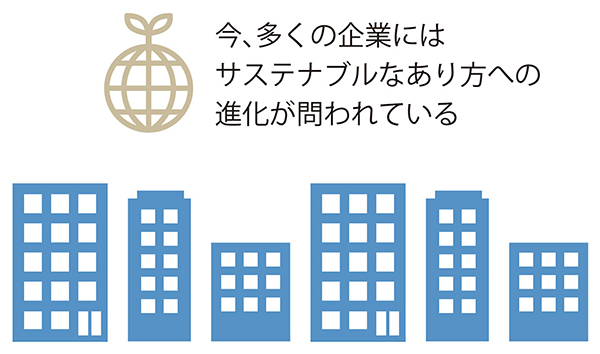
サステナブルな企業へと進化するためのポイントは、まずCO2の排出量の削減にある。CO2を排出しない仕事のやり方を実現することで減らしていく。そしてもう1つのポイントは限りのある地球資源の消費を抑えることだ。例えば、化石燃料を使わないことはCO2削減につながり、森林資源を残すことはCO2を吸収することにもなる。
企業活動においてCO2排出を削減する鍵はエネルギー消費をいかに抑えるかにある。業種業態によって消費するエネルギーの種類はさまざまだが、共通しているエネルギーとして挙げられるのは電力だ。特に日本では化石燃料由来の電力の占める割合が大きく、世界的にも課題とされている。この点、電力消費を抑えることは即CO2削減につながるだろう。
企業として電力消費を抑える最も分かりやすい対策は労働時間の短縮だ。稼働時間が短くなれば消費電力量は減る。実現できれば残業時のエアコンや照明などの電気代も減り、従業員への負担も軽減される。企業としての業績を落とすことなく、労働時間を短縮するには、生産性の向上を図るのが一番確実な方法だ。
そのためにお勧めしたいのがRPAの活用だ。多くの業務がコンピューター上で行われており、人手による単純な繰り返し作業も多い。これをRPAに置き換えることで業務は大幅に効率化できる可能性がある。RPAは今までより短時間で業務を処理し、24時間稼働できる。RPAに置き換えられる業務がないか検討してみることは重要だ。
次のポイントは紙の使用量の削減だ。紙は木材から作られている。この使用量を削減することは森林資源を守ることになり、CO2の吸収量を維持することにつながる。しかも紙代を抑え、紙を置くスペースを減らすことにもなる。目指すべきはペーパーレスな業務スタイルだ。そのためにはまず今の紙の書類をデジタル化することが必要になる。AIを使ったOCRは精度も高く、威力を発揮するはずだ。その上でデジタル化した書類をクラウドストレージに保管しておく。書類保管の必要がなくなり、いつでもどこからでもインターネット経由で取り出すことができるようになる。場所を選ばない働き方、テレワークも可能になる。
そしてCO2削減の切り札の1つとなるのが、このテレワークだ。自宅でオフィスと同じように仕事ができるようになれば、通勤の機会も減る。そうなればガソリンを消費する自動車による移動も少なくなる。全体で見れば大幅なCO2削減が実現されることになる。CO2削減は事業を継続するために求められている喫緊の経営課題だ。できるところからサステナブル企業へとかじを切ることをお勧めする。
執筆=高橋 秀典
【MT】
視点を変えて可能性を広げるITの新活用術