
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
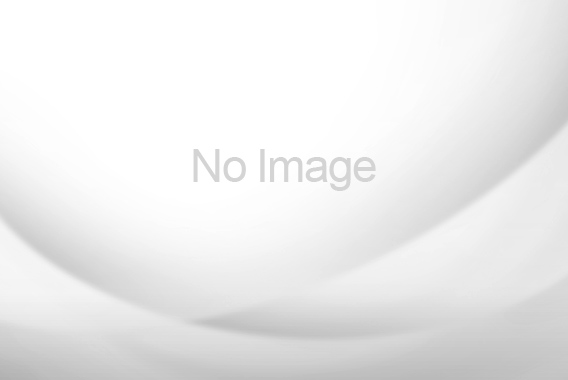
企業規模・業種業態を問わず、デジタルを活用したビジネス変革、DX(デジタルトランスフォーメーション)をいかに推進するかが大きなテーマになっている。そのカギを握るのがデータの活用だ。企業が蓄積するデータは重要な経営資源となり、新規ビジネスの創出や競争力強化の原動力となるものだ。だが、そのデータを脅かす事案が増えている。人ごととは言っていられない状況だ。
企業データを毀損するリスクは至る所にある。その1つがコンピューターウイルスの「ランサムウエア」だ。攻撃者は企業のサーバーやパソコンに保存されたデータを暗号化して使えなくする。そして、データを復号化する条件として金銭(仮想通貨など)を要求する。こうした手口から、身代金要求型ウイルスとも呼ばれる。標的型メール攻撃などと同様に攻撃者の手口も巧妙化しており、うっかりメールを開いてランサムウエアに感染するケースもある。身代金を払っても、データが元通りになるとは限らない。ランサムウエアに感染した場合、重要データであっても諦めざるを得ないのが実情だ。
また、台風や地震、集中豪雨などの自然災害でオフィスのサーバーやパソコンが被害を受け、保存されたデータが消失するリスクもある。パソコン操作のうっかりミスでサーバーのデータを削除したり、上書き保存したりする恐れもある。
こうしたデータに関わるリスクを回避するには、データをバックアップしておくことだ。万一、ランサムウエアに感染してもバックアップデータがあれば、身代金を支払ったり、慌てたりせずにすむ。また、自然災害については、本社とリモート拠点、クラウドなど地理的に離れた場所で相互にデータバックアップすればデータ消失のリスクを分散できる。被害を受けなかった拠点で事業継続すればBCP対策になる。
ちょっとしたデータの移動にはUSBメモリーが重宝されるが、セキュリティ上の観点から大企業では使用を禁止するケースが多いのが実情だ。また、比較的安価で大容量になってきてはいるものの、データの保存という観点から見ると物足りなさは否めない。
データ保存の手段として、パソコンにUSBケーブルで接続するHDD(ハードディスクドライブ)を導入する企業も多い。HDDは家電量販店などで手軽に購入できるものの、ビジネスデータを保存するには問題もある。パソコンに外付けするためHDDを机の上などに置くユーザーも見受けられるが、万一落下すれば衝撃でHDDが故障し、データを失いかねない。
突然の停電や落雷の影響でデータが破損したり、HDDの部品の経年劣化によりデータの読み書きができなくなったりするケースは少なくない。故障したHDDを修理するサービスもあるが総じて高額で、しかもデータが元通りに復旧できるとは限らない。
HDDの弱点はデータの保存に関わる問題だけでなく、複数台のパソコンとデータをやり取りするのが難しいところにある。個人用パソコンの内蔵HDDの容量が足りずに外付けのHDDを利用するのはともかく、業務でHDDを利用するのは、もはや古いやり方と言わざるを得ない。外付けHDD使用禁止とする企業もある。
そこで、データの保存や共有に適したストレージ機器がNAS(ネットワーク・アタッチド・ストレージ)だ。オフィスのネットワーク(LAN)上に設置し、LANに接続されたパソコンデータの保存と共有が可能だ。ネットワークでつながる他拠点もNASのデータを利用でき、企業のデータ活用を促進する。
NASは複数のHDDを搭載するなど、信頼性を高める機構を備える。万一、パソコン操作のうっかりミスなどでデータを消してしまった場合、作業前に遡ってデータを復旧する機能などを備えるタイプもある。
一方でNASは社内ネットワーク上に設置するため、データの保存・共有ではネットワーク機器の安定稼働も欠かせない。初めて使うときなどは不安も伴うだろう。詳しい人やオフィスにIT担当者がいなければ、外部のIT専門家の力を借りる方法も考慮しなくてはならない。そういった状況が予測される場合には、サポートがサービスとして付与されているものを選んだほうが運用はうまくいくことが多い。NASを検討する際にはネットワークを含め従来のIT環境を見直し、IT活用を支援するサポートサービスを活用するとよいだろう。
執筆=山崎 俊明
【MT】
視点を変えて可能性を広げるITの新活用術