
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
2019年5月10日に「IT人材白書2019」(調査年:2018年度)が発表された。情報処理推進機構(IPA)が毎年発表し、IT人材の現状と今後の動向を示すものだ。同白書から見えてくるのは、デジタル変革への企業の取り組みとその成功要因、そして依然として続く、IT人材の深刻な不足状態である。
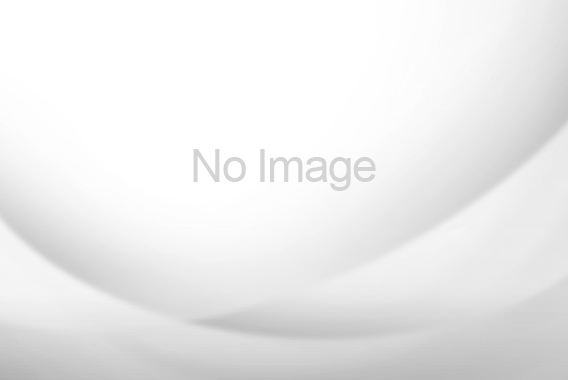 IT人材白書2019のサブタイトルは「人から始まるデジタル変革 ~イノベーションを生む企業文化・風土を作れ~」。冒頭に「“人”こそがデジタル変革を牽引し、日本の産業競争力を高め、希望に満ちた明日を築く要である」と述べられている。
IT人材白書2019のサブタイトルは「人から始まるデジタル変革 ~イノベーションを生む企業文化・風土を作れ~」。冒頭に「“人”こそがデジタル変革を牽引し、日本の産業競争力を高め、希望に満ちた明日を築く要である」と述べられている。
同白書では、既存のビジネスモデルの転換を「デジタル化」と定義した上で、967社のユーザー企業と1206社のIT企業に対してアンケート調査を実施。結果、36%のユーザー企業が「デジタル化に取り組んでいる」と回答した。
興味深いのは、その内訳である。「取り組んでおり、成果(収益)が出ている/出始めた」という回答は11.6%で、24.4%は「取り組んでいるが、成果(収益)がまだ出ていない」と回答している。デジタル化に取り組む企業の多くで、いまだに成果が上がっていない実態が浮かび上がった。
その原因は明確だ。デジタル変革の原動力となる人材が不足しているからだ。「“人”こそがデジタル変革を牽引」と述べられた冒頭のメッセージは、IT人材が不足している実態の裏返しでもある。
日本全体でIT人材の不足感は続いている。同白書ではIT人材の“量”に対する過不足感の5年間の推移が示されており、ここ3年は「大幅に不足している」という回答が増加している。2018年度は3割強に達し、人材の“質”に対する不足感も同程度ある。特にユーザー企業では、IT人材の“量”が「大幅に不足している」と回答した割合は、2014年度の16.2%から31.1%に倍増している。
一般的に、大手企業は新卒採用、中途採用、常駐派遣など、ありとあらゆる手段を使って必要なIT人材を確保しようとする。それでもIT人材が不足している状況だ。この現状をどう打開すればよいのだろうか。
IT人材白書2019に採用成功のヒントが掲載されていた。同白書によると、中途採用を積極的に実施したり、強みとなる自社の文化や風土、魅力を持ったりしている企業が採用に成功しているという。
デジタル化に「取り組んでおり、成果(収益)が出ている/出始めた」と回答したユーザー企業の工夫を見ると、採用面での成功のヒントが見えてくる。2割強が「デジタル化ビジネスの具体的な内容と業務内容を提示」。約1割が「柔軟なワークスタイル(週3-4日勤務や自宅勤務)」「例外的な処遇を提示(通年採用とは異なる処遇)、人事制度の改定(期間を限定した契約社員採用など)」を取り入れる。
このデータから見えてくるのは、デジタル化に対する明確な戦略が採用を成功させ、成果をもたらすという方程式の存在だ。明確な戦略があるからこそ、具体的な業務の内容を提示でき、働き方改革の推進や例外的な処遇を断行できる。
しかし、こうした戦略の立案やワークスタイルの変革、人事制度改定は、体力のある大企業や斬新な取り組みをしやすいスタートアップ企業は別として、普通の中小企業では簡単ではない。中小企業の採用においては、IT部門配属を採用の前提としないケースも多い。優秀なIT人材がデジタル変革に不可欠なのに、IT部門に特化した中途採用もできないし、特別待遇も設けられない。さらに、人件費の課題もある。ITが高度化・複雑化する中でデジタル変革を進めるには、高度な専門知識を持ったIT人材でないと自社に最適なIT活用を進められない。当然、そういった高度なIT人材の人件費は高い。
デジタル変革は待ってはくれない。腰を据えて高度なIT人材の採用を進めなければならない。ただ、自社にとって採用が難しいと判断するなら、IT関連は専門企業にアウトソーシングしてしまうという選択肢もある。デジタル変革にIT人材は不可欠であるが、人材の“質”“量”ともに不足している認識を持ち、アウトソーシングも視野に入れるのが現実解だろう。
執筆=高橋 秀典
【MT】