
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
6月に働き方改革関連法が成立し、残業に関する規制が強化された。業務効率のアップは企業にとって待ったなしの状況だ。そのために不可欠なのはITの活用。それによって、時間や場所に制約されない柔軟な働き方が可能になる。オフィスの内外を問わず、業務に必要な情報にアクセスができるようにしたり、緊密な情報のやり取りができたりする環境を整えるのだ。
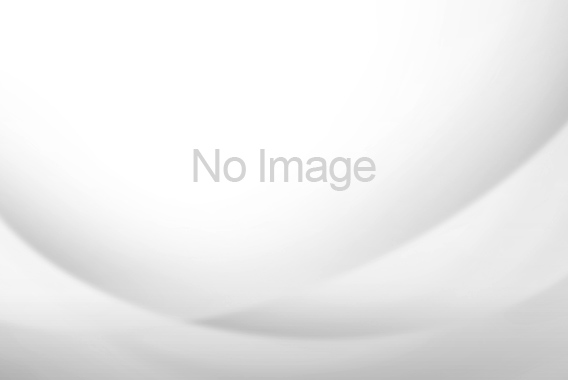 それにはまずLANの整備がキモになる。例えば、テレワークを導入した場合、出先や社員の自宅など、社外から社内LAN上のサーバーやシステムにアクセスして仕事を行う。あるいは、社内LANからインターネットを経由して、メールやファイル共有などのクラウドサービスを利用して業務を効率化する企業も増えている。
それにはまずLANの整備がキモになる。例えば、テレワークを導入した場合、出先や社員の自宅など、社外から社内LAN上のサーバーやシステムにアクセスして仕事を行う。あるいは、社内LANからインターネットを経由して、メールやファイル共有などのクラウドサービスを利用して業務を効率化する企業も増えている。
こうした企業において、万一、社内LANを構成するルーターやスイッチなどのネットワーク機器にトラブルが発生すれば、業務に支障を来す。ネットワークのトラブルでクラウドサービスにアクセスできなくなり、メール送受信やファイル交換が行えなくなれば、業務への影響は計り知れない。
ただ、中小企業の場合、トラブルに対処するシステム専任の担当者を置くのが難しい。しかも、ネットワークにつながる機器の種類と台数は増加している。トラブル解決は難しくなるばかりだ。例えば、社内のパソコンがインターネットにつながらない。そんなトラブルが発生した場合でも、原因がパソコンにあるのか、社内のネットワークにあるのか、インターネットに接続する回線側にあるのか。これらを正確に判断して、対処できる人材は社内になかなかいない。
ITに少し詳しい程度の社員がトラブルを解決しようとしても、原因を切り分けて、早急に復旧するのは非常に難しい。ネットワーク機器のメーカーや販売会社、インターネットサービスプロバイダー、通信事業者などに電話で問い合わせ、原因究明と復旧を依頼しても、原因が分からず、たらい回しになり、復旧が遅れるという話も枚挙にいとまがない。
ITの専門知識と高いスキルを持つ人材を確保・育成し、自力でITを運用するのは中小企業にとってハードルが高い。ならば、むしろ外部の専門サービスに社内ネットワークの運用管理をアウトソーシングするほうが現実的だ。
外部の専門サービスを活用すれば、24時間365日、ネットワークの監視・運用を行い、万一の障害時には復旧作業を行ってくれる。社内に少数の担当者を置いても、その実現はほぼ無理なのを考えれば、どちらが得かは火を見るより明らかだ。
業務効率化のために整備した社内ネットワークの運用・管理のために、新たな人材を雇用したり、配置したりするのは得策とはいえない。そうした業務は外部にアウトソーシングして本業に集中する。それが中小企業の働き方改革にあった方法だろう。
執筆=山崎 俊明
【MT】